
2006年
翔ぶが如く(1) * 司馬遼太郎 * 文春文庫 * 2006/07/07
 西郷隆盛の、明治維新後の生き方を描く。維新前は、幕府体制を倒すべく、最もめざましい活躍をした西郷であったが、太政官を中心とする官僚国家ができると、突然自分が用のない存在であることに気付く。
西郷隆盛の、明治維新後の生き方を描く。維新前は、幕府体制を倒すべく、最もめざましい活躍をした西郷であったが、太政官を中心とする官僚国家ができると、突然自分が用のない存在であることに気付く。
たしかに陸軍大将などの国家の最高位についていながら、実際の役所の創設や制度の構築は、有能で若い連中が次々と受け持っている。維新前からの部下であるかつての人斬り、桐野利明は、進歩的な時代に合わない。
川路利良は、自分が推挙した薩摩人だが、パリに留学して警視庁の基礎を学んで帰国するとすっかり政治的な方向が違ってしまっている。大久保利通はかつて薩摩藩で島津斉彬(なりあきら)のもとに共に育った仲間であったが、今ではことあるごとに見解が相違する。
留学している政治家たちの留守を預かる木戸孝允も三条実美(さねとみ)にしても、西郷の主張に表立って反対しないものの、留学している者たちが帰ってくるまで決定を出すことができないでいる
西郷が、心臓の調子が悪くなるほど精神的に追いつめられていたときに、救いになりそうだったのは「征韓論」であった。といっても一般に言われているようにただ朝鮮を攻めればよいというものではない。
ヨーロッパの列強が次々と進出する中、中国、日本、そして朝鮮が結束して近代的な国家体制を築き対抗しなければ、あっという間に餌食になってしまうという考えに基づくものであった。西郷は、自分が特使として朝鮮に赴き、そこで殺されてもかまわないと思っていた。
だが、政治家たちの中には、西郷が野心を持っているのではないか、かつての足利尊氏のように、国民的人気を持って政権を執ってしまうのではないかと疑う者も少なくなかった。
人体 失敗の進化史 * 遠藤秀紀 * 光文社新書258 * 2006/07/13
著者は動物の遺体解剖によって進化の謎を解く科学者である。動物園から貰い受けたタヌキの死体からカバやキリンに至るまで、あらゆる動物を解剖し、そのからだの仕組みの謎に迫る。
この本のもう一つのメッセージは、遺体解剖に対する行政の冷たい目を紹介し、営利を産み特許を取ることが至上とされる昨今の「行政改革」を批判し、地味で基礎的な研究がもっと自由に行われることへの提唱である。
動物の進化は、最初の単純な形態から、さまざまな「設計変更」を受けて今日の形に変化していった。汗腺から乳腺が作られ、顎の付け根から耳の中の音響を伝える骨が借用され、鰓のまわりの部分からほ乳類の顎が、魚の浮き袋から肺が作られていった。
このように環境の変化や生息条件の変化によって生物は最初の身体の構造にどんどん変更を加えてその機能まですっかり変えてゆくことができた。つまりまったくはじめから新しい設計によるのではなく、最初の形の手直しや転用、縮小によって新たな形を産みだしていったのだ。
ということは今日のどんな生物でももとを辿っていくとどこかでそのプロトタイプになったものに突き当たるというわけだ。このようにして生物の多様性は中には失敗作も無数に生み出しながらもその枠を広げていったのである。
しかし何といっても人間が二足歩行をすることほど劇的な事件はあるまい。東アフリカでの気候の乾燥化がきっかけだと言うが、その状況に適応したのはよかったにしても、様々な問題を引き起こしてしまった。それまでの水平の姿勢から90度の転換を経たわけだから、下にさがる内蔵、垂直に流れる血液、頭の荷重、など同時に解決しなければならない問題が数多くあった。
特に女性の生理に関する考察は面白い。昔の女性は絶えず子供を産み続けなければいけなかった。結婚して連続して産んで7人から10人ぐらい。そうしないと高い死亡率に追いつかなかったのだ。だから、妊娠出産授乳の繰り返しだったのだ。当然の事ながら結婚したら生理が訪れるヒマがない。
現代女性は、一生の間に産む子供の数が一人か二人に激減した。昔のペースが変わらない子宮はその間、開店休業の状態なのだ。でもいつ再び大量に子供を産まなければいけない事態が来るかわからないからその備えをしているのだ。
両手で道具を使うことによって爆発的に増えた脳の量は、現代文明をも産みだした。だがその足取りがあまりに急激で、それまでの生活形態を破壊するほどのものだ。オフィスワークやほとんど動かない生活が定着した。椎間板ヘルニア、腰痛や肩こりなどのさまざまな悩みはこれまでの人間の生理的パターンを無視している現れである。
そしてこの地球を後戻りできないほどに環境破壊を進めてしまった。完全な行き詰まりである。「50キロの身体に1400CCの脳をつなげてしまった哀しいモンスター」になってしまった。これは明らかに人類が進化上の失敗作であることを物語っている。したがって近い将来に滅びるしかないのである。これまで地球上で無数の生物が絶滅の歴史を繰り返したように・・・
翔ぶが如く(2) * 司馬遼太郎 * 文春文庫 * 2006/07/28
 三条実朝が、西郷に対して朝鮮に派遣することを安請け合いしてしまった。このため征韓論に反対の政治家たちは、大久保も含めなんとかこれを止めさせようと躍起になる。
三条実朝が、西郷に対して朝鮮に派遣することを安請け合いしてしまった。このため征韓論に反対の政治家たちは、大久保も含めなんとかこれを止めさせようと躍起になる。
その中にまだ若い伊藤博文がいた。当時はまだ小僧の扱いだったが、多くの政治家の間を駆け回り、根回しをして西郷という大物の行動を阻止しようと試みた。そのやりかたは将来の手腕を予測させる如く巧みなものだった。
海外に留学した政治家たちは、ヨーロッパ列強の力を思い知らされ、へたに日本が朝鮮に攻めていったりすると、たちまちのうちにつけ込まれて彼らのいうなりになってしまうことを恐れていた。日本も中国などと同じように植民地化されてしまうのではないかと。
だが、西郷のほうは朝鮮を攻めるという考えではなく、革命(維新)の輸出をしたいと考えていた。朝鮮の政治家たちをめざめさせ、国家をきちんと確立して中国、朝鮮、日本の3カ国が一致団結して、西欧の侵略をくい止めたいという願いから来ていた。そのために自分が殺されてもかまわないとも思っていた。
西郷に対して真っ正面から反対する政治家がいないため、政治家たちは動揺する。会議に西郷が現れたら誰も反論できないだろう。そのため自分たちの思うように会議を進めるための手だては、西郷に会議の欠席を求めることだった。
 西郷は征韓論が政府の最高会議で正式に認められることを願うが、結局の所、反征韓論を唱える大久保利通を中心とし、若き伊藤博文らの暗躍でつぶされた。政治的に敗北した西郷はその気になれば自分が掌握している近衛兵や不平士族をまとめて一気に明治政府を倒すことはできただろうが、そうはしなかった。
西郷は征韓論が政府の最高会議で正式に認められることを願うが、結局の所、反征韓論を唱える大久保利通を中心とし、若き伊藤博文らの暗躍でつぶされた。政治的に敗北した西郷はその気になれば自分が掌握している近衛兵や不平士族をまとめて一気に明治政府を倒すことはできただろうが、そうはしなかった。
そのかわり政治上の職の辞表を残すと東京の政界から姿を消してしまった。向島に猟に行っている間に弟や親しい友人が訪ねてきたが、殆ど言葉を交わすことなく去り、一方で政府にいた大勢の薩摩人がその官職を棄てて故郷に戻ってしまった。
明治政府はその有力な政府の役人を失い、全国的に不安定な状態は、この生まれてまもない政府を風前の灯火とした。だが、一方では国の仕事に残る薩摩人もいた。川路もその一人である。枯葉警視庁をどんどん発展させ、大久保の管理下にある内務省に属し、治安を日々確実なものにしていった。
ある日、それまで征韓論の争いを避け、それでもたくみに権力の座を確実なものにしていった山県有朋が襲われ傷を受ける。だがこれはむしろいっそう警察による捜査や管理の緊密化を増した。
一方、旧旗本の娘、千絵は、自分の荒れ果てた屋敷を海老原という反政府活動を志す男に貸す。屋敷はそのうち日本中の明治政府に不満や恨みを持つものが始終出入りするようになった。西南戦争で戦死する、宮崎八郎もその一人であった。彼の兄弟たちと同じく、理想家肌で大きなスケールでものを考えるこの男は、何と警視総監である川路の所に、これ以上スパイ行為をしないと談判にまでゆく。
翔ぶが如く(4) * 司馬遼太郎 * 文春文庫 2006/08/20
 東京での仕事や地位をすべて棄てた西郷は故郷に戻り、姿をくらます。日本中の士族たちの不満は高まり、村田新八ら薩摩の人間はその多くが東京での仕事を辞めて故郷に戻った。中には熊本出身の宮崎五郎のように、薩摩以外の人間でも西郷に希望を託す人間が多くいた。
東京での仕事や地位をすべて棄てた西郷は故郷に戻り、姿をくらます。日本中の士族たちの不満は高まり、村田新八ら薩摩の人間はその多くが東京での仕事を辞めて故郷に戻った。中には熊本出身の宮崎五郎のように、薩摩以外の人間でも西郷に希望を託す人間が多くいた。
そのうちに佐賀の乱が起こる。だが、この動きはあまりに性急すぎた。戦いはすぐに政府軍に鎮圧され、江藤新平は西郷に助けを求められたが、断られ、捕まって死刑となった。大久保の命によるこの死刑執行はこれから起きるであろう数多くの反乱の見せしめにするつもりであったらしい。
薩摩は、まるで独立国のようになり、帰京した若者たちがヒマを持て余すことがないようにきちんと統制のとれた組織の必要があると、西郷の取り巻きたちは考えた。これが「私学校」の誕生である。すでにある鹿児島県の行政組織にとってはこれは独裁政党のようなものであった。
本部や分校が造られ、独自の教育や訓練が施されるようになった。中央政府のようにひたすら欧化政策や工業化を追うのではなく、農本主義のような方向で薩摩の内部が変わっていった。
その頃、複雑な国際情勢の中で琉球人が台湾の土着民に殺される事件が起こり、軽率にも大久保らはこれを不平士族の不満を解消するチャンスと考え、軍艦に兵士を乗せて西郷の弟が率い討伐に向かった。だが、結果はマラリアによる病死者の続出と、国際関係、特に清との関係の緊張を招いただけだった。
この派兵は、水や食料の調達にしても、兵を乗せる艦船についても実にいい加減で中途半端であった。きちんとした議論を経ず、勝手に軍隊を動かしたというこの前例は、不幸なことにはるか太平洋戦争に至るまで日本の軍部の常套手段になった。
アメリカの原理主義 * 河野博子 * 集英社新書 * 2006/08/21
 建国以来、アメリカという国は、キリスト教を中心にしてライフスタイルを定める流れと、世俗的な自己に責任を置く流れとに分かれて存在してきた。だが、1960年代における、世界中に広がった文化革命により価値の崩壊が起こり、それに伴う社会の変化に対するバックラッシュが1980年代頃から盛んになってきた。
建国以来、アメリカという国は、キリスト教を中心にしてライフスタイルを定める流れと、世俗的な自己に責任を置く流れとに分かれて存在してきた。だが、1960年代における、世界中に広がった文化革命により価値の崩壊が起こり、それに伴う社会の変化に対するバックラッシュが1980年代頃から盛んになってきた。
つまり、60年代における左傾から、右傾化への転換である。そしてあの9.11事件はその方向を決定的なものにした。それまでは(リベラルなニューヨークではなく)アメリカの田舎で根を張っていた右翼的な保守的な思潮は、この事件を転機に一気に表に出て共和党の政権と結びついた。
この間に、息子のブッシュ大統領は、さまざまな党派をバランスを取りながら自分の陣営に取り込むことが巧みなものだから、キリスト教系を味方につけて2期大統領を続けることに成功し、自らの念願である中東への影響力の行使をアフガニスタン、イラクへの侵略を開始した。
人々の考えは、ずっと前からすこしずつ右傾化していたが、福音派の牧師の宣伝が功を奏し、純潔教育、そして多様性や多文化主義を避け、親ユダヤ的な方向を持った排外的なアメリカ像を持つようになってきた。これは旧ソ連が崩壊してアメリカが軍事的に超大国になった時期と一致する。
本来「原理主義」とは宗教的教えを文字通り受け取って実践する人々のことであるが、「イスラム原理主義」に対峙させて、「キリスト教原理主義」が多くの人々の話題に上るようになったのである。その源流には、進化論を否定し、中絶や同性結婚絶対反対、過激なテロや、露骨な人種偏見を持つ人々も含まれる。
アメリカ政府の方針は、もちろん多国籍企業や大金持ちの力が従来通りまかり通ってはいるものの、この原理主義の影響が陰に陽に現れているらしい。しかしブッシュ大統領の人気が落ち目になり、イラク侵攻に対する批判が高まる中、中間選挙、そして2008年における大統領選挙に、原理主義の影響がまだ及ぶのか、それとも衰退してかつてのリベラルな流れに戻るのか、目が離せない。
翔ぶが如く(5) * 司馬遼太郎 * 文春文庫 * 2006/09/04
 大久保の命令で出兵した台湾への軍隊は、たちまち国際的な非難を浴びた。特に清では下級外交官では相手にしてもらえずに、大久保自らが北京に赴いた。大久保の常軌を逸した姿勢に清の外交官たちは根負けして、国際法上出兵を認めたばかりか、費用まで負担することになった。
大久保の命令で出兵した台湾への軍隊は、たちまち国際的な非難を浴びた。特に清では下級外交官では相手にしてもらえずに、大久保自らが北京に赴いた。大久保の常軌を逸した姿勢に清の外交官たちは根負けして、国際法上出兵を認めたばかりか、費用まで負担することになった。
だが、この専制的挙動は、日本政府の軍との関係に悪しき前例を残す結果となり、これはやがて太平洋戦争における軍部の独走へとつながってゆく。台湾への志願兵たちの多くは薩摩や肥後の出身者が多かった。これは大久保が士族の政府に対する不満を少しでも和らげようという意図だったからだ。
だが、彼らは栄養失調やマラリアに苦しみ、ようやくのことで長崎に戻ってきた。その中にはかつて東京の海老原に会いに行った宮崎八郎も含まれていた。宮崎一家は、大きく望みを持ち、金銭に卑しくならず、そして何よりも反政府的な雰囲気を持っていた。その長男である八郎は、その頃からルソーの思想を中江兆民の訳本を通じて熱中し、自由民権運動を目指すことを考えていた。
地元肥後では仲間と共に「植木学校」を創設し、いずれは政府を転覆する革命戦士を養成するつもりでいた。東京に出ている県令(知事)に会いに行くため、八郎自らも上京することになった。再会した海老原は「評論新聞」という反政府的宣伝機関の主宰者になっていた。これを見た八郎は自分も記者にしてもらう。
 21世紀のある日、宮崎県日向大学の防災工学の助教授黒木はある男に面会を求められた。それは「火山オタク」ともいえる黒木に、迫り来る火山の大爆発に備える政府の計画に参加を求めるというものだった。
21世紀のある日、宮崎県日向大学の防災工学の助教授黒木はある男に面会を求められた。それは「火山オタク」ともいえる黒木に、迫り来る火山の大爆発に備える政府の計画に参加を求めるというものだった。
「K作戦」と呼ばれた計画は秘密裡に行われ、黒木も参加して大惨禍に備える。果たして霧島山系の中に何十万年もの間埋もれていた休火山が大爆発を起こした。ちょうど新聞記者の岩切と共に霧島山中に調査に出かけていた黒木は大噴火を目のあたりにする。
火砕流が流れ出し、鹿児島市や宮崎市も含めて近隣の市町村は全滅した。高温のサージが迫る中二人は4輪駆動車で必死に逃げ回る。何度も高熱に焼き殺されそうになり、至る所で発生した土石流につぶされそうになりながら、ようやく日南線のトンネルに入り、太平洋岸に出ることができた。
その頃、黒木の妻で医師の真理は日南の病院で手術中だった。そこへサージが直撃したが、厚い壁に囲まれた手術室にいたために九死に一生を得た。再会した夫婦や岩切たちは港で待つ船に救助される。
火山灰は九州全土に降り注ぎ、全滅の瀬戸際にあったが、風は火山灰をさらに北方へと運び、西日本そして関東地方に甚大な被害を及ぼす情勢となった。総理大臣の菅原は日本国が滅びないように、黒木のアイディアも加えてさまざまな施策を考える。
暴落した円を救い、将来の再建のために備えなければならない。これまでのように軟弱な沖積平野に都市と作ることや、やたらにダムを造って地形を歪めることなく国土を保全することを考えなければならない。
いま溶岩や火山灰によってかつての国土の大部分はおおわれてしまったが、おかげで未開拓の広大な土地が手に入ったのだともいえ、播種と植林によって新しい国土を作るべきだと首相はテレビの演説で訴えるのだった。
特にすぐれた出来映えではないが、それでもついつい引き込まれ、読後の清涼感もあるのは、「こうなって欲しい・・・」という潜在意識が満足させられたからだろう。
翔ぶが如く(6) * 司馬遼太郎 * 新潮文庫 * 2006/10/11
 維新政府の政策は、年々各地の士族の不満を高めていった。佐賀の乱の後、政府は着々と国家建設を続けていたのだが、各地にもししっかりした指導者がいればたちまち爆発しかねない勢いであった。
維新政府の政策は、年々各地の士族の不満を高めていった。佐賀の乱の後、政府は着々と国家建設を続けていたのだが、各地にもししっかりした指導者がいればたちまち爆発しかねない勢いであった。
旧薩摩藩の藩主だった島津久光もその一人で、その超保守的な政見は次々と欧化政策を進める維新政府に対して日々怒りを高めてゆき、かつては裏切り者として退けていた西郷にさえ、接近するほどだった(逃げられてしまうが)。政府は久光を鹿児島に置くことの危険を感じて高い位を与えてなんとか東京に引き留めようとしたが、結局は勝手にくにに帰ってしまった。
政府の要人が次々と輩出した長州にも、反政府的考えを持つ人々は多くいた。前原一誠はその首領格で、政府の引き留めにも関わらず東京での官職を捨てて故郷に戻ってきてしまった。しかも密偵に自分の政府転覆計画を軽率にも話してしまったためにのっぴきならない立場に追い込まれる。
肥後でも士族の不満は高まっていたが、となりの薩摩と同盟しようというグループもあり、まったく独自の路線をゆく宗教団体もあった。旧体制に戻して欧化政策を厳しく排撃する神風連もその一つである。彼らは前原にも行動を共にするよう呼びかけ、着々と準備を進めていた。
薩摩に使者を送りはしたが西郷に合うことはできず、結局自分たちで独自の反乱を起こすことになった。すぐにつぶされたものの、熊本城下で兵士や政治家の殺戮を行い、そのニュースは日本全国にショックを与えた。
三十三年之夢 * 宮崎滔(とう)天 * 岩波文庫 * 2006/10/27
明治初期、熊本県の田舎で11人兄弟姉妹の末に生まれた滔天は、「大物になれ、金銭に執着するな」と教える父親と、それに同調する母親のもとに育った。兄たちの影響もあって、反政府、反官吏、そして自由民権への憧れを持って大きくなった。
「金銭に手を触るるごとに、『えた、非人の所為なり』」「畳の上に死するは男子なによりの恥辱なり」「官軍や官員やすべて官のつく人間は泥棒悪人の類にして、賊軍とか謀反とかいうことは大将豪傑のなすべきことと心得いたり」という家風の中に育ったのである。
はじめ自由な雰囲気の塾に入って様々な考えを吸収するが、師も仲間達も実は功名心、名誉心が原動力であることを知って退塾する。後のキリスト教の宣教師として知り合い、洗礼まで受けてその教えに入り込むが、次第にその限界を知り、もっと大きな流れを求めて上京する。
東京では専門学校に通う傍らさまざまな人々と知り合い、世界を変えるには、まず中国に乗り込んで活動を開始しなければならないと考える。だが、いったん郷里に戻り長崎から中国に向かったものの、友人は借りた金を返してくれず、いったんは挫折して戻ることになる。さらに病を得た。
風変わりな外国人のおかげで若い女性と知り合い、恋に落ちてしまった。このため結婚をするが若くして所帯を持つことは今後の活動の差し障りになることは十分わかってのことである。
ある友人の情報から、タイに行く事を勧められる。だが、移民責任者が病気となり、彼自身が引率することになった。当地ではこの国を建設するために日本人の人的援助を期待しており、一度広島の移民担当の会社に引き返してしっかりした計画を立てるように説得することにした。
二度目のタイ行きは困難を極めた。コレラが蔓延し、彼自身も感染して危うく死ぬところだった。再び日本に帰り、何人かの中国人と知り合う。その中には孫文やその同志がおり、間に立って連絡役を務めた。再び組織の強化を目指してシンガポールに渡るが仲間の一人を暗殺しようとしているのではないかという疑いをかけられ監獄に入れられてしまう。
わずか一週間ほどで疑いは晴れるが、孫文やその仲間と共に日本行きの船に乗せられて強制送還されることになった。この間にフィリピン革命のための武器を積んだ船は沈み、日本人仲間の一人が横領をして、多くの軍資金が失われてしまう。
中国では孫文の一派が恵州事件を起こしたが、これも先の横領事件のために資金が不足して成功とはならなかった。滔天は、これまでの33年間を振り返って、ずいぶんいろいろな活動をして、親や家族に迷惑をかけ、友人や支持者にも大変な思いをさせながら結局はみんな失敗だったと反省する。
自分の生き様を少しも隠すことがない。酒と女に取り囲まれて日を送ったことも、少しも悪びれず描いているし、その食欲のすごさに、自分を「製糞機」とよんでいるくらいだ。それでも多くの人間とのつきあいの中から実りのある成果を生みだしてきたのだ。
人生は夢なのだ、そして突如活動を止め、この本を書いたあとでは日本から出ることはなく何と浪花節語りとなる。私利私欲に惑わされず、功名心もなく、日本ではなく中国に革命を起こすことを夢見た日本人がここにいたのだ。
Guns, Germs, and Steel (邦名;「銃、病原菌、鉄」草思社)/ Jared Diamond / Vintage / 2006/11/27
 現代文明は世界の先進国に偏り、一方では最近まで石器時代に近い暮らしをしている人々が地球の各地に住んでいる。なぜこのように人類の暮らしには格差が開いてしまったのか?ある人はそれが各民族の先天的、遺伝的な違いによるものだと主張するが、著者はこれがそれぞれの地域の自然環境の違いによって生じたのだということを実証しようとする。
現代文明は世界の先進国に偏り、一方では最近まで石器時代に近い暮らしをしている人々が地球の各地に住んでいる。なぜこのように人類の暮らしには格差が開いてしまったのか?ある人はそれが各民族の先天的、遺伝的な違いによるものだと主張するが、著者はこれがそれぞれの地域の自然環境の違いによって生じたのだということを実証しようとする。
これまでの人類の歴史はヨーロッパ中心の見方であった。これを改めて南北アメリカ、ニューギニア、オーストラリアなどの古代の人類の暮らしや移住の状況に焦点をあてて考察する。
まず問題となるのは、植物の栽培と動物の家畜化の歴史である。古代を振り返ると、地中海の東、今のシリア、イラク、ヨルダンあたりの地域が、気候といい、植物や動物の利用のしやすさといい、あらゆる点で恵まれていた。これに対しニューギニアあたりでは家畜に向く動物もおらず、タンパク質不足に苦しんだ。
このように出発点からしてそれぞれの環境の与える恩恵の度合いが著しく異なっていたのだ。農耕と牧畜がさかんになれば、当然人々の暮らしにゆとりが生まれて都市化を促進し、職人や軍人といった食糧生産以外の仕事をする人々を養うことができるようになる。これが文明の始まりであった。
このように、文明の発達は、栽培植物と家畜のセットが完備して初めて実現するのである。ところが世界中を見回してみるとそのように恵まれた地域は意外に少ないことがわかる。アフリカやアメリカ大陸は南北に長く、緯度の違いにより、植物の栽培がスムーズにいかない。一方ユーラシア大陸は東西に長いために同じ緯度ででの伝播が可能であった。
話の中にさまざまなエピソードが登場する。タイプライター、そして現在のパソコンのキーの配列は、実につまらない原因で定められたものだった。ニューギニアのある地域では土着人の知的好奇心が乏しくて、文明世界からの珍しいものを目にしてもすぐに関心を失い農作業に戻ってしまう。ほんの一握りのスペイン人が、南アメリカの大帝国を制圧してしまった。
特に目を引くのは、植民地では銃で殺されたよりもはるかに多数の原住民がヨーロッパ人たちのもたらした病原菌で倒れたということであろう。それらは記録に残らず、また特定の個人や集団の責任にすることもできない。
上記の自然環境に恵まれたかった地域は大いに遅れをとり、タイトルの3つの「武器」がまたたく間に世界を制覇してしまったのだ。かくして現在でもその「格差」が世界中に残ってしまったのである。歴史学は実験室での実証はできないけれども、比較研究を行うことによって、実に興味深い成果が得られるものだ。
翔ぶが如く(7) * 司馬遼太郎 * 文春文庫 * 2006/12/12
 神風連の乱の後、長州や九州の秋月で次々と小規模な旧師族の乱が起こったが、すぐにつぶされた。これはひとつには彼らの行動があまりに計画性に事欠き、自分たちが立ち上がれば、まわりの者たちもそれに呼応して乱が広がると単純に考えていたためであった。
神風連の乱の後、長州や九州の秋月で次々と小規模な旧師族の乱が起こったが、すぐにつぶされた。これはひとつには彼らの行動があまりに計画性に事欠き、自分たちが立ち上がれば、まわりの者たちもそれに呼応して乱が広がると単純に考えていたためであった。
そのころ薩南では相変わらず西郷はひとりで猟に没頭しており、各地からの乱の知らせで行動を起こす気配はなかった。ところが私学校の血気にはやる若い連中はじっとしていることができず、その狂気と情熱は日に日に高まるばかりだった。
一方、東京では鹿児島県だけがひとりまるで独立国のように振舞っていることに、何とかしなければならないと大久保を中心に対策を考えていた。そこで思いついたのが忠実な部下であり警視総監である川路が薩摩出身の警官を郷里に戻させ、密偵の役割を果たしてもらうことだった。
だが、彼らが鹿児島県にはいると、簡単に見破られさらに悪いことには西郷の暗殺を最終目的にしていることが明らかになり、これを聞いた若者たちは激昂してまさに手がつけられないほどに県内での圧力が高まってしまった。
一部の者たちが弾薬を盗んだりしたことから、これは東京からの挑発に乗ってしまったと考えていいだろうが、ついに西郷が山から降りて来て彼らの怒涛の中に身をゆだねると宣言する。しかし東京へ進軍するという漠然とした考えがあるだけで具体的な作戦が立っていたわけではない。
海軍の軍艦が東京からの使者として錦江湾に入ってきたが、話し合いは不調に終わり、出陣がいよいよ迫ったことを感じた西郷は二人のイギリス人に会って自分の立場を明らかにする。
サバイバル登山家 * 服部文祥 * みすず書房 * 2006/12/15
 この出版社がみすず書房であることに注目していただきたい。「山と渓谷社」ではないのだ。これは単に技術論ではなく、何か文明論的なインパクトを秘めた本ではないかと思ってしまうではないか。実はこの出版社は多くの山岳関係の本を出しているのだ。それはひとつに登山は技術だけでなく、現代文明に対する一つの思想を含んでいるからだろう。
この出版社がみすず書房であることに注目していただきたい。「山と渓谷社」ではないのだ。これは単に技術論ではなく、何か文明論的なインパクトを秘めた本ではないかと思ってしまうではないか。実はこの出版社は多くの山岳関係の本を出しているのだ。それはひとつに登山は技術だけでなく、現代文明に対する一つの思想を含んでいるからだろう。
まだ年若い著者は、技術としての登山全般に飽きたらず、病める現代文明への一つの提案として自分の行動を表現として用いている。それは単なる消費者となり金と交換するだけになってしまった安楽な生き方に対して、自分を自然界に曝して生きる意味と生きる強さと経験を引き出す試みだ。
彼にとって大切なのはその行動が「フェアー」なのかどうかということだ。道具に頼る、その他人間の発明した便利なものに頼るということは、自然に対してフェアーに立ち向かっていることにはならないという。まさにこれに私は同感だ。強力なSUVに乗り、砂浜を走り回って鳥の卵を平気でつぶす連中の醜さがいい例だ。
500メートルはなれたコンビニに車で行く恥知らずは言うに及ばず、装備を競い、その性能を競う風潮は目にあまる。すべては自分の肉体が勝負だ。ヨットやウィンドサーフィンのワンデザイン・クラスは、このような発想から生まれたのである。登山界にもこのような考えをする人がいるのは実に喜ばしいことだ。
著者はアメリカがはじめたグローバリズムにも反感を持っているようだ。仲間が持ってきた行動食、スニッカーズ(肥満者の友!?)のことを「口の中にアングロサクソンの好みそうな恥知らずな甘味が広がっていった」などとおもしろく描写されている。
そのためには登山のあらゆる技術を試みたし、つり、山菜取り、狩猟と自然の中で生きるための方法について飽くなき探求を続ける。そして得た力を試すため、知床半島や、日高山塊に挑み、近代的な装備をできるだけ減らして何日間も山にこもって自らの力を試すのである。機械力や技術力に頼るのでなく、なるべく素っ裸な肉体で「フェア」に自然の中で振舞いたいというのだ。
彼の考えには大賛成だし、自分でものを考える人だということはよくわかる。ただしこの本を読んで日本中の若者がそのまねをしては困る。そんなことをしたら、奥山のヤマメや山菜はあっという間になくなってしまうだろうから。ただし、ガマカエルの内臓を取り出してその残りを食べてしまえる人はあまりいないだろうから、その心配は杞憂に終わるだろうが。
それに、このライフ・スタイルは決して新しいものではない。終戦直後の食糧難時代において山から本当の意味で生存を引き出した人は当時は大変な数に上っただろうし、その多くはどこで何を見つけたらいいかちゃんと知っていたのである。それ以前の人々では山に出入りする人は言うにおよばず、山村に暮らす人の常識であった。だがいつのまにか人々は快適生活に惹かれ、山や海を汚染し、かつてのたくましさや力強さを失い、何でもかんでも依存することを覚えて甘やかされてしまった。
この本を読んで物悲しく思うのは、いかに現代日本人のほとんどが「家畜化」されているかということだろう。その意味でこれが警告の書であるということはいくら強調してもし過ぎることはなかろう。真夏にエアコンをガンガンかけた部屋から一歩も出られず、100メートル離れたコンビニに自家用車を運転していく人が多数を占める世の中なのだから。
それにしても日高山脈や、黒部渓谷での冒険はほとんど死と隣り合わせだ。ふとダーク・ダックスの「山男の歌」を思い出してしまった。<娘さんよく聞けよ、山男にゃ惚れるなよ・・・若後家さんだよ・・・>の部分だ。さらにフォークの名曲、「小さな日記」も思い出してしまった。
「やめる」から始める人生経済学 * 森永卓郎 * アスペクト * 2006/12/18
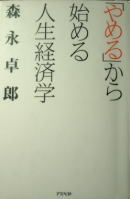 この本は体制の中で個人がどのように生きたらいいかという点でアドバイスをしている。この社会体制全体を葬れと主張する人ではない。だからその主張もおのずと限界がある。ただ多くの無気力な日本人はこういうことでも実行に移すのは無理ではないかと思ってしまう。
この本は体制の中で個人がどのように生きたらいいかという点でアドバイスをしている。この社会体制全体を葬れと主張する人ではない。だからその主張もおのずと限界がある。ただ多くの無気力な日本人はこういうことでも実行に移すのは無理ではないかと思ってしまう。
バブルがはじけそれが回復してきたときに小泉が首相になった。彼のやり方はまるでアメリカ流であり、「改革」とは人々の間に賃金格差をつけて競争を激化させ、その勢いで企業をグローバリズムの中で勝ち抜かせようという政策である。国民はもともとお人よしだけにまんまとそのやり方に乗せられ、現在のようなカネ万能の世の中ができあがった。
現代の日本の特徴は2極化である。そして低いほうにおかれている人々は自分たちの行き方をきちんとおさえていないから金持ちにやたらあこがれたり、絶望したりしている。仕事もそのおもしろさではなく、金額で計られるものだから実につまらなくなる。
著者は人々が流されることなく自分なりの生き方を追求することを勧める。欧米諸国の大部分のサラリーマンがそうやっているように、ハタラキバチはごめんだと見切りをつけ、給料は生活保障とみなしグローバル・スタンダードでは300万で十分であり、出世なし、定刻までの働きであとは自分なりの行き方を追及せよということだ。高賃金と地位を目指して働きすぎでボロボロになるのはエリートに任せておけばよい。
日本のように大企業が全体を牛耳り、中小企業がその下請けや系列に甘んじている国ではその未来は明るくない。イタリアのように、中小企業が元気で独創的な活躍ができる国では景気が悪くなっても自分たちの持つエネルギーで立ち直れる。
個人的にはこれまでの狭いサラリーマン世界から脱し、それ以外の分野の人々と多く知り合い、見識を広げるべきだ。専業主婦、子供、マイホームは三大不良債権だという。若い人はこの三つによって自分の人生が奴隷状態にならないように気をつけて生きよう、と著者は言っている。
2007年
翔ぶが如く(8) * 司馬遼太郎 * 文春文庫 * 2007/01/05
 薩摩領内での、私学校の若者たちの熱狂はもう押さえがきかなくなり、西郷もついに彼らの運命に身を任せることになった。ただ西郷自身に明確な政治的な理念やプランがあったわけではないし、今後の作戦は、幹部たちに任せきりだった。
薩摩領内での、私学校の若者たちの熱狂はもう押さえがきかなくなり、西郷もついに彼らの運命に身を任せることになった。ただ西郷自身に明確な政治的な理念やプランがあったわけではないし、今後の作戦は、幹部たちに任せきりだった。
そのころ東京では、独立国のような振る舞いに神経をとがらす警視庁の川路総監が、薩摩人警察官を故郷に帰らせるという名目でスパイを送り込んだが、たちまち彼らはつかまり、取調べによって西郷殺害を企てていたらしいことが明らかになり、これは一気に薩摩の反政府姿勢を強めてしまった。
これが政府の明らかな挑発だったかははっきりしないものの、これにて双方とも臨戦態勢に入り、西郷とその軍隊は、東京の政府と直接談判するという名目で北進を開始した。
隣の熊本県では城を包囲したが、政府軍は篭城を決め込んだ。薩摩の軍隊はその先北九州や中国地方への転進をしっかりと決めておかなかったために、多くの兵隊を熊本市内に残し、北からの政府軍、まずは乃木の率いる連隊と戦うことになった。
強さで知られた薩摩の兵隊は、最初のうちこそおびえる政府軍を蹴散らしていたが、やがて熊本市周辺での「高瀬の会戦」あたりからしだいに押され気味となる。しかし一方では政府のやり方に腹を立てている地元の農民たちの薩摩軍への期待は高く、民権政治の真似事をするところすら現れた。
沢彦(たくげん) * 火坂雅志 * 小学館 * 2007/01/23
 織田信長の一生を、彼の家庭教師であり顧問であった沢彦から見た小説となっている。沢彦は各地の戦国大名の顧問を多く輩出していることで知られた妙心寺の出身である。禅宗の流れを受け、その生活は座禅をして公案を考え、日常そのものが修行である。彼は信長に自分の天下統一の理想を実現させようとした。だが、成功の頂点に達したとき、弟子である信長は師の言葉を無視し、暴走を始め、誰にも手のつけようがなくなってしまったのである。
織田信長の一生を、彼の家庭教師であり顧問であった沢彦から見た小説となっている。沢彦は各地の戦国大名の顧問を多く輩出していることで知られた妙心寺の出身である。禅宗の流れを受け、その生活は座禅をして公案を考え、日常そのものが修行である。彼は信長に自分の天下統一の理想を実現させようとした。だが、成功の頂点に達したとき、弟子である信長は師の言葉を無視し、暴走を始め、誰にも手のつけようがなくなってしまったのである。
これまで見聞きした信長の一生を扱った小説や映画は極めて多いが、そのほとんどは今までに見る限りその扱いは「英雄」であった。英雄とは、その勇ましくプラスの面だけが強調され、読者や観客はそこに多大な魅力を感じる。だが、明治時代以降、国家権力を強化しようとあらゆる努力をおしまなかった人々は、信長を戦乱の後の国家統一の象徴と見たのは当然だろう。
この小説を読むと、この男の残虐性、狂気が表面にはっきり現れてくる。最後に明智光秀がどうして暗殺をするようになったかのいきさつがごく自然に飲み込める。実際のところ400年も前の歴史に関して十分な資料が残されてはいないのだから、多くの点でこれからもさまざまな見方がでてくるであろうが、これだけは確かだ。ヒットラーも、ナポレオンも、スターリンも、レーニンも、アレクサンダーも、ジンギス・ハンも人間本性に基づく無差別虐殺なしには彼らの「偉業」は成し遂げられなかったということだろう。
歴史というものは、じつに簡単にゆがんでしまうものだ。まず信長死後に政権を確立した秀吉によるゆがみ。彼にしてみれば自分の政権の正当性を主張するために、どんな創作も証拠隠滅も行ったことであろう。その後の時代には小説家の「想像力」がゆがみに大いに貢献した。そして明治、大正、昭和には中央集権国家の強化と結びついたのである。
そしてさらに今日では、「経済効果」「組織への忠誠」が重視されている。「楽市・楽座=自由市場」といった図式のように、自由競争やら実力主義というのが、信長にすばらしい手本を見つけられるかのような風潮だ。こうやってみるといかに「本当の」歴史像を見つけるのが難しいのかがわかる。
翔ぶが如く(9) * 司馬遼太郎 * 文春文庫 * 2007/02/5
 戦局は、次第に薩摩軍が押され気味になってきた。熊本の田原坂の攻防での後、政府軍はじりじりと南下を続け、その一方で薩摩軍は撤退を続けることになった。弾薬は不足し、死傷者が増える一方で、鹿児島県でもっと多くの兵士を募集する必要に迫られた。
戦局は、次第に薩摩軍が押され気味になってきた。熊本の田原坂の攻防での後、政府軍はじりじりと南下を続け、その一方で薩摩軍は撤退を続けることになった。弾薬は不足し、死傷者が増える一方で、鹿児島県でもっと多くの兵士を募集する必要に迫られた。
政府側は、鎮台兵のみならず、警官までも投入して兵隊代わりに使おうとした。激闘の繰り返しにより、ついに熊本城は明渡され、薩摩軍は熊本県から外に出ることになった。しかし薩摩兵の強さと豪胆さは相変わらずで、山県をはじめとして政府は物量作戦しか方法がないと考えた。
西郷は政局の悪化と共に、敵を避けて移動していった。人吉から日向へと移ったのは、宮崎県が政府のまだ力の及ぼしていないところであり薩摩への支援を申し出る住民も多く、薩摩の指揮者の中には、大分から小倉へと進出する方策を考えていたものもいたからである。
翔ぶが如く(10) * 司馬遼太郎 * 文春文庫 * 2007/02/10
 軍は北を目指した。しかし延岡の戦いで、いっそう薩摩軍の不利が明らかになった。延岡の近く、可愛岳まで来ると、兵員も食料弾薬も不足し、もはや状況は絶望的になってきた。多くが降伏したが、残ったものは、再び郷里の鹿児島に戻ることを志向した。
軍は北を目指した。しかし延岡の戦いで、いっそう薩摩軍の不利が明らかになった。延岡の近く、可愛岳まで来ると、兵員も食料弾薬も不足し、もはや状況は絶望的になってきた。多くが降伏したが、残ったものは、再び郷里の鹿児島に戻ることを志向した。
政府軍の意表をついて、西郷を連れた薩摩の残党は一路南を目指し、鹿児島市の中にある城山に立てこもる。だが人数もわずか数百人となった薩摩軍は、最後の政府軍による総攻撃で、西郷を初めとした幹部は、闘死や切腹、降伏のいずれかを選びここに西南戦争は終結した。
********
西南戦争は、中央集権国家を目指そうとした中央政府に対する一種の独立運動である。私学校の幹部たちの間に優れた戦略がなかったために敗れてしまったが、東京の政府に対抗して自らが独立した国家を作ろうとした(最後の)試みであった。
西郷は明治維新の際に自分の政治目標を達成し、以後は帰農してのんびり暮らそうと考えていたらしいが、征韓論が拒否されて故郷に帰ってしまったときから熱烈な私学校生徒に持ち上げられ、この戦争の目的・理念とされてしまった。本当は西郷は戦争をやる気ではなかったのかもしれない。戦争は部下の桐野が中心になってやった(そしてそのやり方はまずかった)。
西南戦争以後、中央集権体制は強固なものとなり、日本の地方は完全に東京政府によって掌握された。政府のカネによって、灌漑や鉱山など、どんどん地方に施設を作ったのだ。今でも公共事業の甘いえさによって地方は完全に独立性を失い中央に全面的に依存する体制に組み込まれている。これは暴力団によって覚せい剤を与えられ従属しきっている子分みたいなものだという人もいる。
魔王・呼吸 * 伊坂幸太郎 * 講談社 * 2007/02/18
 主人公安藤は、東京に暮らすサラリーマンだが、いつも人の考えに流されず、自分でものを考えようと努力している。最近、犬飼という野党党首がその歯に着せぬものの言い方で人々の注目を浴びている。その言い方は率直で簡潔で人々の気持ちをとらえているのだが、安藤はそれが何か不安でならない。彼の大学時代の友人や行きつけのバーの主人は犬飼に惹かれているようだ。
主人公安藤は、東京に暮らすサラリーマンだが、いつも人の考えに流されず、自分でものを考えようと努力している。最近、犬飼という野党党首がその歯に着せぬものの言い方で人々の注目を浴びている。その言い方は率直で簡潔で人々の気持ちをとらえているのだが、安藤はそれが何か不安でならない。彼の大学時代の友人や行きつけのバーの主人は犬飼に惹かれているようだ。
一方同居している弟やその恋人、そして会社の同僚にも自分の気持ちを打ち明ける。安藤はある日自分が特異な腹話術の能力を持っていることを発見した。自分の思ったことを今見つめている相手にしゃべらせることができるのだ。犬飼の主張は、アメリカ人の家に放火したり暴動にまで発展する。ある日犬飼の演説会に出かけた安藤は、この危険人物に対して彼の意志とは関係ないことをしゃべらせようとした。だが演説会場に近づき犬飼の姿を見るとなぜか意識が朦朧となり・・・
続編「呼吸」では、弟の恋人が主人公になる。というのも」安藤は犬飼の演説会場で脳溢血により急死したからだ。それから5年。二人は結婚し、仙台に暮らす。弟にはなぜか兄の声がかかっているような気がしてならない。競馬では次々と勝ってしまう。一方犬飼はついに首相になり、日本は憲法改正への道を進み始めた。
彼女は派遣社員としてある会社で働いているが、そこでも政治の主張に考えもせず流される人、自分でものを考えて慎重に行動しようとする人などさまざまだ。ある日彼女は自分の夫が競馬で莫大な金を貯め込んでいることを発見する。彼はそれをどんな政治目的に使おうというのか・・・
政治に対して全く無関心でいることは結局知らぬ間にムッソリーニのようなファシズムを許すことになろう。どんなに不器用でも一人一人が自分でものを考え、日常生活の些細なことに気をとられることがあっても、もっとマクロな事態の展開に目を見張らなければならないということだろう。