コメント集(6)
H O M E > 体験編 > 映画の世界 > コメント集(6)
今年見た映画(2000年)
A Passage to India インドへの道 04/02/00
 一人の英国娘(アデラ)が狂言で男から襲われそうになったと訴える。舞台はインド。イギリスに植民地支配を受けていた頃の話だ。彼女は、婚約者に会いにインドを訪れて本物のインドに接したいとあこがれるが、洞窟へ案内してくれた親切なインド人医師(アジズ)を告訴することになったのは、暑さのせいか、それとも草原に埋もれたインドの古代人によって彫られた男女交歓の姿を見たせいなのか?支配者であるイギリス人は、彼女の婚約者も含めて現地のインド人とは必要以上に決してつきあうことをしないし、現地人はイギリス人のことを自分たちを搾取する支配者として常日頃から恨みの目で見ている。だからこのような告訴事件が起これば、暴動が一発触発の事態に進展する。このストーリーで良心的な存在はアデラと同行した、未来の夫の母親(モア夫人)であろう。「何世紀もの間、肉体的抱擁をしているのに、男と女は互いになにも理解していない」「年を取ると人間は自分が神なき宇宙の影に過ぎないことに気づく」と、核心に触れる発言をするのだ。その彼女も裁判のごたごたを嫌ってイギリスへ帰る船の中で心臓発作を起こして死んでしまう。原題に
A が付いているように、インドへの道はたくさんあるが、たまたま彼女らが選んだこの道はあまり幸せな道ではなかったようだ。(1984年)
一人の英国娘(アデラ)が狂言で男から襲われそうになったと訴える。舞台はインド。イギリスに植民地支配を受けていた頃の話だ。彼女は、婚約者に会いにインドを訪れて本物のインドに接したいとあこがれるが、洞窟へ案内してくれた親切なインド人医師(アジズ)を告訴することになったのは、暑さのせいか、それとも草原に埋もれたインドの古代人によって彫られた男女交歓の姿を見たせいなのか?支配者であるイギリス人は、彼女の婚約者も含めて現地のインド人とは必要以上に決してつきあうことをしないし、現地人はイギリス人のことを自分たちを搾取する支配者として常日頃から恨みの目で見ている。だからこのような告訴事件が起これば、暴動が一発触発の事態に進展する。このストーリーで良心的な存在はアデラと同行した、未来の夫の母親(モア夫人)であろう。「何世紀もの間、肉体的抱擁をしているのに、男と女は互いになにも理解していない」「年を取ると人間は自分が神なき宇宙の影に過ぎないことに気づく」と、核心に触れる発言をするのだ。その彼女も裁判のごたごたを嫌ってイギリスへ帰る船の中で心臓発作を起こして死んでしまう。原題に
A が付いているように、インドへの道はたくさんあるが、たまたま彼女らが選んだこの道はあまり幸せな道ではなかったようだ。(1984年)
Directed by David Lean Writing credits E.M. Forster (novel) David Lean Cast : Judy Davis .... Adela Quested / Victor Banerjee .... Doctor Aziz / Peggy Ashcroft .... Mrs. Moore / James Fox (I) .... Richard Fielding ヒアリングーイギリス英語と、インド英語の二つが混じるわけだが、アメリカ英語に慣れた人には非常に聞き取りにくく、慣れが必要だろう。
Lenny レニー・ブルース 04/05/00
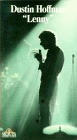 1960年代前後といえば、ビートルズをはじめとして、音楽も美術もあらゆる文化が反体制運動と共に開花して、20世紀の中の「ルネサンス」と呼べる10年間だった。 現代のように「富」だけを求める時代からは想像するべくもないが、この当時は何をやっても「熱気」みたいなのがあって、人々を大きな興奮の中に巻き込んだのだ。このストーリーの主人公レニー・ブルースもその一人だ。はじめは、さえない場末のコメディアンで司会でもあったのが、自分のきわどい「ワイセツ語」を交えながら、社会批判を即興で始めると、この時代の中で大変な人気を博したのだ。ケネディもローマ法王もベトナム戦争もこき下ろし、人々が気取って、隠していた私生活や同性愛や偽善を次々と自分のトークショウの中で暴き立て、ますます人々はそれに拍手喝采したのだ。だが、同時代のマリリン・モンローやロックミュージシャンたちと同じく、その命は短かった。麻薬にとりつかれ、ワイセツな発言のため、当時の頭の固い裁判所から何回も有罪を宣告され、結核にもかかって、最後は自殺とも他殺ともわからない死を遂げた、壮絶な人生の一つであった。「卒業」のダスティン・ホフマンが演じ(若い!)、ストリッパーだった妻やエージェントからインタビュー回想する形式になっていて、「市民ケーン」と構成がよく似ている。しかもわざとカラーでなく、白黒にしてある。また、この時代の雰囲気が、何とマイルス・デイビスの演奏を中心に表現されている。最後に流れる曲は
It Never Entered My Mind で象徴的だ。(1974年)
1960年代前後といえば、ビートルズをはじめとして、音楽も美術もあらゆる文化が反体制運動と共に開花して、20世紀の中の「ルネサンス」と呼べる10年間だった。 現代のように「富」だけを求める時代からは想像するべくもないが、この当時は何をやっても「熱気」みたいなのがあって、人々を大きな興奮の中に巻き込んだのだ。このストーリーの主人公レニー・ブルースもその一人だ。はじめは、さえない場末のコメディアンで司会でもあったのが、自分のきわどい「ワイセツ語」を交えながら、社会批判を即興で始めると、この時代の中で大変な人気を博したのだ。ケネディもローマ法王もベトナム戦争もこき下ろし、人々が気取って、隠していた私生活や同性愛や偽善を次々と自分のトークショウの中で暴き立て、ますます人々はそれに拍手喝采したのだ。だが、同時代のマリリン・モンローやロックミュージシャンたちと同じく、その命は短かった。麻薬にとりつかれ、ワイセツな発言のため、当時の頭の固い裁判所から何回も有罪を宣告され、結核にもかかって、最後は自殺とも他殺ともわからない死を遂げた、壮絶な人生の一つであった。「卒業」のダスティン・ホフマンが演じ(若い!)、ストリッパーだった妻やエージェントからインタビュー回想する形式になっていて、「市民ケーン」と構成がよく似ている。しかもわざとカラーでなく、白黒にしてある。また、この時代の雰囲気が、何とマイルス・デイビスの演奏を中心に表現されている。最後に流れる曲は
It Never Entered My Mind で象徴的だ。(1974年)
Directed by Bob Fosse Writing credits Julian Barry (I) (also play) Cast : Dustin Hoffman .... Lenny Bruce / Valerie Perrine .... Honey Bruce / Jan Miner .... Sally Marr / Stanley Beck .... Artie Silver / Frankie Man (I) .... Baltimore Strip Club MC ヒアリングーインタビューでの会話はかしこまっているから聞き取りやすい。ストリップ小屋での会話などちょっと苦しむ表現が多いが、何と言ってもここではワイセツ語に通暁する必要があろう。
Dog Day Afternoon 狼たちの午後 04/08/00
 1972年に本当に起こった事件の映画化。銀行強盗を試みるが、警官に包囲されて、行員を人質に立てこもる、といえばよくあるパターンだが、時代は60年代、この事件にさまざまな背景がかかわってくるのだ。その取り込み方がすごい。ATTICA
といえば当時、劣悪な環境の刑務所で囚人たちの大暴動が起こり、大勢が殺された事件だ。これで司法、警察当局への国民の不信が一気に高まった。人質事件の首謀者(アルパチノ)が一言「ATTICA」と叫ぶと、ヤジウマたちが彼の味方になってしまう。また、マスコミの偽善も露わにされる。彼と相棒は二人ともベトナム戦争帰還兵である。目的のはっきりしない戦争と意味のない殺戮を経験した彼らの多くは、国に戻ってからも人殺しを何とも思わなくなっていた。人質にされた店長と女子行員たちは比較的冷静である。むしろ犯人たちとの「うち解けた」会話から、彼女らの低い賃金や犯人の私生活が明らかになってゆく。主人公の犯人はバイセクシュアルなのだ。女房子供もいながら、深く愛する男性を「妻」にもしている。このことをテレビの報道で知ったゲイたちが、現場に駆けつけて自分たちの権利を主張して気勢を上げる。最後に破れかぶれになった犯人たちはバスを用意させ、空港には自分たちが世界地図のどこにあるかも知らないアルジェリア行きのジェット機を要求するが・・・(1975年)
1972年に本当に起こった事件の映画化。銀行強盗を試みるが、警官に包囲されて、行員を人質に立てこもる、といえばよくあるパターンだが、時代は60年代、この事件にさまざまな背景がかかわってくるのだ。その取り込み方がすごい。ATTICA
といえば当時、劣悪な環境の刑務所で囚人たちの大暴動が起こり、大勢が殺された事件だ。これで司法、警察当局への国民の不信が一気に高まった。人質事件の首謀者(アルパチノ)が一言「ATTICA」と叫ぶと、ヤジウマたちが彼の味方になってしまう。また、マスコミの偽善も露わにされる。彼と相棒は二人ともベトナム戦争帰還兵である。目的のはっきりしない戦争と意味のない殺戮を経験した彼らの多くは、国に戻ってからも人殺しを何とも思わなくなっていた。人質にされた店長と女子行員たちは比較的冷静である。むしろ犯人たちとの「うち解けた」会話から、彼女らの低い賃金や犯人の私生活が明らかになってゆく。主人公の犯人はバイセクシュアルなのだ。女房子供もいながら、深く愛する男性を「妻」にもしている。このことをテレビの報道で知ったゲイたちが、現場に駆けつけて自分たちの権利を主張して気勢を上げる。最後に破れかぶれになった犯人たちはバスを用意させ、空港には自分たちが世界地図のどこにあるかも知らないアルジェリア行きのジェット機を要求するが・・・(1975年)
Directed by Sidney Lumet Writing credits P.F. Kluge (article) Frank Pierson Cast; Al Pacino .... Sonny Wortzik / Penelope Allen .... Sylvia / Sully Boyar .... Mulvaney / John Cazale .... Sal ヒアリングー現場はニューヨークブルックリンだから、みんなしゃべるのはニューヨーク英語。早口であっても欲わかる歯切れのいい発音。
Paper Moon ペーパームーン 4/15/00
 タイトルのペーパームーンとは「紙製の月」で、縁日などで、記念の写真撮影の背景になる、段ボールか何かによってできている黄色い三日月である。たいていは恋人同士のツーショットで撮ることが多い。この歌はスタンダードになっている。ある薄幸の女の子(アディー)が母親の死後、かつて母親とつきあっていたという男(モーゼ)に連れられて叔母のところへ向かう。ところがこの男、聖書を言葉たくみに売りつける一種の詐欺師なのだが、アディーの勘の鋭さで、自分の商売が大変うまくいくようになってしまう。アディーからは自分は、あごの形が似ているので父親だといわれ、渋々つれていったのに、いつしか二人は本当の父娘のようになる。アメリカ映画によく見られるロードムービー(旅道中を描く)の一つで、途中で浮気女のダンサーとその小間使いが出てきたり、ある時は密造酒の販売人とのトラブルに巻き込まれる。最後に叔母の家に送り届けたとき、二人は再び一緒に旅を続けることになるのは観客には容易に想像できるだろう。73年の作品なのにあえて白黒だ。というのも時代がフランクリン大統領、つまり大恐慌のまださめやらぬ頃の話だからだ。また、実はこの二人、実生活では実の父娘だ。(1973年)
タイトルのペーパームーンとは「紙製の月」で、縁日などで、記念の写真撮影の背景になる、段ボールか何かによってできている黄色い三日月である。たいていは恋人同士のツーショットで撮ることが多い。この歌はスタンダードになっている。ある薄幸の女の子(アディー)が母親の死後、かつて母親とつきあっていたという男(モーゼ)に連れられて叔母のところへ向かう。ところがこの男、聖書を言葉たくみに売りつける一種の詐欺師なのだが、アディーの勘の鋭さで、自分の商売が大変うまくいくようになってしまう。アディーからは自分は、あごの形が似ているので父親だといわれ、渋々つれていったのに、いつしか二人は本当の父娘のようになる。アメリカ映画によく見られるロードムービー(旅道中を描く)の一つで、途中で浮気女のダンサーとその小間使いが出てきたり、ある時は密造酒の販売人とのトラブルに巻き込まれる。最後に叔母の家に送り届けたとき、二人は再び一緒に旅を続けることになるのは観客には容易に想像できるだろう。73年の作品なのにあえて白黒だ。というのも時代がフランクリン大統領、つまり大恐慌のまださめやらぬ頃の話だからだ。また、実はこの二人、実生活では実の父娘だ。(1973年)
Directed by Peter Bogdanovich Writing credits Joe David Brown (novel) Alvin Sargent Cast : Ryan O'Neal .... Moses Pray / Tatum O'Neal .... Addie Loggins / Madeline Kahn .... Trixie Delight / P.J. Johnson .... Imogene ヒアリングーきわめて早口。ミズーリ州など、中西部の英語が中心で、聞き取りにくいことこの上ない。アディも演技上、舌足らずな感じ。
Cry Freedom 遠い夜明け 04/20/00
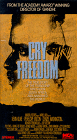 事実に基づいた映画。南アフリカのアパルトヘイトは、それに反対する人々に多くの犠牲を強いた。Steve Biko(1946‐1977)もそうだ。彼は、後に大統領となったマンデラと共に黒人たちの間で非常に人気があった。ソウェト蜂起(1976)の中心人物で、たびたび投獄され、裁判の時には、知恵に満ちた発言をした。そのため検事や裁判官らはたじたじとなるほどだった。たとえば、黒人は「黒」のイメージのため、余りよい印象を持たない。これに対し白人は「白」のイメージのため得をしている。ビコは、白人は白いというよりピンク色だということを指摘した。だが拘束中にもかかわらずその大胆な行動のため、首都へ向かう途中に捕らえられ、警官の暴行を受けて殺されてしまう。この事件は黒人たちを憤激させ、アパルトヘイト撤廃の大きなきっかけにもなった。ところで、彼と親交を結んだ、ウッズというリベラルな白人ジャーナリストがいた。ビコと知り合ううち、すっかり彼の魅力に惹かれ、彼についての伝記を書いた。だが、国内における締め付けは、ウッズもまた警察から狙われ、拘束される立場に追いやられてしまった。ウッズは国境を突破し、イギリスでその本を出版することを決意する。家族も共に軽飛行機に乗って国外に逃れる場面はまるで「サウンドオブミュージック」を思わせる。彼の出版した本は、世界中でアパルトヘイトに対する反対運動の世論をもりあげた。(1987年)
事実に基づいた映画。南アフリカのアパルトヘイトは、それに反対する人々に多くの犠牲を強いた。Steve Biko(1946‐1977)もそうだ。彼は、後に大統領となったマンデラと共に黒人たちの間で非常に人気があった。ソウェト蜂起(1976)の中心人物で、たびたび投獄され、裁判の時には、知恵に満ちた発言をした。そのため検事や裁判官らはたじたじとなるほどだった。たとえば、黒人は「黒」のイメージのため、余りよい印象を持たない。これに対し白人は「白」のイメージのため得をしている。ビコは、白人は白いというよりピンク色だということを指摘した。だが拘束中にもかかわらずその大胆な行動のため、首都へ向かう途中に捕らえられ、警官の暴行を受けて殺されてしまう。この事件は黒人たちを憤激させ、アパルトヘイト撤廃の大きなきっかけにもなった。ところで、彼と親交を結んだ、ウッズというリベラルな白人ジャーナリストがいた。ビコと知り合ううち、すっかり彼の魅力に惹かれ、彼についての伝記を書いた。だが、国内における締め付けは、ウッズもまた警察から狙われ、拘束される立場に追いやられてしまった。ウッズは国境を突破し、イギリスでその本を出版することを決意する。家族も共に軽飛行機に乗って国外に逃れる場面はまるで「サウンドオブミュージック」を思わせる。彼の出版した本は、世界中でアパルトヘイトに対する反対運動の世論をもりあげた。(1987年)
Directed by Richard Attenborough / Writing credits John Briley Cast; Kevin Kline .... Donald Woods / Penelope Wilton .... Wendy Woods / Kate Hardie .... Jane Woods / Denzel Washington .... Steve Biko / Juanita Waterman .... Ntsiki Biko ヒアリングーイギリス映画だが、特にイギリス訛りが強いわけでなく、南アフリカ風の英語であり、ゆっくりして歯切れの良い発音。
Gaslight ガス燈 04/22/00
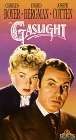 「おまえはまた忘れている」「さっき預けた品物はなくしたのか?」「何を思い違いしているんだ?」と四六時中言われたら、まるで自分はボケてしまったのだと思いこむに違いない。この恐ろしいやり方で妻(バーグマン)を精神的に参らせた夫は、彼女の死んだオペラ歌手である叔母が残した宝石を奪うことが目当てだったのだ。ヒッチコックのスリラーを思わせるこの作品は、白黒であることがますます不気味さを強め、もし叔母の元ファンであるロンドン警視庁の刑事が気づかなかったら、彼女は狂い死にしていただろう。ミステリーの構成も優れているが、イングリッド・バーグマンの見事な演技に驚かされる。彼女の独り舞台だといってもいい。そもそも「大」が付くような女優はただ美しいだけではダメなのだ。カメラのアングルによって、醜くなったり、かわいくなったり、恐ろしくなったり変貌自在の表現ができるかが問題だ。その点、彼女の顔の表情は、夫に責められているときのおびえた顔といい、最後に警察に捕まった夫を憎々しげにすさまじい形相で見つめる顔といい、カメラマンはそれらをアップにして、スクリーンいっぱいに観客に示すのだ。(1944年)
「おまえはまた忘れている」「さっき預けた品物はなくしたのか?」「何を思い違いしているんだ?」と四六時中言われたら、まるで自分はボケてしまったのだと思いこむに違いない。この恐ろしいやり方で妻(バーグマン)を精神的に参らせた夫は、彼女の死んだオペラ歌手である叔母が残した宝石を奪うことが目当てだったのだ。ヒッチコックのスリラーを思わせるこの作品は、白黒であることがますます不気味さを強め、もし叔母の元ファンであるロンドン警視庁の刑事が気づかなかったら、彼女は狂い死にしていただろう。ミステリーの構成も優れているが、イングリッド・バーグマンの見事な演技に驚かされる。彼女の独り舞台だといってもいい。そもそも「大」が付くような女優はただ美しいだけではダメなのだ。カメラのアングルによって、醜くなったり、かわいくなったり、恐ろしくなったり変貌自在の表現ができるかが問題だ。その点、彼女の顔の表情は、夫に責められているときのおびえた顔といい、最後に警察に捕まった夫を憎々しげにすさまじい形相で見つめる顔といい、カメラマンはそれらをアップにして、スクリーンいっぱいに観客に示すのだ。(1944年)
Directed by George Cukor Writing credits Patrick Hamilton (play) John Van Druten Cast overview: Charles Boyer .... Gregory Anton / Ingrid Bergman .... Paula Alquist / Joseph Cotten .... Brian Cameron / Dame May Whitty .... Miss Thwaites ヒアリングーきれいで聞き取りやすいロンドン英語。会話は内容が単純だからなおさらわかりやすい。
Viaggio in Italia イタリア旅行 04/27/00 (再)11/22/12
 11月22日は「いい夫婦の日」だ。離婚を考えている人、夫婦の危機に陥っている人たちは、この映画を見てみるのもいいかもしれない。ただし、この映画を真摯に理解し言っている意味が分かるセンスを持ち合わせている場合の話だが。
11月22日は「いい夫婦の日」だ。離婚を考えている人、夫婦の危機に陥っている人たちは、この映画を見てみるのもいいかもしれない。ただし、この映画を真摯に理解し言っている意味が分かるセンスを持ち合わせている場合の話だが。
中年夫婦が車に乗ってナポリへ向かっている。仲が良さそうではない。会話からすると、裕福ではあるが8年の結婚生活の後、お互いにうんざりし退屈しきっているのがわかる。
ナポリについて、自分たちの別荘に着くと、二人の間のよそよそしさは一層激しくなる。友だちが来ているときは何とか救われるが、二人きりになると、お互いの敵意むき出しだ。妻は博物館めぐり、夫はカプリ島に遊びに行くというわけで、趣味も違う。イタリアになんか来ないで、ロンドンで仕事をしていれば良かったのだ。
最後に友人のぜひともという招きで二人で出かけたポンペイの遺跡の中で、二人は離婚を決意する。だが妻は夫のいない生活の寂しさを予感していた。騒々しいナポリのお祭りの中で、人々が大勢町を埋め尽くしている。子供たちも大勢いて、みんな楽しそうだ。陽気なナポリっ子に囲まれて、二人はしっかりと抱き合う。
シンプルな映画だ。ナポリの風景を楽しむために観てもいいし、夫婦関係の機敏を観察するために観てもいいだろう。既婚者は自分の私生活を重ね合わせてみるのもよい。
「ガス燈」のイングリッド・バーグマンがまたまたここで大活躍だ。あの映画から9年後、中年女としての彼女も、その表情の変化の見事さは少しも変わっていない。
やはりカメラマンは彼女の顔を大写しにして、観客に訴えかける。大根役者じゃないから、画面がすべて彼女の顔が映されていても、少しもバーグマンの個性はスクリーンに負けない。(1953年)・・・資料![]()
Directed by Roberto Rossellini Writing credits Vitaliano Brancati Roberto Rossellini Cast: Ingrid Bergman .... Katherine Joyce / George Sanders .... Alexander Joyce ヒアリングーイタリア映画で、すべてイタリア語。バーグマンのイタリア語は、ほかの俳優と比べても何ら遜色なし。
History is Made at Night 歴史は夜作られる 4/29/00
 嫉妬に狂う、海運王の夫に愛想を尽かした妻アイリーンは、パリのレストランの給仕長ポールに恋をする。恋をして、本当に相手が信頼できるようになるには(つまり歴史ができあがるのは)、「一晩」あればよい。彼は殺人事件のぬれぎぬを着せられ、妻は夫に無理矢理ニューヨークへつれて行かれるが、、ニューヨークのレストランに移って活躍する給仕長と、コック長シーザーに巡り会えた。無罪の罪を着せられた男を救うべくパリへ向かう二人、だが乗った船アイリーン号は海運王が記録にこだわる処女航海についていた。船は氷山のたくさん流れる地域に全速力で突入してゆく・・・、とはいってもこれはタイタニックの物語ではない。指人形というのがあるが、この映画の最も素晴らしいコミュニケーションの手段は、「手」人形であり、親指と人差し指の間を口にして、しゃべらせる愛嬌のある芸だ。給仕長は、この「人形」にしゃべらせて、彼女に自分の気持ちを伝える。また彼女のほうも再び巡り会えたときに、この「人形」を使って会えなかった間いかに深く思っていたかを伝える。また、給仕長ポールは「桃太郎侍」に似ている。彼は自分の仕事に誇りを持ち、彼の給仕によって、再びそのレストランを訪れる客が後を絶たない。二人の思い出のメニューはロブスターと野菜サラダとピンク・ワインの組み合わせ。それもシーザーが腕によりをかけたもの。この映画の全体構成は大したことはないが、細部に様々な魅力を秘めている。(1937年)Directed by Frank Borzage // Writing credits C. Graham Baker Gene Towne
// Cast: Charles Boyer .... Paul Dumond / Jean Arthur .... Irene Vail /
Leo Carrillo .... Cesare / Colin Clive .... Bruce Vail ヒアリングー何かフランス訛りが入っているような気がするが、大部分はニューヨーク英語。
嫉妬に狂う、海運王の夫に愛想を尽かした妻アイリーンは、パリのレストランの給仕長ポールに恋をする。恋をして、本当に相手が信頼できるようになるには(つまり歴史ができあがるのは)、「一晩」あればよい。彼は殺人事件のぬれぎぬを着せられ、妻は夫に無理矢理ニューヨークへつれて行かれるが、、ニューヨークのレストランに移って活躍する給仕長と、コック長シーザーに巡り会えた。無罪の罪を着せられた男を救うべくパリへ向かう二人、だが乗った船アイリーン号は海運王が記録にこだわる処女航海についていた。船は氷山のたくさん流れる地域に全速力で突入してゆく・・・、とはいってもこれはタイタニックの物語ではない。指人形というのがあるが、この映画の最も素晴らしいコミュニケーションの手段は、「手」人形であり、親指と人差し指の間を口にして、しゃべらせる愛嬌のある芸だ。給仕長は、この「人形」にしゃべらせて、彼女に自分の気持ちを伝える。また彼女のほうも再び巡り会えたときに、この「人形」を使って会えなかった間いかに深く思っていたかを伝える。また、給仕長ポールは「桃太郎侍」に似ている。彼は自分の仕事に誇りを持ち、彼の給仕によって、再びそのレストランを訪れる客が後を絶たない。二人の思い出のメニューはロブスターと野菜サラダとピンク・ワインの組み合わせ。それもシーザーが腕によりをかけたもの。この映画の全体構成は大したことはないが、細部に様々な魅力を秘めている。(1937年)Directed by Frank Borzage // Writing credits C. Graham Baker Gene Towne
// Cast: Charles Boyer .... Paul Dumond / Jean Arthur .... Irene Vail /
Leo Carrillo .... Cesare / Colin Clive .... Bruce Vail ヒアリングー何かフランス訛りが入っているような気がするが、大部分はニューヨーク英語。
Fried Green Tomatoes フライドグリーントマト 5/4/00 (再)2012/11/23
 友情で結ばれたイジーとルースという二人の若い女性が、アメリカ南部アラバマ州でレストラン経営をしてさまざまな事件に巻き込まれる1代記。二人の共通の思い出は、足がレールに挟まり列車に轢かれたイジーの兄。ショッキングなシーンである。彼が事故に遭う前に話した「カモの大群が、厳寒で凍ってしまった湖ごと飛んでいってしまった」というホラ話がいつも引き合いに出される。
友情で結ばれたイジーとルースという二人の若い女性が、アメリカ南部アラバマ州でレストラン経営をしてさまざまな事件に巻き込まれる1代記。二人の共通の思い出は、足がレールに挟まり列車に轢かれたイジーの兄。ショッキングなシーンである。彼が事故に遭う前に話した「カモの大群が、厳寒で凍ってしまった湖ごと飛んでいってしまった」というホラ話がいつも引き合いに出される。
グリーントマトの料理はレストランでの二人の仲の良さの象徴である。群れ飛ぶ蜂の巣の中に素手を入れてイジーが蜜を取る話、ルースの暴力を振るう夫を始末する話、裁判で牧師が偽の証言をする話など、など、平凡に見えながら、さまざまな起伏がドラマの中にちりばめられている。
登場人物は、ルースを密かに愛した浮浪者、ルースを小さいときから面倒を見てくれてレストランの焼き肉係りでもある黒人、ルースの夫殺しの犯人を執拗に追う刑事、などみな後で思い出すと懐かしくなるような人ばかり。また、この話は、老人ホームで話し相手を捜すニニー(老イジー)が、結婚倦怠期で人生の行く末に悩む中年の太った女性エベリンに話して聞かせるかたちで現れる。話を聞いたエベリンの現実の世界での人生の建て直しと、イジーの思い出話が、うまくかみ合って、複雑なストーリーが進んでゆく。(1991年)・・・資料![]()
Directed by Jon Avnet // Writing credits Fannie Flagg (also novel) Carol Sobieski // Cast : Kathy Bates .... Evelyn / Couch Mary Stuart Masterson .... Idgie / Threadgoode Mary-Louise Parker .... Ruth / Jessica Tandy .... Ninny Threadgoode ヒアリングー聞き取りにくい南部英語、というわけではない。すべての登場人物の話し方は標準的。
Looking for Mr.Goodbar ミスター・グッドバー氏を探して 5/6/00
 ヒロインであるテレサは、美しい体を持っているが、幼い頃ポリオにかかり、脊髄を手術し、またいつそれがぶり返すかわからない。ろうあ小学校の教師だが、妻子ある男性教師の気をひこうと立ち回る。だが、実際のセックスの場で彼は最後までやってくれない。そのうち彼とは別れ、彼女は居酒屋ミスターグッドバーで酒を飲み、自分に関心のありそうな男たちを漁り始める。やくざなバンドマンや、福祉事業の仕事に就くまじめな青年とつきあうが、なぜか最後までゆく関係にならない。満たされないまま、コカインやマリファナに手を出し、売春婦のまねもしてみるが男と深い関係になることは決してない。カトリックの父親にも愛想を尽かされ、ろうあ学校の生徒にもみすかされる。最後はまたグッドバーで見つけた、変質的な男を部屋に入れ、狂った男のナイフによってずたずたに刺されて死ぬ。お粗末な生涯であるが、映画の作りそのものはお粗末ではなく、6,70年代のセックス、ドラッグ革命の行く末を暗示している。そのため、当時の時代背景を知らないと、ただの「男漁り」映画としかとらえられない危険性がある。なお、慣れない人には、ヒロインが心の中で想像した情景が突然、実際の話の流れに挿入されるため、その区別が理解できないかもしれない。だがその唐突さも彼女の不安定さをよく表しているともいえる。たとえば、相手の男を見ているとき、突然彼女がその男に愛される場面が登場するが、それは実は彼女の願望の現れなのである。(1977年)Directed by Richard Brooks (I) Writing credits Richard Brooks Cast : Diane
Keaton .... Theresa Dunn / Tuesday Weld .... Katherine Dunn / William Atherton
.... James Morrissey / Richard Kiley .... Mr. Dunn / Richard Gere ....
Tony Lopanto ヒアリングーマンハッタンのポルノ街が中心のニューヨーク英語。麻薬や酒でろれつが回らないところを除けば、標準的で聞きやすい。
ヒロインであるテレサは、美しい体を持っているが、幼い頃ポリオにかかり、脊髄を手術し、またいつそれがぶり返すかわからない。ろうあ小学校の教師だが、妻子ある男性教師の気をひこうと立ち回る。だが、実際のセックスの場で彼は最後までやってくれない。そのうち彼とは別れ、彼女は居酒屋ミスターグッドバーで酒を飲み、自分に関心のありそうな男たちを漁り始める。やくざなバンドマンや、福祉事業の仕事に就くまじめな青年とつきあうが、なぜか最後までゆく関係にならない。満たされないまま、コカインやマリファナに手を出し、売春婦のまねもしてみるが男と深い関係になることは決してない。カトリックの父親にも愛想を尽かされ、ろうあ学校の生徒にもみすかされる。最後はまたグッドバーで見つけた、変質的な男を部屋に入れ、狂った男のナイフによってずたずたに刺されて死ぬ。お粗末な生涯であるが、映画の作りそのものはお粗末ではなく、6,70年代のセックス、ドラッグ革命の行く末を暗示している。そのため、当時の時代背景を知らないと、ただの「男漁り」映画としかとらえられない危険性がある。なお、慣れない人には、ヒロインが心の中で想像した情景が突然、実際の話の流れに挿入されるため、その区別が理解できないかもしれない。だがその唐突さも彼女の不安定さをよく表しているともいえる。たとえば、相手の男を見ているとき、突然彼女がその男に愛される場面が登場するが、それは実は彼女の願望の現れなのである。(1977年)Directed by Richard Brooks (I) Writing credits Richard Brooks Cast : Diane
Keaton .... Theresa Dunn / Tuesday Weld .... Katherine Dunn / William Atherton
.... James Morrissey / Richard Kiley .... Mr. Dunn / Richard Gere ....
Tony Lopanto ヒアリングーマンハッタンのポルノ街が中心のニューヨーク英語。麻薬や酒でろれつが回らないところを除けば、標準的で聞きやすい。
Casablanca カサブランカ 2000/5/11 2006/12/12
 パリで反ナチ運動をしていたリック(ボガード)が、同じくレジスタンス運動をしていた男の妻であるイライザ(バーグマン)に恋をするが、虐殺されていたと思われていた夫が突然生還したため、イライザはふたりで一緒に国外へ逃げる約束を破り、リックだけがさまざまな流浪のうちにモロッコのカサブランカに酒場を開いて落ち着いている。ナチスはパリを占領し、フランスは親ナチのヴィシー政権(1940-1944)だった時代である。
パリで反ナチ運動をしていたリック(ボガード)が、同じくレジスタンス運動をしていた男の妻であるイライザ(バーグマン)に恋をするが、虐殺されていたと思われていた夫が突然生還したため、イライザはふたりで一緒に国外へ逃げる約束を破り、リックだけがさまざまな流浪のうちにモロッコのカサブランカに酒場を開いて落ち着いている。ナチスはパリを占領し、フランスは親ナチのヴィシー政権(1940-1944)だった時代である。
そこへ偶然にもイライザが夫と共に彼の酒場に突然現れる。夫は出国ビザを得て、リスボン経由でアメリカに亡命を望んでいるのだ。はじめは彼女の昔の裏切りにこだわっていたリックも、次第に心を和らげ、最後には夫妻が無事亡命できるように取りはからってやる。
 イライザは、夫とリックの間に引き裂かれそうになるが、リックと別れる決心がつかない。イライザから決断をゆだねられたリックは結局、身をひく。典型的な「おとなの映画」である。ただし、リック自身が犠牲になるということではない。彼女がそのまま自分とカサブランカに残っても後悔するだろうから、夫と共にさらに反ナチ活動に邁進して欲しいという前向きの姿勢なのだ。
イライザは、夫とリックの間に引き裂かれそうになるが、リックと別れる決心がつかない。イライザから決断をゆだねられたリックは結局、身をひく。典型的な「おとなの映画」である。ただし、リック自身が犠牲になるということではない。彼女がそのまま自分とカサブランカに残っても後悔するだろうから、夫と共にさらに反ナチ活動に邁進して欲しいという前向きの姿勢なのだ。
また二人のパリでの思い出の、Dooley Wilson 演じる酒場のピアノ弾き Sam による As Time Goes By は切ない名曲だ。リックのレストランのピアニストの演奏として披露される。フランス領であるカサブランカの町の警察署長、ルノー大尉も忘れがたい。ナチに従うように見えながら、リックの人柄に惹かれて、最後に夫妻が飛行機で出国する際にはリックに全面的に協力する。
ここでも「ガス燈」と同じく、バーグマンはただ美しいだけでなく、実に表情が豊かだ。スクリーンいっぱいに写されても決して画像負けしない、大変な女優だ。2人の男が現れてしまった苦悩を見事に演じている。それにしても、配役といい、音楽といい、物語の構成といい、どれをとっても文句なく一流の映画だといえよう。(1942年)
Directed by Michael Curtiz Writing credits Murray Burnett (play) Joan Alison Cast: Humphrey Bogart .... Richard "Rick" Blaine / Ingrid Bergman .... Ilsa / Lund Laszlo Paul Henreid .... Victor Laszlo / Claude Rains .... Captain Louis Renault ヒアリングーフランス領の町なのに、フランス人もアメリカ人もドイツ人もみな完璧な英語をしゃべる。これはハリウッド映画なのだ。
Sophie's Choice ソフィーの選択 5/20/00
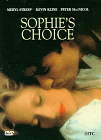 この映画が痛々しいのは、現代に生きながら、ナチによるすさまじい体験を引きずっていることだ。ヒロインのソフィーは、親ナチの父と夫を持ったポーランド人だったが、ナチのポーランド侵攻によって二人とも失い、自分も闇物資を持っていたためにアウシュビッツ強制収容所に送られる。最も悲惨なのは、自分の幼い娘と息子のどちらかを「選択」しなければ、両方とも殺されるという状況に置かれたことだ。彼女自身がドイツ語がきわめてうまかったために、収容所では秘書の仕事をもらい、最終的に収容所から生還できるが、ニューヨークに移り住んでも彼女の心の傷はいやされないままだった。そこへネイサンという精神分裂症気味だが、彼女を心から包容してくれる男に巡り会い、共同生活を始める。だが、ネイサンは時々発作を起こし、彼女の心を平気で傷つけるようなことを口走る。同じアパートに住むことになった南部の田舎から出てきた作家志望の青年スティンゴもソフィーにあこがれ、この二人と無二の親友になり、彼女の過去を徐々に知ってゆく。ソフィーはメリル・ストリープが演じているが、2000年1月15日に見た「Falling in Love」がデ・ニーロと対等に演じたのと違い、まさに彼女の独壇場だ。バーグマンと同じく、その表情の変化の見事さ、スクリーンに大写ししても少しも負けない演技力はやはり大女優の名にふさわしい。(1982年)Directed by Alan J. Pakula Writing credits Alan J. Pakula Cast : Meryl
Streep .... Sophie Zawistowska Kevin Kline .... Nathan Peter MacNicol ....
Stingo ヒアリングーニューヨークの標準英語以外に、大変特徴的なのは、メリル演じるソフィーが帰化したポーランド人だということになっているから、英語がうまくなく、ポーランド語訛りの、わざとゆっくりブロークンなしゃべり方をすることだ。
この映画が痛々しいのは、現代に生きながら、ナチによるすさまじい体験を引きずっていることだ。ヒロインのソフィーは、親ナチの父と夫を持ったポーランド人だったが、ナチのポーランド侵攻によって二人とも失い、自分も闇物資を持っていたためにアウシュビッツ強制収容所に送られる。最も悲惨なのは、自分の幼い娘と息子のどちらかを「選択」しなければ、両方とも殺されるという状況に置かれたことだ。彼女自身がドイツ語がきわめてうまかったために、収容所では秘書の仕事をもらい、最終的に収容所から生還できるが、ニューヨークに移り住んでも彼女の心の傷はいやされないままだった。そこへネイサンという精神分裂症気味だが、彼女を心から包容してくれる男に巡り会い、共同生活を始める。だが、ネイサンは時々発作を起こし、彼女の心を平気で傷つけるようなことを口走る。同じアパートに住むことになった南部の田舎から出てきた作家志望の青年スティンゴもソフィーにあこがれ、この二人と無二の親友になり、彼女の過去を徐々に知ってゆく。ソフィーはメリル・ストリープが演じているが、2000年1月15日に見た「Falling in Love」がデ・ニーロと対等に演じたのと違い、まさに彼女の独壇場だ。バーグマンと同じく、その表情の変化の見事さ、スクリーンに大写ししても少しも負けない演技力はやはり大女優の名にふさわしい。(1982年)Directed by Alan J. Pakula Writing credits Alan J. Pakula Cast : Meryl
Streep .... Sophie Zawistowska Kevin Kline .... Nathan Peter MacNicol ....
Stingo ヒアリングーニューヨークの標準英語以外に、大変特徴的なのは、メリル演じるソフィーが帰化したポーランド人だということになっているから、英語がうまくなく、ポーランド語訛りの、わざとゆっくりブロークンなしゃべり方をすることだ。
H O M E > 体験編 > 映画の世界 > コメント集(6)
© 西田茂博 NISHIDA shigehiro
