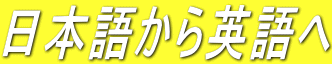第4章 全般的な違い:その2
前の章では動詞と主語を中心に見てきましたが、今度はもう少し立ち入った点から除いて見ます。文末の動詞に次々といろいろな語がつく現象、「いる」と「ある」のちがい、など改めて日本語には見直しておかなければならない点がたくさんあります。
例文1;はげしく雨が降り風も吹いているので、傘を3本ばかり持っていこうかな。Since it is raining and blowing hard, I might as well take three or more umbrellas.
日本語には名詞と結びつく<助詞>とよばれるものがあり、これはユーラシア大陸の中央部(アルタイ語系、ウラル語系)にも数多く見受けられる文法上の重要な機能を持った品詞です。こういう機能の助詞が西欧諸国語にはなく、性質が大きく異なることも学習を困難にしている大きな要因です。
助詞にはいろいろな種類があり、その中で西欧語における<前置詞>に対応しそうなのが、<後置詞>つまり<格助詞>です。これは前置詞が名詞の前につくのに対し、名詞のうしろにつけるわけですから順序がまったく逆になります。
例1での「雨+が」、「傘+を」がそれにあたり、これにより「雨」が主語、「傘」が目的語だということが示されることになります。「雨」と「が」がまるで膠(にかわ)という接着剤で結合されたようだというわけで<膠着(こうちゃく)>とよばれています。
前置詞の場合ですと in my room のように前置詞とそのうしろの名詞要素とは<分かち書き>を必ずしますが、格助詞の場合では普通ひらがなを続けて書いています。ですから「雨が amega 」は二つの要素がくっついているように見えるのです。しかしローマ字表記であれば ame ga でも amega でも両方可能です。前者の表記法はまさに後置詞として認識されているといえましょう。
一方、英語をはじめとする西欧語では bus の複数形が buses となり、これを、<語尾変化>とよんでいますが、日本語でも見方によっては ame が amega というように語尾変化を起こしているといえないわけではありません。ロシア語などの学習でさんざん語尾変化に悩まされた人にとっては特にそう見えるかもしれません。
もう一つの助詞は西欧語の<接続詞>に対応することの多い、<接続助詞>です。これも英語などの西欧語では<接続詞+主語+動詞・・・>の語順なのに対し、<主語+動詞・・・+接続助詞>というように正反対の語順になりますから、「吹いているので huiteirunode 」のように「ので」が文の最後(正確には動詞の辞書形+ノデ)につけてあります。ひらがなでもローマ字でも前の文とつなげて書くのが普通ですのでこれはことさら膠着のイメージが強いのです。
では文末表現はどうでしょうか?「持っていこうかな motteikoukana 」は「持つ→持って・いく→持って・いこう→持って・いこう・かな」とうしろに補助動詞「 iku 」、助動詞「 ou 」そして最後に終助詞「 kana 」を次々と付け加えてあります。これをローマ字で表記するときにさすがにバラバラで書く人はいませんね。まさに動詞を中心にさまざまな要素をうしろにつけた典型的な”膠着状態”です。
最後に「傘を持って→傘を・3本・持って→傘を・3本・ばかり・持って」にみられるように「3本」と「ばかり」は、とりはずしがきき、絶対不可欠な部分ではないということになります。これらは文の中での副詞的要素といえます。このうち「3本」は数量的なものですが、もう一つの「ばかり」は副助詞とよばれ西欧語の副詞にほぼ該当するとみてよいでしょう。
このように日本語の助詞はさまざまな見方が可能であり、論者によってかなり相違があるようですが、膠着語のイメージは漢字仮名交じり文の外見から生じた書き方から生まれ、その結果、外観がまるで一つの単語のように見えるようになってしまったものを表したのだといえます。外国人の日本語学習の初心者はそれをいちいち解きほぐしてバラバラにし、それぞれの意味を確認しなければならない厄介な存在です。
省略は日本語の中でももっとも重大な特徴です。普通の日本語文を見て省略されている部分を見抜き、きちんと復元しないと外国語、特に西欧語に変換することができません。ここでの復元とは「普遍的な言語ルール」というものがあるとすれば、それを満たすのに必要な要素を入れるということです。
<ウォーミング・アップ>次の例文はどこが省略されていますか。補ったり書き換えたりしてみましょう。
例文1;(場面;レストランでの食事)何にする?ビフテキだ。飲み物は?ビールね。(場面;食事が運ばれてくる)熱い!どうしたの、やけどした?大したことないよ。指がね、ちょっと赤くなっただけ。ところで出発は何時?10時半だ。じゃあ、まだあと1時間半あるね。
補足例;(レストランで)あなたは何を食べますか?私はビフテキを食べるつもりです。あなたは何を飲みますか?私はビールを飲みたいです。(運ばれてきて)このビフテキは熱い!何が起こったの?あなたはやけどしましたか?私のやけどはたいしたことはありません。なぜなら私の指が少し赤くなっただけだからです。ところであなたは何時に出発するのですか?私は10時半に出発する予定です。じゃあ、出発までまだあと1時間半あるね。
こんなにたくさんつけ加えた訂正では、会話がちっとも進まないじゃないかと思う人がいるかもしれません。しかしこうでもしなければ、国際的に通用しないのです。大部分の日本語学習者はこんなふうにしゃべっています。つまり外国語に移し替えて、しかもコミュニケーションが成立するためには、これほどまでに補い変形しなければなりません。また、大部分の話し言葉が「ダ」や「ネ」などで終わっています。これらは相手が了承ずみだということを示す信号でもあるのです。
日本語を母語とする人は、そのような省略にすっかり慣れてしまっていて、こんなに大量になされていることを意識しない。だから外国語への切り替えが不得意なのだといえます。一番に目につくのはなんといっても主語の省略。ほとんど主語がありません。それでも二人の会話はスムーズに進んでいます。
いちばん気になるのは国会での答弁でしょう。質問する側はかなり気を使って明快な日本語をしゃべっていますが、答える側はなるべく少ない語彙で済ませようとするためか、それともイヤイヤだからなのか、驚くほど省略が多い。政治家の言葉を外国語に通訳する人の察しの良いことに頭が下がります。政治家は気分次第でたくさんの言葉をはしょります。これでは通訳や翻訳者によっぽどがんばってもらわないと、国際会議などでは外交問題に発展しかねません。
例文2;東京の人口は大阪より多い。 The population of Tokyo is larger than that of Osaka.
比較の文における省略は例2に現れています。比較するもの同士は原則として等しいレベルになければならない。わたしとあなた、イギリスとフランス、それならば「東京の人口」と「大阪の人口」です。英語では代名詞 that (of) を利用して繰り返しの手間を省いていますが日本語ではズバリ書かないのが普通ですね。
例文3;「テーブルの上にあるナイフを使ってリンゴを切りなさい。」「よく切れないよ」「もっとしっかりつかむのよ」「あっ、切っちゃった!」
日常ではよくきく会話です。この通り、主語はもちろんのこと、目的語さえも省略しています。それでもこの場に居合わせる限りは、滞りなく会話をすすめることができるでしょう。この文を英語に翻訳するならば、次のように言葉を補わなければなりません。
「(その)テーブルの上にある(一本の)ナイフを使って(その)リンゴを切りなさい。Cut the apple with a knife on the table. 」「(僕は)(そのナイフでは)(そのリンゴは)よく切れないよ I can't cut it well with it. / (その)ナイフは切れ味が悪いThe knife doesn't cut well. 」「(あなたは)(ナイフの握りを)もっとしっかりつかむのよ。 Grip the handle more firmly. 」「あっ、(僕は)(自分の指を)切っちゃった!Oh! I cut myself!」
英文では<主語+動詞+目的語>などの構文上の構成要素はいつもそろえておくようにします。その場合は可能な限り、代名詞を使う。また、冠詞を使って特定のものを示す。どうしても省略する場合は「すでに一度出てきたもの」だけに限る、というのが鉄則です。ですから誰でも省略された文は規則を知っている限り誰でも復元することができます。
こうやって見ると、日本語の場合の省略は文法的な規則に基づくのではなく、かなり”気分しだい”で省略がおこなわれるために、身内の間での会話の場合には問題ないが、思考習慣も、文化的背景も異なる人との間での会話では当然のことながら、意味不明の部分が出てきてしまうのです。自分のいいたいことのうちどれだけを言語化すべきか常に適切な情報量を考えておかなければなりません。
これらのことを念頭において、常に次のような過程をふむ習慣をつけましょう。<日本語の文→(理想文)→外国語の文>のように。<外国語の文→(理想文)→日本語の文>の場合も同様です。<理想文>とは何語で書かれていてもかまいませんが、主語・理由・明確な代名詞・主観客観の区別などが”くどい”といわれるくらいきちんと収まっているものをいいます。言い換えると、相手に伝達するのに必要なすべての情報のことです。
日本語では生物・無生物によって存在の表現を動詞の「いる」と「ある」で使い分けますが、英語ではそんなことはしません。英語で生物無生物にかかわりなく存在に使う動詞は(すでに述べたコピュラの働きとは別の) be動詞です。またこの be動詞をさらに「存在する exist 」や「暮らす live 」「横たわる lie 」のような存在タイプの自動詞に置き換えることもできます。またどの部分に重点を置くかによって存在表現には2種類あり、その違いは英語でも日本語でも守られています。
例文1;その地区に公園があります。There is a park in the area.
例文2;その公園に少女がいます。There is a girl in the park.
例1,2での基本表現は「・・・に(生物)がいます」「・・・に(無生物)があります」の二つです。それぞれは「公園に(誰が)いますか?」「公園に(何が)ありますか?」という質問の答えだと考えられます。つまり存在する場所は一応わかっているが、そこにどんなモノ・ヒトがいるか、あるかを示すことがこのタイプの文の使い道です。これらの表現では主語に「・・・ガ」を使っています。
英語の場合、このタイプは There構文を使います。これは「There + be + 名詞(+場所の副詞)」が基本的な語順となります。be動詞は時制や人称に応じて変化します。そのうしろにくる名詞はbe動詞がそれに対応して形を変えることから<主語>ということになっています。最後に場所をあらわす副詞相当語句が来ますが、その多くは<前置詞+名詞>の形をとります。
話の中心は日本語の場合と同じく、まん中の<主語>の部分です。ここに入る生物・無生物は聞き手にとって初めて紹介されるわけですから、すでに知っていることを示す印である th-, 所有格などの形をとることは滅多にありません。
例文3;その公園はその地区にあります。The park is in the area.
例文4;その少女は公園にいます。 The girl is in the park..
もう一つの基本表現は例3,4での「(生物)は・・・にいます」「(無生物)は・・・にあります」です。これらは「(その)生物はどこにいますか」「(その)無生物はどこにありますか」という質問の答えであり何なのか、誰なのかはあらかじめわかっていて、その存在する場所が話の中心になっています。例1,2と違うところは、まず主題(主語と兼用)を取り上げるために「・・・ハ」で始めています。
英語でも There構文とは別の形式を使っています。また、あらかじめわかっている名詞(主語)はそれを示すために th- * か所有格をつけてあります。存在動詞と場所の副詞はそのうしろです。語順は<th- / 所有格+主語+ be動詞+場所の副詞>と表すことができます。
このように存在文は、2種類の機能を持っており、ときと場合により、それらを両国語ともうまく使い分けなければなりません。この区別はほかの言語にも見受けられます。世界中どこでも日常生活を営む上で、どうしてもこの違いをはっきりさせないと困るからでしょう。
蛇足ですが、こうやってみると日本語には英語における<定冠詞>はないけれども「・・・ハ」は定冠詞のある場合、「・・・ガ」は”初登場”の場合というように、これらを適切に使うことによってある程度その機能を肩代わりしているのかもしれません。
* 注;th- とは the / this / that / these / those の5種類のことを言います。これに they / them を付け加える場合もあります。いずれもある名詞を指定したり特定したりすることが特徴です。
<どれだけわかりますか?>
次の文中にある下線部1~5の「ある」はどんな働きでしょう。
渡辺さんにはワンルームが(1)ある。名古屋に(2)あって、ベッドもそのままにして(3)あるから、いつでも寝泊まりできるので(4)ある。当地で会議が(5)あるときは必ず行く。
(1)所有(2)存在(3)結果の状態(4)である体(5)開催
このように日本語では「アル」という表現でも本来の<存在>の意味を持つ場合はごく一部です。それ以外はそこからいくつか派生してはいるものの、すっかり異なる意味を持つようになっています。この点では「イル」も同様です。
主語とはある動詞が使われるときのその主体であり、目的語とは動詞がその意味を明確に示すために必要な新たな名詞である、と考えられます。英語でも日本語でも、主語と目的語の概念は同じものにしておいた方がよいでしょう。それによって、それぞれの言語で置かれている文法上の位置の違いがはっきりします。
主語については、動詞の主体となる名詞(または名詞相当語句)であること。あくまでも「主体」であって、「主題」にする必要はありません。日本語での「・・・ハ」を主語そのものと勘違いしている人がいます。「走る run 」であれば、実際に走る動物や人間や物体でなければなりません。「象は鼻が長い」の場合は「長い」と直接関係を持つのは「象」ではなく「鼻」ですからこれが主語ということになります。日本語では主語と主題が兼用のこともあれば、別々に設けられることもあるわけです。
主語は英語でも決定するのが意外にむずかしい場合があります。たとえば「(雨が)降る rain 」の主語は何かなどという問題が起こります。単に「降る fall 」であればその主語を「雨 rain 」とすればいいのですが、rain という動詞の場合はいったい何が主語なのでしょうか?空でしょうか、雲でしょうか、天候という抽象的なものでしょうか?
いろいろと議論がもめそうです。英語ではこのような場合に it (天気の it )を主語にすることにしました。 it の中身は各自想像してくれということです。また他の言語では判定が困難なときはじめから明確な主語をつけるのをやめてしまいました。これを<無人称構文>ということがあります。
日本語の場合には、主語を確定することがいっそう困難な例が数多くあります。主語を省略するのが日常茶飯事になったのにはそのような背景があるのかもしれません。主語は各自の「察し」によって決まるのかもしれません。でも実際のところ主語がなくても成立する場面は数多くあるのです。主語が必須の要素という考えは捨てなければならないかもしれません。
次に、目的語の場合は、「ビールを飲む drink beer 」と「飲む drink 」とを比較してみればいいでしょうか。主語と同じく、必ず名詞相当語句であること。「飲む」に関していえば、それだけでは飲むのが水なのか、ジュースなのか、ウィスキーなのかわからない、つまり<情報不足>に陥っています。これを解消するための語が目的語です。
ただ夜におとなの仲間同士で「飲もうぜ」と言うときにはアルコール類であるという暗黙の了解があるために、目的語を<省略>しているに過ぎません。ということは目的語を持つ<他動詞>と目的語を持たない<自動詞>という区別は情報量の多いか少ないかだけで済むのだと思う人がいるかもしれませんが、どうもそう一筋縄ではいかないのです。
例文1;彼は旗を上げた He raised the flag.
例文2;旗が上がった The flag rose.
「(主語)が(目的語)をあげる raise 」と「(主語)があがる rise 」は同一語源から生まれた他動詞・自動詞の例として英語学習でも日本語でもよく引き合いに出されますが、例1,2で見るとおり、目的語が追加されるだけではすまない場合があることに気づきます。
つまり主語の持つ性質の違いです。他動詞では「彼 He 」が主語として新たに加わっている。「飲む drink 」の主語は自動詞でも他動詞でも、常に生物ですから心配ありませんが、こちらはまったく別タイプの主語に変更するという構造上の大変化がおきているわけです。このことには昔の人も気づいていて「他動詞+目的語 VO」の組み合わせの場合の主語(能格という場合がある)は自動詞の主語(主格)とはまったく別物だとはっきりと区別している言語もあるくらいです。
幸いなことに、英語のある動詞の他動詞は日本語の場合にも他動詞になる場合が大多数です。つまり意味の上で共通ならば、目的語を要求するかどうかも言語間で共通な場合が多いのです。ただしそれぞれの言語内での固有な現象を知らないと、そのことに気づかないことがあります。次の例を見て下さい。
例文3;その写真を見てごらん。○ Look at the picture.× Look the picture.
例文4;彼らはその問題について議論した。 ○ They discussed the matter. × They discussed about the matter. ○ They talked about the matter.
例3での「写真を見る」は日本語ではれっきとした VO関係です。ところが英語に目を転じると、look が自動詞ではないか!というわけです。しかしよく見ると前置詞 at がそのうしろについています。前置詞はそのうしろに名詞(目的語)を連結しますから、動詞の直後についた場合には look at の組み合わせで一語の他動詞であると見なしていいわけです。look は本来自動詞としての意味から出発しており、at / for / into などがつくことによりはじめて他動詞の機能を発揮するようになったのです。
例4はその逆の例です。日本語では「議論する」は自動詞であり、「・・・について」は助詞(後置詞)の一種ですので、これがそのまま英語にも通用するような気がします。ところが discuss という動詞は「・・・について」の意味も含んだ他動詞であり、途中に about のような前置詞をはさむ必要はありません。ところが discuss の類語である talk は自動詞なので再び前置詞が必要になります。
このようにしてみると英語での他動詞と自動詞の違いは個々の動詞にあらわれるというよりはうしろに目的語(ここでは the picture / the matter )が必要かどうかという問題に絞られ、そこにたどり着くまでの構造はその語の歴史的経過を反映してさまざまだ、ということになるようです。たとえば「赤ちゃんの世話をする take care of the baby 」の場合ですと、日本語では「赤ちゃんの+世話を+する」というように3つの部分に分解されますが英語の場合、「take care of 」が一語の他動詞として、「 the baby 」が一語の目的語として扱われているのです。
英語では目的語を持つ動詞(句)の形は、VO の他に(1) V 前置詞 O (2) V O 副詞 (3) V O 前置詞 O (4) V 副詞 前置詞 O と4種類のパターン(注)がありますが、いずれの場合でも O を含んでいるため他動詞の役割を果たしているわけです。
(注)それぞれの例として(1)「彼をあざ笑う laugh at him 」(2)「会議を延期する put the meeting off 」(3)「彼女から鞄を奪う rob her of her bag 」(4)「彼に遅れずについてゆく keep up with him 」などがあげられます。
例文1;タンクにはガソリンがたくさんある。There is much gasoline in the tank.
例文2;タンクには(はじめから)なにもない There is nothing in the tank.
例文3;冷蔵庫には(はじめから)ミルクがない。There is no milk in the refrigerator.
例文4;タンクにはガソリンが少しもない。(前はあったのだが・・・) We have none of the gasoline in the tank.
例文5;タンクにはガソリンがほとんどない。(前はあったのだが・・・) We have little of the gasoline in the tank.
例文6;彼はめったに会議に行かない。 He rarely attends the meeting.
日本語での存在表現は「アル・イル」ですが、その否定形はそれぞれ「ナイ・イナイ」です。この中で興味深いのは存在詞としての「アル」には”否定専門”の「ナイ」があるということです。この「ナイ」はさらに使い方の幅を広げ、ついには存在のみならず一般の否定文に用いられることになりました。
でも、もとが動詞の一種であるところから日本語での慣例により常に<文末>に置かれることになります。このため日本語での否定表現は「それだけしか・・・ナイ」「どんな・・・ナイ」「だれも・・・ナイ」「どこにも・・・ナイ」「ほとんど・・・ナイ」などと他の言葉と組み合わせるにしても最後に「ナイ」が来るようになっていることがわかります。
英語では否定語の位置はさまざまです。なぜならばその品詞が副詞、形容詞、代名詞とさまざまだからです。例3は形容詞を使っています。例2,4,5は代名詞を使っています。形容詞 no, little なら名詞に直結、代名詞 none, little ならうしろに of をつけて名詞とつながることができます。以前から存在しなくて、タンクの中身が何であるか問題にならないときは同じ代名詞でもof のつかない nothing ( no one, nobody もこの系列)にします。
ここで重要なのは nothing / nobody / no one タイプと none の違いです。共に代名詞でありながら状況によりこまかい使い分けをしています。前者はタンクの中身がわからなくてもその存在だけが問題になる状況で用い、後者はすでにそこにある物質の名前を知っている場合です。
形容詞の no は no + thing によって一語になってしまいましたが、例3のように普通の名詞に結合してある物質の存在の有無だけを示すこともできます。しかしこれは上記の「すでに入れたはずの・・・」という背景はありません。単にその種類のものがあるかないかだけです。little も同様です。
副詞の場合は、<頻度>を表す rarely/seldom - never という系列や、<程度>を表す hardly / scarcely / little / barely *** などが否定語ですが、例6にあるように「一般動詞の前」「be 動詞のあと」などというように位置はだいたい決まっています。
注 *** barely 「かろうじて・・・」という意味のため、必ずしも否定的に用いられるわけではありません。
例文1;太郎は次郎より速く走る。Taro runs faster than Jiro.
例文2;次郎は太郎ほど速く走らない。Jiro doesn't run as fast as Taro.
例文3;古来、彼以上の建築家はいない。He is as great an architect as ever lived.
例文4;次郎は太郎より速く走らない。Jiro doesn't run faster than Taro.
例文5;風邪にかかっているのはひとりやふたりではない。More than one person has a cold.
例文6;日本で富士山ほど高い山は他に存在しない。No other mountain in Japan is higher / as high as Mt.Fuji.
例文7;日本で富士山は他のどんな山よりも高い。Mt.Fuji is higher than any other mountain in Japan.
西欧語では2者間の比較を表す場合、その手段となっている形容詞や副詞を特別な形、<比較級>に作りかえ、それに than のような接続詞を添えて比較する対象をつなぎます。英語の場合には、3者間の比較のために最上級の形まで用意してあります(ほかの西欧語では最上級の代わりに<冠詞・所有格+比較級>のようなちょっとした変形だけですましてしまう場合が多い)。
比較級は例1にあるように -er 語尾変化によって作ってみたり、 more を頭に追加したりするわけです。ところが日本語ではそのようなことはいっさいしません。ただ単に「・・・より」という助詞を比較対照の前につけるだけです。アジアの言語にはこのような方法が多く見受けられます。
例1では「太郎は速く走る」という文がもともとあって、そのあとで「次郎より」を挿入しただけです。ですから、「副詞か形容詞の前」というきまった位置さえ間違えなければよい。これは明らかに日本語のほうが簡便ですね。
例2は同等比較 as 原級 as の否定文、<不等比較>の例です。ここでは「・・・ほど」という助詞を用いています。これは程度をあらわしており、一見例1と同じことをいっているように見えますが、正確にいうと「同じ早さではない」と言っているだけで than がないのでどちらが早いかは明示されていません。ただ次郎の速度が太郎の速度に達していないことから、太郎のほうが早いだろうということになっています。
本来は例1と例2はきちんと区別しておくべきです。例3の言い方もよく気をつけてみると同等比較であり、直訳すれば「かつて生きていた建築家と比べ、誰にも劣らず偉大である」という意味になりますが実際は主語である彼が greatest であるという最上級の解釈に勝手に変えられています。
さらに例4では「次郎は太郎より早い」という事実をうち消しているわけですから、本当のところは、「太郎が次郎より早い」か又は「二人は同じ早さ」のどちらかだということを暗示しています。内容の解釈が重大な意味を持つときは、ここのところは慎重に扱うべきです。
また、例5での more than one とは「1人(つ)よりも多くて2,3,4・・・と続く」という表現です。ですから全体としては複数の意味なのに、one という名詞が”形容詞的”な more than によって修飾されているために単数扱いになってしまっています。日本語では「一人以上」というわけにもいかず、これも注意が必要です。
最後に、例6では比較対照の一方(多くは主語)がNo + 名詞であるために、実際には存在しないことを表しています。このことはこの世の中に自分に勝る競争相手がいないことを示しますから、自然と最上級の意味を持つようになります。この表現の原理は英語でも日本語でも似ていますが、すでに述べたように日本語では否定が文末にくるために大きく構造が異なっているように見えます。
例7の発想の中心は「比較級+ than any... 」にあります。これは肯定文で用いられる any が「どんな・・・も」というように、例外を認めないような言い方になっているためです。やはりこれも遠まわしな言い方ながら最上級の意味を示しています。
なお、英語では「2者間」と「3者以上」とでは表現形式が違い、比較とは前者に属するタイプであるために、いずれの例でも mountain は単数になっています。また比較対象「富士山」とそれ以外の「日本の山」というグループをはっきり分離するために other をつけていることにも注意する必要があります。このような厳密な区別は日本語では見あたりません。
例文1;ネズミたちは机の上や(机の)下を走り回っていた。The mice were running on and under the table.
例文2;我々はその仕事を成し遂げることができるし、成し遂げなければならない。We can and must finish the work.
単語や文を and / or / but などの接続詞で連結するとき、それをどのようにして効率的に表すでしょうか?一方が二つ以上のものに連結しているときには重複するものをわざわざ2度以上書くのは面倒です。このため英語などでは、例1,2の内容を表現するときに、最低限の語数で済むように仕組みが定着しました。日本語の場合にはそのようなシステムが考え出されていないというよりは、これまでそのような表現が使われなかったというべきでしょうか。
例1の日本語では「机の」が2回、例2では「成し遂げる」がそれぞれ2回繰り返されています。これに対し英語では table や finish が1回だけです。文の全般的傾向を観察すると、数式における展開した形< ab + ac >と、因数分解した形< a ( b + c ) >では、前者に近いのが日本語タイプであり、後者に近いのが英語をはじめとした西欧語タイプだといえます。
例1では共通の名詞 the table に対して前置詞 on と under が結合しています。工夫次第ではほかの言い方もできるのですが、日本語では共通構造が完全には確立していないため、「机の+名詞」を2回繰り返さなければなりません。省略して「机の上や下を」とは言えますが、使用する単語によっては誤解を生じるおそれがあります。
この傾向は例2のように英語での助動詞が共通の動詞原形と結びついているときにますます顕著に現れます。動詞部分を「そう」という、繰り返しをあらわす副詞的表現で言いかえて、「成し遂げることができ、そうしなければならない」とやるのは苦しいところでしょう。英語ではどんな品詞との結びつきでもこの<因数分解タイプ>が使えますので、日本語での表現の時は常にこの部分を誤解のないように表すよう意識しておいてもらいたいものです。
例文3;彼女はパリに有能な医者を雇う病院を設置し、多くの老人たちの世話をした。She started in Paris a hospital which employed able doctors, and took care of many old people.
英語で気をつけなければならないのは、and の使い道です。「赤と黒」のように A and B で A と B が and をはさんで直接向き合っているときは別に問題がありませんが、例1のように A と and との間にたくさんの語句や文がはさまっている場合、つまり A ..... , and B となっている場合は A と B が何を示しているのかを注意深く点検する必要があります。また、結びつくものがたとえば、5つあるのなら A, B, C, D and E というように、最後に来るものが and のあとにつきます。それ以外はコンマで結ばれます。
例2の and のすぐうしろにある B が took なのは当然だとしても、A にあたるものは動詞であり過去形であり、”主語が共通”であるという観点から employed ではなく started であることがわかります。and の前に打ってあるコンマも見逃せません。これらの特性をよく飲み込んでおかないととんでもない読み間違いをするかもしれません。仮にもし、employed とつながっているのだと示したければ、and と took の間に which を補う方法が考えられます。
日本語の場合には話し手や書き手の工夫の余地はあるにしても、誰でも使える普遍的なルールがまだ確立していないのです。ただ動詞は文末表現に含まれますから、それを目安に構造を把握する方法があります。学校の国語の時間では文学鑑賞ばかりしていないで、生活の中でのコミュニケーションで誤解を招かないような「正しい文の構造の研究」にもっと集中してもらいたいものです。
<共通構造>とならんで、英語などの西欧語では確立されていながら日本語では一部の翻訳者の文章センスに頼り切ってしまっているのが、<挿入構造>です。なるほど日本語の文章、たとえば新聞記事をいくら読んでも、例1の日本語訳に示したような挿入つきの文例を書く記者はどこにもいないようですし、敢えて書いたりすれば読みにくいという読者からのクレームが殺到するかもしれません。
英語での挿入の第1タイプは、その文の中の任意の単語(Aとする)と内容的に同じだと思われる語・句・節(Bとする)があってそれが隣接して置かれる場合をいいます。
例文1;子供たちが思春期に入ったとき、私たちは基本的なルールのひとつーよき親となることーを引き受けることを拒否してしまった。We have refused to accept one of the basic rules -- to be good parents -- when our children become adolescents.
例1では one of the basic rules = to be good parents であるということは英語を読む人にとっては挿入部分におけるダッシュ(ー)を見ればすぐ了解されるのに対し、日本語ではそのような構造は一般になじみがないために、読んですぐには理解されにくくなっています。
ではどうすればよいのか?翻訳者は英文から日本語文へ変えるときにできるだけもとの形を崩したくないという深層意識のためか、たいていは英語の挿入構造をそのまま日本語に移し替えているようです。そのため英語で使っていたハイフンをそのまま流用しています。これを思い切ってやめ、「だという・・・」」を使い、「子供たちが思春期に入ったときは、よき親となるべきだという基本的なルールがある。私たちはこれを引き受けることを拒否してしまった。」とまで文の構造を変え短文化してしまったほうが楽なようです。
英語での挿入の第2タイプは、たとえば文型 SVOC があったとすると、S * V * O * C のように * の位置に何らかの副詞(的表現)が前後の語順はそのままで入れ込むことです。ですからその挿入語句を取り払ったとしても文そのものの基本構造は変わりません。
例文2;しかしながら、この計画は金なしには実現できない。This project, however, cannot be realized without money.
例文3;思うに、この計画は実行が困難である。This plan is, I think, difficult to carry out. = I think that this plan is difficult to carry out.
例2での「しかしながら however 」は「それ故 therefore 」などと共に、英語では文と文の間の流れの交通整理をする副詞であって、本来ならば文頭にあってもよいのですが、この場合のように主語のあとであるとか、文末に置かれることが好まれます。接続詞ならば文頭になければならないところを筆者が比較的自由にその位置を選ぶことができます。
日本語ではいずれの場合でも、それらを先頭から移すとおかしく聞こえてしまいます。日本語は比較的語順が自由であると言われながら、文と文を結合する機能を持つ単語はあまり動きません(通常文頭)。無理に動かすと思わぬ誤解が生じることもあります。
例3での think は本来うしろに接続詞 that をつけて従属節を従え、文頭に主節として置かれるべきものですが、that を省略したついでに副詞的な要素に変化し、ここでは be動詞のあとに挿入されています。この場合、think の代わりに know, say, find などをいれてもうまくいきます。
この場合では日本語は別の言い方の工夫が可能です。本来の「・・・だと思う」というように動詞が最後に来る形式を捨てて、「思うに・・・、心に思っていることだが・・・、私の考えでは・・・」というように副詞的にするか、または主題化をはかることで文頭に持ってくる工夫が可能ですが、そう頻繁に使われる形式ではないので、使う人は多少の勇気を要します。同時通訳をする場合のように時間的制約があるときには必要な手段だといえましょう。
例文4:誰がこのかばんを盗んだと思いますか?Who do you think stole this bag? ←誰がこのかばんを盗みましたか。 Who stole this bag?
例文5;正直だと思っていた少女が私をだました A girl who I thought was honest deceived me. ←正直な少女が私をだました。 A girl who was honest deceived me.
例4は疑問文の中に do you think を加えたものです。これにより「あなたの考えるところを聞きたい」という気持ちが付加されますが、答えそのものが変わるわけではありません。そのため語順としては常に do you think よりも<疑問詞>が優先されて文頭につきます。このような場合に使う動詞は think だけでなく suppose, believe でも大丈夫ですし、場合によっては say でもよいでしょう。
例5は関係詞の直後に挿入節を加えたもの(連鎖節)です。これは例3と同じ流れをくむものですが、形容詞節の内容に関するものなのでこの位置しか考えられません。この場合、I thought があるのとないのとではずいぶん違ってきます。I thought があれば「正直」だということは私の思い込みに過ぎないが、I thought がないなら一応客観的事実だと認められるからです。こちらは think の代わりに know, believe, suppose, find など(つまりうしろに that節をつけることが可能な動詞)がいろいろ使えそうです。
最後にその違いをまとめてみると、対照的な3点が浮かび上がってきます(左が英語、右が日本語)。
(1)動詞の位置はSVO型に対してSOV型である
(2)前置詞+名詞、接続詞+文なのに対して、名詞+格助詞、文+接続助詞である
(3)語順厳守型、なのに対し、標識優先型である
このように何もかもが反対なので、学習者が苦労するのも無理もないのです。しかしこの違いを意識の中にとどめることによって、これからの英語、そしてその他の外国語の勉強をはるかに効率的に進めることができるのです。
HOME > 言語編 > 英語 > 日本語から英語へ > 04
© 西田茂博 NISHIDA shigehiro