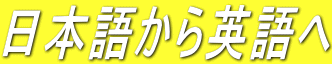第15章 発音と語彙
最後は音声です。言語は、そして語彙は音声なしには成立しませんでした。そもそも文字のない時代のほうが文字の使われる時代よりもはるかに長かったのですから。「まず音声ありき」です。
音素とは
新潟県地方で「越後」といえば、エチゴだけでなく、イチゴと聞こえる場合もあります。これはこの地域の方言での「越後」の最初の音が、普通の日本語の発音とは異なった形が日常生活で通じていることを意味します。この、「エ」と「イ」の中間のような音が、この地域での「越後」の発音では<音素>であるといわれます。
ここでの「エ」とか「イ」は<単音>と呼ばれるだけですが、人々の発音は年齢、性別、地域、体格によっていろいろ違ってきますので、「少なくともこの音であれば、この単語の意味であると認識される」とされた範囲内に収まる音のことを<音素>といっているわけです。
こうやってみると、逆に「辞書」と「自称」や、「京都」と「共闘」とで私たちが明らかに区別がついているということは、ショ sho とショウ shoo 、ト to とトウ too では音の長さが異なるというだけでなく、単語を判別する別個の音素であるということになります。英語でも同じことがあてはまります。たとえば ship と sheep には違う音素が含まれています。
また、外国語の辞書には必ず載っている、<万国音標文字>はたいへん便利な記号ではありますが、これは音素として使われている音の最大公約数の”モデル”にすぎず、絶えず揺れ動くものなので、唯一の正統で絶対的なものだとみなしてはいけません。
二重分節とは
たとえば、ku と i と ra の3つの音があった場合、この組み合わせはいくつになるでしょうか?カタカナ表記すると、「イラク、イクラ、クライ、クイラ、ライク、ラクイ」が生まれます。つまり、たった3つしか音がなくても6種類の組み合わせが生まれ、そのうち現代日本では少なくともイラク、イクラ、クライ、ライクの4つは意味が通じる単語として扱われています。
これは見事としかいようのないことで、何の意味のない音素(第二次文節)が結びつくと、ひとつのまとまった意味(第1次文節)をつくることができるわけです。これが人類の使える単語数が増加した秘密です。上記の場合ですと、クイラとラクイは今のところ空席で、まだ使い道がありませんが、将来何か適当なものごとに命名されるチャンスが残されているわけです。
同時性を持つ視覚と異なり、聴覚は時間の流れに沿って一方通行でしか伝わりません。この状況でわずかな音素を使い無限に近い単語を作り出すことができる言語の特徴を<二重分節性>といっていますが、このような観点からすると、発音の研究は単語を作る”ブロック”の研究であり、特に外国語を学習する場合にはまさに基礎をなす部分になっています。
五十音表を頭に思い浮かべてみましょう。誰でも知っているとおり、アイウエオからはじまっています。a i u e o という5つの母音だけです。しゃべったりするときはこの音がいろいろ変形したりはしますが、とりあえず日本語では5つしか母音がないことになっています。この配列は歴史的に決まったものでしょうが、動かす舌の位置を<前舌、中舌、後舌>の順番に発音してみると、i e a o u となります。こうやって発音してみると、舌の「位置」と「高さ」が母音の種類を決めていることがよくわかるでしょう。
また、五十音といいながら、実際に数えてみると45しかありません(オとヲをひとつに数えた場合)。これは長い歴史の間に、ほかの母音が消えうせたか、合併して一つになってしまったせいです。母音の数がこれしかないということは、子音の少なさも手伝って<同音異義語>を大量に作り出しました。(後述)
子音はどうでしょうか?カサタナハマヤラワですから、全部で9種類あるかのように見えますが、ローマ字で書くと、実はさらにもっといろいろなタイプがあることがみえてきます。単語の判別に必要だという観点からぎりぎりに絞ると、19個というところです。
私たちは「カ行」といえば ka ki ku ke ko で子音は「 k 」音だけですね。ところが「サ行」はどうでしょう?日本語には「 r 」「 l 」の音どちらも存在するのだろうか?「 f 」「 h 」との音の違いは?つまる音(促音そくおん)とは?小さなカタカナ・ひらがな(拗音ようおん)とは?「ka 」の音はあっても「 k 」だけの音なんてあるんだろうか?日本語の音は意外に複雑な世界なのです。
例1; a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi hu he ho ma mi mu me mo ya yu yo ra ri ru re ro wa
|
五十音表 |
||||
|
a |
i |
u |
e |
o |
|
ka |
ki |
ku |
ke |
ko |
|
sa |
shi |
su |
se |
so |
|
ta |
chi |
tsu |
te |
to |
|
na |
ni |
nu |
ne |
no |
|
ha |
hi |
hu |
he |
ho |
|
ma |
mi |
mu |
me |
mo |
|
ya |
*** |
yu |
*** |
yo |
|
wa |
*** |
*** |
*** |
|
(1)清音
ヘボン(Hepburn)氏をはじめとして、多くの人々が日本語の音になるべく近い表記方法を工夫してきました。その結果、かなりの部分のつづりが変化しています。そしてそれでも今でも十分ではなく、たとえば「東京」は tokyo と書かれていますが、誰でもが認める共通の伸ばす音(長音)の記号がないために、実は「トキョ」になってしまっています。また「富士」は fuji と書かれていますがそれで正しいのでしょうか?
例1の五十音表を見るとわかるようにサ行では「スィ si 」ではなく「シ shi 」が、タ行では「ティ ti 」ではなく「チ chi 」、「トゥ tu 」ではなく「ツ tsu 」が他と違っています。このようにローマ字表記が異なったのは、これらの舌の位置が同じ母音の他の音とは少し違っているからです(音声学による区分)。つまり同じ子音が集まっているはずの行(ぎょう)の中には異なる音が紛れ込んでいたわけです。
同様にして、ハ行の hi と hu も厳密にいえばあとの3つとは異なります。そしてこのハ行というのは本来、 f 音ではないということです。つまり、「ハハハ・・・」と笑うときの音に近いのであって、英語のときのように上の前歯で下唇をこするときの音ではないし、唇をすぼめ気味にする what に含まれる音でもないのです。
さらにラ行ではすべて r であり l で書かれてありません。これはもしかして個人差があり、単語によっても l だったり(たとえばプリンやライス)、 r だったり(たとえばラブ=愛)することがあるかもしれません。早くいえば日本人は r と l の音の違いなど気にかけてはいないのです。
そしてどの組合せも必ず「母音( vowel )単独」か「子音(consonant)+母音」の組合せになっています。つまり、<V 構造>か<CV 構造>になっています。理屈の上では日本語にはCだけの音はあり得ません。常に母音がついてしまうのです。ということはたとえば、 strike という英語をカタカナ表記すると、どうしても「ストライキ sutoraiki 」か「ストライク sutoraiku 」になってしまうのです。
例2; ga gi gu ge go za ji zu ze zo da ji zu de do ba bi bu be bo pa pi pu pe po
|
濁音一覧 |
||||
|
ga |
gi |
gu |
ge |
go |
|
za |
ji |
zu |
ze |
zo |
|
da |
ji |
zu |
de |
do |
|
ba |
bi |
bu |
be |
bo |
|
pa |
pi |
pu |
pe |
po |
12.0pt;mso-bidi-
(2)濁音・半濁音
濁音はどうでしょうか。濁音とは、無声音(清音)に対する有声音の行です。ここでは k-g s-z t-d の3組が生じています。なお、ザ行の ji zu とダ行の ji zu は同じ音と考えて差し支えないでしょう。z の音は前歯の付け根近くで発せられるのに対し、j の音はもっと奥のほうで発せられています。ji を無理に zi にしますと「ズィ」となってしまい、これまで日本語にはなかった音です。
またローマ字表記によって気づくことは、実は p-b も無声音と有声音のペアですが、前者がハ行の半濁音、後者がハ行の濁音と呼ばれているわけです。不思議なことに、ハ行での子音は h ですが、これは b とも p ともまるで縁のない音であるということです。しかも、平安時代あたりでは「ハ行」が fa fi fu fe fo と発音されていたという説もあり、このへんの音はだいぶ流動的なようです。
(3)拗音(ようおん)・撥音(はつおん)
例3; kya kyu kyo sha shu sho cha chu cho nya nyu nyo mya myu myo rya ryu ryo gya gyu gyo jya jyu jyo hya hyu hyo pya pyu pyo
|
拗音一覧表 |
||
|
kya |
kyu |
kyo |
|
sha |
shu |
sho |
|
cha |
chu |
cho |
|
nya |
nyu |
nyo |
|
mya |
myu |
myo |
|
rya |
ryu |
ryo |
|
gya |
gyu |
gyo |
|
jya |
jyu |
jyo |
|
hya |
hyu |
hyo |
|
pya |
pyu |
pyo |
拗音は漢語(つまり中国語)をなるべく原語に近く発音するために工夫されたようです。拗音では、もとになったカ行、サ行、タ行とはだいぶ違う音が入ってきて、ローマ字表記も一工夫必要です。拗音表記のほとんどが y つまり半母音(またはみじかい i )をはさんでいます。
しかし sha shu sho cha chu cho にはその音が入っていないのです。これはなぜでしょうか。「会社」をカイシィヤとは言わないでしょう。y の音は飛ばされてしまっているのです。日本語では半母音として、この y と 「ワ」を表す w の二つが使われています。
撥音は古代にはない音でした。「ン」で表されていますが、必ずしも n の音ではなく、前後にくる音によって口の形はいろいろ変わります。ただ常に鼻から空気を抜く<鼻音(びおん)>ですので、口からの空気は遮断されて鼻の中だけを空気が流れます。「井戸 ido 」と「インド indo 」のように、これがなければ単語の区別ができませんから、きわめて重要な音素になっています。
(4)促音(そくおん)と長音(ちょうおん)
促音は「ッ」で表されています。撥音と同様、古代には存在しませんでした。「位置 ichi 」「一致 icchi 」でわかるように、「ッ」の前の音でいったん立ち止まることによってちょっと時間をかけ、区別をするわけです。”詰まる音”ともよばれ、お隣の朝鮮半島の言語でも、「濃音(のうおん)」という名で似たものがあります。あちらでは濃厚に発音するという感覚でしょう。これは朝鮮半島からの語彙の流入と関係があるかもしれません。
母音から次の子音に移るときに、口腔内に空気を溜め込むために口内の圧力が瞬時に上がり、この子音が強く発音されることになります。このため子音字(「icchi 」の場合は c )が二つ重ねて表記されるわけです。
長音はなぜかローマ字表記ではあまり重要視されていません。すでに述べたように tokyo とは本当は「トキョ」なのに、誰もが「トーキョー」とのばすことを疑いません。tookyoo とか toukyou のように書いたほうが正確なのです。 伸ばすべき母音 の上に記号( ¨ など)をつけるなど、何らかの形で表記を統一してほしいのですが、今のところ誰もそんなことを始める気配もありません。
まったく別の単語が数多く生じることから、普通の短い音と、長音では”別の音”であると考えるべきでしょう。「時 toki 」、「陶器 tooki 」というように、長音はこんなに重要な単語判別の役割を果たしているのですから、英語の「短い i 」と「長い i 」のように、たがいにまったく別の音であるとしてその地位を引き上げてやらなければなりません。
なお、長音のひらがな表記では、「おかさん」から「おかあさん」というように、直前の文字(ここではカ)に含まれる母音をつけるのが基本になっています。さらに気になるのは、「通り(とおり)」と「党利(とうり)」の違いです。どちらも発音は同じはずなのに、前者は歴史的な仮名遣いの流れから「オ」を使っています。数から言えば「ウ」を使うのが大多数です。ですから、「ときょ」を長音化した場合には、「とおきょお」か、「とうきょう」か、いちいち覚えなければなりません。一部の若者が「とーきょー」と書く気持ちもわかります。これは(年配の人からすると)見栄えは悪いが、統一しやすい書き方だとはいえます。
<参考>拍数について
外国人の中には会話中の日本語を聞くと、まるで機関銃を撃っているようだと言う人もいます。これは日本語が CV 構造であり、それぞれの組が同じ長さで発音されるためでしょう。一つの組は1拍と呼ばれます。たとえば katakana は4拍の単語です。aiueo の母音だけでもそれぞれ1拍です。そして気をつけなければならないのは、撥音、促音、拗音、長音いずれも1拍に数えられることです。ですから「インド indo 」は3拍、「一致 icchi 」も3拍、「彼女 kanojyo 」も3拍、「東京 tookyoo 」は4拍となります。
(5)アクセント
さらにアクセントですが、英語のように<強弱アクセント>にすると、強い部分がやや長く発音されます。拍数を守って同じ間隔にしたいという無意識の願望があるのかどうか、それとも中国語の影響があるのか、日本語では音の長さにあまり変化の起こらない<高低アクセント>が使われています。たとえば、下着の「パンツ」は「パ」が高くなり、ズボンの一種である「パンツ」は「ンツ」が高くなるようです。
もとから同音異義語が多いことでいろいろ不便をきたしている日本語の単語ですが、このようなアクセントがきちんと定着すれば、単語間の判別も楽になるでしょう。ただし今のところ、中国における北京語の<四声>のように辞書でしっかりと定まっているのと違い、日本語のアクセント位置は地方により、世代により、個人によりつねに”ゆれて”います。あなたは「橋」「端」「箸」における”標準”アクセントの違いを正確にいう自信がありますか?もっとも、同音異義語が減ると、”ダジャレ”の楽しみも減りますが。
(6)母音調和と子音調和
「酒屋」は「サケヤ sakeya 」ではなく、「サカヤ sakaya 」と発音します。これはなぜでしょうか?最後の音に付属する母音が a であるために、 e-a と発音するより、 a-a と続けて同じ(タイプの)母音のほうが発音するのに楽だということで平安時代のころに発生したものと思われます。こうすれば母音を発音するときにあまり大きく口を動かさなくてもすむわけです。
この現象が最近まで存在してきたということは、これが発音のなめらかさを求める無視できない傾向、つまり<母音調和>が行われていることを表しています。風が強かったり、厳寒だったりする気候の中で、なるべく口を動かしたくないという不精さがこんな言い方を生んだのかもしれません。
また、過去や完了を示すときには「タ形」を用いますが、これも「書く kaku →書いた kaita 」となるのに、「読む yomu →読んだ yonda 」となり、「読んた yonta 」とならないのはなぜでしょう。つまり ta が da となってしまう現象です。これは「一軒 ikken 」なのに「三軒 sangen 」となるのも同じです。これらの例では前が n のように<鼻音>の場合には、そのうしろも有声音が続いたほうが発音しやすいのです。こちらは<子音調和>といわれています。
これらの調和現象は古代の日本語では盛んに使われていたようですが、現在では名詞を中心にしてごく少数にとどまっています。それでも発音のしやすさから日常生活の中に目立たないながら根を下ろしているのです。奇妙なことにトルコ語でもこの現象があり、それが現代語にも立派に残っています。もしかしたら、トルコ語と日本語は遠い昔にどこかで分かれたのでしょうか?
(7)音便
母音調和と子音調和よりもさらに有名なのが、<音便>による発音の変化です。これはその大部分が古代の言葉から、平安末期の言い回しに変わるときに伴って現れたものです。かつて「書キテ kakite 」だったのが、「書イテ kaite 」となり(イ音便)、「ヨク yoku 」を「ヨウ you 」といったり(ウ音便)、「読ミテ yomite 」だったのが「読ンデ yonde 」となったり(撥音便)、「言ヒテ iite 」が「言ッテ itte 」となったりしました(促音便)。
この4種類の音便については、大部分が動詞の<テ形>にともなうものです。動詞のところでも述べたようにテ形は非常に応用範囲が広いので、ひんぱんに会話の中に登場するため、滑らかで楽な言い方が自然に工夫されたのでしょう。このためテ形のつくりかたは規則的でなく、学習者泣かせなのです。
英語の母音
さて、英語の場合は母音の数はいくつぐらいあるでしょうか?代表的な辞書によれば、全部で8から16種類です。その内訳は<短母音>が9個。この中には「ネコ cat 」の a 音と「オーブン oven 」の o 音を含む「ア」タイプが含まれ、<あいまい母音>で知られる e を逆さまにした記号も入っています。
6個ある<長母音>は短母音のいくつかを延ばしただけなのですが、一人前に独立した単音ということになっています。さらに二つの短母音か、短母音と半母音を組み合わせた<二重母音>と呼ばれるものが9個あります。
しかし、すでに<音素>のところで述べたように、音声学ではなく、単語の判別に使うだけならば、もっと絞り込んで母音の数は10個ぐらいでも十分だといえます。それでも、日本語の母音はたった5個しかないのですから、新たに少なくとも5個増え、学習者にとって英語の「リスニング」がたいへんなのもうなずけます。これまではどれもみな同じ「ア」だったのが、cat / cut / curd というように、今度は最低3つの「ア」の区別をする訓練をしなければなりません。
英語の子音
子音の数もしぼって24個。日本人にとってやっかいなのは「これ this 」の音に含まれる上下の前歯で舌をはさむ th 音(無声音・有声音の両方あり)が筆頭にあげられます。下唇と上の前歯をこすって出す、 f 音と v 音も要注意です。なぜならすでに述べたように現代日本語の「ハヒフヘホ」は f の音が一つも含まれておらず、のどの奥と唇だけを使って出す音だからです。
また、サ行の「シ shi 」は「si 」ではありません。たとえば「海」は「シー」といっていますが、これを英語では「スィー」に改めなければなりません。タ行の「チ chi 」音も同様です。「ティ ti 」音を練習しなければなりません。もっとも最近ではこの音が入っている「teacher 」や「tissue 」を正しく発音している人も増えました。ほかにはダ行の「ジ ji 」があり、「ディ di 」音や「ズィ zi 」音と区別する必要があります。
英語ではCV構造の他に、V だけなのはもちろん、C だけやCC, CCC などもあります。つまり途中に母音がはさまらずに子音が立て続けに発音される場合もあるのです。「指導者 instructor 」では -nstr- の4つの子音字が連続しており、間には一つも母音がはさまっていません。これに対して、日本語では aiueo 以外は必ず子音のあとに母音が連なりますから、英語の machine も母音の聞こえ方によって「マシン mashin 」と「ミシン mishin 」の二通りができてしまうのです。
英語の変化音
これだけたくさんの母音と子音を組み合わせるのですから英語の単語の音は当然ながら複雑なのです。組み合わせの数が多いため同音異義語も少ない。しかもアクセント(強弱アクセント)の位置が規則的でなく単語によってバラバラなのですから、いよいよもってリスニングが難しくなるように思われます。
ゆっくり発音すればたくさんの種類の音に出会いますが、実は早口でしゃべるとアクセントがおかれている母音ははっきりと発音されるが、それ以外の母音はぼやけてしまい、子音だけが連なるように聞こえます。ですから人名の Hepburn は本来アクセントが前にあるため、この音に忠実なカタカナ表記では、ローマ字表示で有名な「ヘボン」とかかれます。ところが日本式の発音ではアクセントが勝手にうしろへいってしまい、あの女優の「ヘップバーン」となってしまいます。
また milk はゆっくりと発音すればそれぞれの母音と子音がちゃんと聞こえますが、実際の会話ではもっとスピードアップしますから、まるで「メウク」と言っているように聞こえます。i と l の音はどこかに行ってしまったように思われ、その代わりにわけのわからない母音、いわゆる「あいまい母音」がおさまってしまうのです。でもそれが英語音の実態であり、water を「ワラー」、American を「メリケン」と聞いた明治時代の諸先輩は、聞こえてくる音を日本式の子音+母音を入れないで、かなり素直に聞き取っていたのかもしれません。
母音があいまいになり、単語の長さが長くなればメリハリをつけるためにアクセントのある音だけは明瞭に発音されればよろしい。たとえば economics では真ん中の -no- に力を入れて発音すれば聞き手はちゃんとわかります。極端な話、cnomcs といっても何とか通じるわけです。ところが日本式にいちいち母音をつけて ekonoomikkusu とやったりするととたんに通じなくなったりする。
このように英語では早口になると、辞書に書いてある発音記号ではない変化が起こりますが、ある程度の規則性がありますからこの変化のしかたをしっかり身につけておく必要があります。実は日本語でも文頭になったり、早口になったりするとやはり音の変化は起こっているのですがそれほど顕著ではありません。
英語でも日本語でもこのようにしていくつかの音素が組み合わさって語彙ができてきました。単語覚えが外国語学習者にとって共通の悩みなのは、いうまでもなく各国語における語彙のつくりがきわめて恣意(しい)的だということにあります。
なんで、人に忠実でオオカミが祖先だといわれている四足の生き物が「inu 」とか「dog 」と呼ばれるようになったのか、知るよしもありません。たとえその語源が明らかになっても自分の母語からすればまるで縁のない音であり、単語を記憶する苦労は特に軽減されるわけでもありません。
生物の進化は太古の昔にその起源をさかのぼることができます。たとえば、われわれの尾てい骨にある痕跡らしきものは、われわれの祖先がシッポを持っていたことを示すといわれています。人間を含む脊椎動物の胎児の最初の形は魚にそっくりです。言語も、長い時間にわたって進化してきたものだと想像されますが、叫び声とか物音とか、自然界の音ぐらいしか語彙を作るヒントになるものがなかったのですから、まさに人は無から突如、有を作らなければならなかったのです。
日本語では、漢語が流入する前の言葉は、「やまとことば」と言われています。根本的な文法構造はもちろんのこと、今でも漢字の訓読みの中に生きていますが、中国語の音と比べると柔らかな響きが多いようです。しかし、日本列島で話されていた語彙数が不足していたため、たちまちのうちに大陸系のことばが押し寄せてきました。
現代日本語というのは、古来の文法構造をもとにして大陸系の語彙を加えたもので、遣隋使の時代から明治の学者に至るまで、さまざまな努力があって豊富な語彙を得てきました。日本では外国の有名な書物がすぐに翻訳出版されますが、これには翻訳を円滑に行うことのできる語彙のストックが十分にあるからです。
最近ではカタカナことばに頼ることが多いけれども、ついこの間まで自前の単語を創造して需要にこたえていたのでした。語学の学習にとってはマイナスかもしれないが、大学で英語による専門科目の授業が極めて少ないのはそのせいでもあるわけです。
ところで、「走る、歩く、寝る」などに対して、「・・・スル」という形の動詞がなんと多いことでしょうか。これはどんどん増える動詞の需要に対して製造が追いつかず、漢語のみを名詞に、これに「スル」をつけることによって動詞化するという方法がすっかり定着してしまっていることを示します。前者は古来使われてきた日常的なことば、これに対して後者には役所や学問の場で使うような公式なことばが多いのもこのような生成過程のためだと思われます。
動詞のほうはこのようにして、できあがっていきました。形容詞や副詞はあまり漢語の影響を受けることがなく、意味は変化することがあっても、古来の形をよく残しています。ただすでにこれまで述べてきたように、動詞と形容詞は、<活用形>をしっかり覚えていれば次々とほかの単語に接続できるわけです。また、格助詞と接続助詞を中心とする文作りの方法があるために、名詞についても、この点では扱いやすいものでした。
すでに述べたように、語尾変化の複雑な言語、または後置詞が発達した言語においては、語順が比較的自由なだけでなく、品詞の判別も楽です。こうやって見ると、日本語の語彙は副詞を除いてそれぞれ決まった活用があるおかげで、うしろにくる単語と見事な結びつきを作ることができるのが特徴です。このためある語についている”標識”さえ読み取ることができれば、その後の文中の文法的な位置や意味をすばやく知ることができるのです。
英語の語彙は、これとはまったく別な歴史的背景のもとに育ちました。よく言われているように、英語はゲルマン系の言語と、ラテン系の言語の双方から影響を受け、そのあと自らの文法規則を著しく簡略化して、語順に重きをおく言語に変身してきました。
このため、ひとつの語彙をさまざまな品詞に使い分けることが可能です。たしかに、-ful をつければ形容詞になるとか、-ly がついていれば副詞の可能性が高い、というように接頭辞や接尾辞によって品詞を判定することも十分できます。しかし、興味深いことに hand とか interest というような語が、動詞の前か後につけば名詞(つまり、主語目的語補語のどれか)だが、名詞の前かうしろについていれば動詞になる現象を見ると、品詞の設定がいかに語順に支配されているかがわかります。
このことは辞書を読んでみるとよくわかります。”重要語”といわれるような単語を引いてみると、動詞と名詞の形が同じ例が実にたくさん見つかります。present という単語はさらにその上に形容詞まであります。語源的には異なっていてもつづりがまったく同じですから、動詞のあとのed形とか、名詞の複数語尾のことがなければただ見ただけではどの品詞かわかりません。
だが、これらの単語がいったん文中に入ってしまえば、たちどころにわかる(イヤ、わからなければならない)のです。ただ、音声の場合には一回で品詞を判断することのできない危険性もありますから、それぞれ異なったアクセント位置が与えられています。長い間に蓄積された語彙判定の知恵はただ感心するばかりです。
*語彙数
最後に、それぞれいくつの語彙を覚えれば日常生活の大体をまかなう(つまり必要事項の80%ぐらい)ことができるのでしょうか?英語の語彙数は今までに主パンされた大辞典を見るとわかるようにきわめて膨大ですが、このレベルならば、1000語も覚えれば十分なのです。ところが日本語の場合にはこのレベルを達成するには5000語を覚える必要があります。
英語は国際言語として用いられるようになってから、ひとつの単語がたくさんの意味をかねるようになったことがこの原因だと思われます。一方日本語は国際化していないために、独自の文化に基づく多様な語彙が存在しているためです。
どちらが優れているかという問題ではなく、広域言語と、地域限定言語としての違いが現れているようです。考え方や文化的背景の違う人々が交流するときは、少なくとも最初の段階では学習の容易さとあまり深く切り込まないレベルでの会話が行われます。一方、地元の生まれも育ちもよく似た人同士の会話では、共通部分が多く、それだけ内容を深く掘り下げることができるために、いろいろな語彙を持ち出す可能性が大きくなるわけです。
いかがでしたか?外国語学習はまず覚えることだとよく言われますが、その前にまず理解なくしてどうして前へ進む気が起こるでしょうか?なるほど、語彙や成句は相手の言語で恣意(しい)的に生まれたもの。これは確かに記憶力がものをいいます。しかし、昔から「言語センス」などといわれていたものは、いったいなんだったのか?誰も明確な説明をしないまま、「私は外国語が向かない」と思いながら学習をあきらめていった人々がなんと多くいたことでしょう。わけもわからずがむしゃらに勉強を続けることは苦痛でもあり、結局は放棄につながるのです。
私はいくつかの言語を研究して安心しました。動詞、形容詞、副詞、名詞など、基本的な品詞はどの言語にも存在します。つまり、それらの間には本質的な違いはなく、こまごまとした文法的な規則さえモノにすればどんな言語でも人間にとって学習不能なものはないということです。本書では日本語と英語の間に限って話を進めましたが、実は他の言語においても学習効率を促進することが可能なのです。
今皆さんは本書を読み終えて、英語と日本語は確かに違いの点で大きいが、乗り越えることのできない壁でないことに気づいたと思います。そして何よりも母語である日本語をしゃべるときに、今までよりもずっと“意識的”になっているのです。マラソンを目指す人がコーチに教えられて、自分のフォームやペースを意識するようになり、ぐんと記録が向上します。同じことが言語の学習にもいえるのです。
© 西田茂博 NISHIDA shigehiro