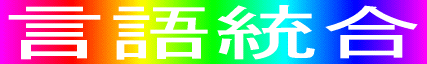
言語の共通部分を探る小論集
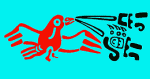
ここでの言語統合とは、エスペラントのような人工的な世界共通語を作ることではなく、遠い将来にもし人類が生存していたならば、ひとりでにでき上がってしまっているであろう自然言語のことである。
その言語がどのような形になるかを予想することがこのコーナーのテーマである。なぜそのようなことに取り組むかといえば、実は現在の人類によって使われている言語の共通部分が当然、将来の言語に直結するからだ。
したがって比較言語学における各言語間の「相違」に注目して研究を進めるのとは違って、できるだけ多くの「共通点」を見いだすことに主眼を置きたい。その共通点を集めて、人間の言語の、従来の文法では見えてこなかった構造を明らかにするのである。
そのためには各言語について多くのことを知っていなければならないが、ただ一つの言語を知るのと違って、途方もない困難な作業である。にもかかわらずこの仕事が魅力的なのは、人類がどうして言語を発明したのか、サルたちとどういう点が違っているがために、このようなコミュニケーションを可能にしたのか、という謎も同時に解けそうだからである。
よくよく考えてみれば、人類が発生した当時、言語はただひとつで「統合」されていたのである。それが交通機関の存在しない先史時代の世界中いたるところに人類が広がり、お互いの行き来ができなくなった時点で言語がいくつにも分かれてしまったのだ(バベリズム)。そして20世紀におけるこの情報社会の到来で、人類は再び100万年前と同じ状況に戻ることができたといっていい。
仮に地球がもっと小さくてお互いの行き来が自由にできたのであれば、今でも世界は一つの単一の言語で(少々の方言はあっても)続いていたことだろう。その言語は今人類が使っているすべての言語と共通点を持ち、人間思考の謎、つまり脳内で「発声」している言語がどのように思考を形成するかの謎にも迫れるというわけだ
だからこの問題は古くて新しく、はなはだ大きすぎるスケールでありながら、実に魅力的なテーマだといえる。それでは実際に各論について考察してみよう。
人類が発生したときに、最初は言語が一つであったかどうかについて走る由もない。タイムマシンでも発明されない限り、最初は文字を持っていなかったことから、いかにがんぱっても当時の状況を再現することはできないである。
ただ、語源的なものを取り扱ってみると、さまざまなロマンが生まれてくる。その中には言語学的には何ら証明されておらず、類推の域を越えないものの、それでいて人々の関心を引きつけてやまないものがいくつかある。
私の高校時代はヨット部に所属していて、小さな漁港の片隅を借りて、セーリングの練習をしていた。昔の漁船は木造で木と木の継ぎ目から水が漏れやすい。これはじわじわと漏れてくるもので、船底にたまってゆく。古い船ほど、嵐にもまれた船ほどその漏りかたは激しいものだが、それを彼らは「あか」と呼んでいた。「そら!漏れてきたぞ、あかを汲め!」と新米の漁船員たちは怒鳴られたのだ。これは漢字で「淦」と書く。
さらに広辞苑を拾ってみると、同じく「あか(閼伽)」というのがあって、これは貴賓、または仏前に供えるもの、それも特に”水”をさす仏教用語である。仏教用語の多くは梵語からきている。
 さて、フランスのジャック・イブ・クストーといえば、世界的な海洋探検家で、カリプソ号で世界中を回り、自分の発明した潜水器具「アクア・ラング」でそれまで未知の世界だった海底を世界中に紹介したことで名高い。アクアはフランス語やスペイン語などのラテン系の言葉だ。英語でも
aquaduct のような連語として生きている。
さて、フランスのジャック・イブ・クストーといえば、世界的な海洋探検家で、カリプソ号で世界中を回り、自分の発明した潜水器具「アクア・ラング」でそれまで未知の世界だった海底を世界中に紹介したことで名高い。アクアはフランス語やスペイン語などのラテン系の言葉だ。英語でも
aquaduct のような連語として生きている。
さて、この「あか」と「アクア」との関係だが、いずれも「水」に関係する音なのである。これをそれぞれ、発生源をたどってゆくと、「アクア」はヨーロッパを出て、中東そしてさらに東へ、「あか」は沖縄方面へへ南下してインドシナ半島の方へ、そしてさらに西へとたどることができるそうだ。
そしてこの「aqua-, aka- 」という音は最終的に、どうやらインドの古代語であるサンスクリットから来たらしいのである。文明の伝播と共に広がった言葉は、いつの間にか地球を半周してしまった。ことばの響きは根強いところがある。どんな言語の中に入り込んでもその持つ意味が強烈で日常にかかわっているときはその特徴を失わないものなのだ。
最近中国語を勉強していたら、「ブドウ酒」のことを「プータオ・チュウ」というのだという。音が似ている。さらにギリシャ語では「ブトロス botrus」と呼んでいる。この三つの発音も、もしかしたらラクダの背にのって、シルクロードをはるばる東進してきたものなのだろうか。
2010年7月最終校訂比較言語学では、音韻、文法、語彙、すべてにわたって仔細に検討し、言語間の縁戚関係を調べる。だが、発音や語彙は、「 American 」が「メリケン(粉)」「 machine 」が「ミシン」となってしまうように、実に気まぐれで突拍子もない変化を遂げる。だから偶然に「あか」と「アクア」が現代に残っていたとはいえ、そのような不安定なもので言語の変遷をたどるのは危険きわまる。
フランス語とスペイン語のように非常に多くの日常語が共通であるならば、その近い関係を断言することもできようが、占領、征服、駆逐、貿易、断絶、孤立、鎖国、災害といった数限りない歴史的要素が入っているのが人類の歴史だから、単語の類似性に頼ることは実に心許ないのである。
もっと長い時代において変化しないもの。それは文法である。単語なら、気の利いた詩人や歌人が一晩のうちに作り出したり流行遅れにすることはできるが、規則を勝手に変えることは、直ちにコミュニケーションの停止につながる。ましてや長い時間をかけて編み出された文法規則は、妥協と試行錯誤の産物だから、そう簡単に変わるわけがないのである。
「アイはユーが好きよ」といっても、しっかりと日本語文法が守られているではないか。極論すれば語彙を無視してもルールさえ共通であれば言語の近似性を断言してもいいのではないか。文法の共通事項を少しずつ収集していけば、大きな体系ができあがるかもしれないのだ。
日本語には現在形と過去形の違いはない。英語にはある。フランス語にもドイツ語にもスペイン語にも該当するものがある。日本語には定冠詞というものがない。なくても平気なのだ。「本が高価だ」という代わりに「本は高価だ」といえば、状況にもよるが定冠詞の役割の一部をつとめている。
 文法体系の違いを比較すれば、それぞれの文法のできあがった経緯を想像することができ、それを使用した民族が情緒的であるとか論理的であるとか、大ざっぱなのか几帳面なのかもわかるかもしれない。
文法体系の違いを比較すれば、それぞれの文法のできあがった経緯を想像することができ、それを使用した民族が情緒的であるとか論理的であるとか、大ざっぱなのか几帳面なのかもわかるかもしれない。
世界には数千とも数万とも言語が存在するが、そのうちのいくつかのグループはかなりの文法的類似性があることがわかっている。人類がアフリカにいた、ただ一人の女から発生したということが正しいとすると、現在の言語もただ一つの言語から発生し、今日のような多様性を帯びたわけだから、その系統樹を研究し、どうして文法上の変異が生まれてしまったかの謎を解くことは大いに興味をそそられるではないか。
***なお、参考までに各国語を比較する際に有効な6種の具体的な文法カテゴリーをあげておこう。***
| テンス | いわゆる時制である。ふつうは現在、過去、未来の三種をもとに文章の述べられている時点を示す。もっとも、きっちりとこの三種が区別されている言語はむしろ少ない。日本語のように現在と未来が混じってしまっていたり、中国語のようにもともと明確な時制を示す印のないものが多い。 |
| アスペクト | テンスとははっきり区別されなければならない。これはたとえば、一つの動詞「眠る」がいったいそのどの局面にいるかを示すための表現である。「眠り始める」「眠っているところ」「眠ったまま」「眠り終わった」「眠ってしまった」などたくさん考えられる。それを示すために、ほかの動詞を結合するやら、助動詞やら、補助動詞やら、特別な語尾やらをつけることによって各国語は苦労しているが、その中でももっとも有名な区別は「完了」と「不完了」であろう。つまり「眠り終わった」のか「まだ眠り終わっていない」のかの区別である。これが実生活では最も重要なものらしい。 |
| 肯定否定 | 言うまでもなく、イエスとノーの区別がなければ、日常生活は立ちゆかない。否定を示す記号や形式はいろいろあるが、不思議と「 n 」の音が入る場合が多いのはなぜだろう。 |
| ていねいさ | 日本語や朝鮮語のように、ふつうの表現のほかに、「ていねい体」があり、さらに尊敬や謙譲を表す表現も数多く見受けられる。英語の場合、一見ていねい体なんかないように見えるが、Sir とか Please のような表現を通じて、その文の表現を変えているのだ。どこの国の言語でも、「よそゆき」の表現は必ずある。 |
| ヴォイス | いわゆる、態であり、「能動態」「受動態」の二つがあるが、これに「使役」を加えてもよい。これらの特徴は、主語に置くものを変化させることによって、その文の「焦点」をかえることにある。 |
| モダリティー | 話し手の気持ちである。「断定」「推量」などが有名であるが、英語などでは、これを助動詞によって表現している。日本語でも「・・・だった」という代わりに「・・・したようだ」というように言い換えてその気分を表している。 |
アルタイ文法なんて今までだれも口にしていないし、実現させようという努力ももちろん聞いたことがない。これはわたしの発案である。トルコ人は、あの巨大な帝国を作って東へ勢力を伸ばし、ついに中国のシンチャン・ウイグル地区にまで達した。彼らの子孫たちは、その間に散らばっている。
モンゴル人もジンギス・カンの帝国をはじめとして、勢力を東へ伸ばし、ハンガリー近くまで達した。このためその子孫たちもその間に散らばっている。ほかに太古の昔、チベット、朝鮮、日本へと人々が散らばった。しかし何と言っても長時間にわたってユーラシア大陸に大きな影響を与えたのはトルコ系であろう。トルコ半島を三角形の一頂点とすれば後の二つは、中国のシンチャン・ウイグル地区と、パキスタン北部になり、それによってカバーされる全面積が、「チュルク語系」に属することになる。
そこに見られる諸言語は、何千年という長い時間の末にすっかり語彙的には変形してしまったけれども、思考パターンの根本たる文法は滅多に変化しないものだから、まったく異なる言語の内部に温存された。これらを言語学的には少々不正確なところもあるが、アルタイ語族という。かつての民族の移動、征服、攻防の歴史がそのまま現在の国境を越えて固定化されたのだ。
これには中国語は含まれない。この言語はアルタイ諸言語とはまったく独自の発達を遂げた。一つには漢字の発明による。アルタイ言語にも漢字を取り入れた事例には事欠かないが、それは言語的に固定されてからの話であって、語彙の面や文化の面での影響は大きくても、それぞれの言語構造そのものには変化をもたらさなかったと言ってよい。
このように語彙の面を抜きにして、思考パターンの一つとしてのアルタイ諸語における共通因子を取り出したものがアルタイ文法である。これは中国語系はもとより、インド・ヨーロッパ語族、ポリネシア語族、アフリカの諸言語、コロンブス以前のアメリカ大陸の諸言語とも違う、一つの体系を為していると考えられる。
最大の特徴は後置詞(助詞)の存在である。前置詞によってその後に名詞相当語句をつなぐ、インド・ヨーロッパ系と異なり、語句のうしろに一定の短い音節の語を追加するのである。これは一見語尾変化ともとれるが、その万能的機能性、次に続く文との連結性から見て明らかに異なるものとする。たとえば「なら」をとれば、「痛いなら」「行くなら」「カゼなら」「いやなら」と前に付く語の品詞に関係なく、後に続く文に対して条件を示せる環境であれば、いずれにも追加できることがわかる。
これによって、主格、目的格のような動詞との位置関係もわかるだけでなく、今の例にあるように条件、理由、譲歩といかなる状態にも適用できる。これによって動詞の相対的位置は低下し、形容詞や名詞と同じような扱いが可能になるが、一方ではインド・ヨーロッパ系のような複雑な動詞活用を不要のものにもしているのだ。
いわゆる後置詞だけでない。その他複数を表したり、感情の微妙なあやを表したりするのに、次々と新しい語を付け加えてゆく。それによって一つの語が「膠着」してできてしまう。「いや・なん・で・しょう・よ」とこの例では5つの部分を付け加えて意味を出している。このような独特な語彙の追加は、他の言語への翻訳を困難にしている。
「赤く(塗る)」と「赤い(靴)」はそれぞれ「赤」が動詞に適応して連用形、名詞に適応して連体形を作っている。インド・ヨーロッパ系での副詞、形容詞と一見似ているが、異なっている点はそれぞれ独特で複雑な連結方法を編み出していることだ。連結するときの最後の「く」や「い」もやはり特殊な後置詞だといえる。
発音の点でも特殊な現象が見受けられる。我々は「酒屋」を「sakeya」と呼ばずに「sakaya」と呼ぶが、なぜだろう。答は簡単だ。後者の方が発音しやすいからだ。なぜか?それは後者のように発音すれば母音がすべて「a-a-a」でまとまるからだ。これを母音調和という。これに対して子音調和というのもある。アルタイ諸語を使う民族は寒冷地に住んでいる場合が多いから、なるべく口を開けないで、つまり喉を外気にさらさないで話すクセがこのような習慣を作ったのだという人もいるが、真偽のほどはわからない。
これらの特徴は他の語族と大きく異なるだけでなく、アルタイ語族内での言語の習得を著しく容易にする。日本人にとっても朝鮮人にとっても英語は難関だが、両国民ともトルコ語の習得は、語彙の点を除けばかなり楽にできる。
これは文法構造の類似が、思考方法の類似へとつながるからであり、コミュニケーションの際に何を優先して述べ、何を後回しにするか、一つの意味を表現するのにどの形式を利用するか同じような道をたどってゆくからだ。
ここにアルタイ文法をまとめる意義がある。すなわち限られた言語の間での共通構造を明らかにすることにより、人類の思考パターンの一典型を目の当たりにすることができることであり、これは今後アルタイ以外との比較をする上にも非常にプラスになるに違いない。
もっとも、日本語や朝鮮語はアルタイ語族に属さないという意見が最近では強く、せっかくの壮大な夢も崩れそうだ。実はアラビア語を勉強していると、動詞の前やあとに人称代名詞の「彼」や「私」がつくことがわかる。主語なしでも動詞そのものがだれが何をしたかある程度わかるようになっているのだ。
アラビア語はアッカド,フェニキア,ヘブライなどの諸言語からなるセム語族に属し、インド・ヨーロッパ語族である英語やフランス語の文構造に似ているが、人称代名詞が動詞語尾に付くという人称語尾という習慣はユーラシア大陸の広大な地域に多大な影響を及ぼしたらしい。
特にシルクロード沿いのトルコ人、キルギス人、モンゴル人などとは隊商貿易が盛んに行われたこともあって、彼らの言語(トルコ語、モンゴル語、ツングース語など)にそのような特徴を移し入れたと思われる。日本や朝鮮は地理的にいわゆる「極東」にあって、しかもポリネシア方面からの流入が多かったから、そのような直接的影響を受けなかったのだと思われる。
 文法学者なら、インド・ヨーロッパと呼ぶべきところだろうが、ヒンディー語やウルドゥ語の研究がまだなので、とりあえずヨーロッパとだけ呼んでおこう。但しハンガリー語、フィンランド語は除く。ロシア語系は、東の端にあったせいで、かなり古いタイプの形式を残している。また文字の上では全く違って見えるアラビア語がヨーロッパ系に意外と近いのは、地中海という地理的な近さのおかげだろうか。
文法学者なら、インド・ヨーロッパと呼ぶべきところだろうが、ヒンディー語やウルドゥ語の研究がまだなので、とりあえずヨーロッパとだけ呼んでおこう。但しハンガリー語、フィンランド語は除く。ロシア語系は、東の端にあったせいで、かなり古いタイプの形式を残している。また文字の上では全く違って見えるアラビア語がヨーロッパ系に意外と近いのは、地中海という地理的な近さのおかげだろうか。
日本人が大学に入って英語以外の第2外国語を学ぶことになり、フランス語やスペイン語、ドイツ語をとるとなると、英語で直面したような困難はあまり感じないことに驚く。確かに動詞の活用や、また一から出直しの語彙については仕方がないことだろうが、それ以外の文法的な点を考えると、英語とこれら3カ国語は非常に似ていることがわかる。
主語と動詞を中心とした「文型」がいくつか定まっており、目的語の位置もたいていは固定されている。また、同様に主格補語や目的格補語の位置も固定されていることが多い。アルタイ諸語のような後置詞がないから、そのぶん語順を厳しく守ることによってあるいは特殊な語尾を付けることによって品詞を明確に表そうとしているのだ。
形容詞と副詞の分業が進んでいる。形容詞は名詞を修飾、副詞は動詞など名詞以外の修飾とわかれていることが多い。さらに形容詞の中に冠詞という役割を果たす語があり、限定・非限定、特定・不特定のちがいを表す記号として活躍している。
英語の場合には大昔に捨て去ってしまったが、人称による動詞変化が存在する。さらに男性・女性・中性などの性変化、単数複数変化、それらが語同士の結合の時に現れる「一致」は、その言語が古めかしいほど顕著である。
英語の BE動詞に当たるものがどの言語にも存在し、これによって主語の「存在」や「属性」を示すことができる。中にはそういう動詞を省略してしまう言語もあるが、なにか「軸」となるようなものが想定できるという点では共通している。
さらに「時制」を明確に定めたものが多い。それらは助動詞によったり、語尾変化によって表されるが、単なる完了・未完了のみならず、大過去・過去・現在・前未来・未来をも詳しく表そうという傾向が見られる。
接続詞とは、文の先頭に付属するばかりでなく、主語と動詞をそろえた「節」同士を結合することができる。さらに接続詞を先頭に着けた方の文が、もう一方の文に対して修飾する働き、つまり副詞節を作ることができる場合がある。
そして前置詞があり、これは基本的にある一つの名詞を目的語として取る。こうしてできた前置詞+目的語のペアは、形容詞句か副詞句の役割を果たすことができる。前置詞の種類は多様だが、最初は「・・・の上」「・・・の下」のような位置関係から発生したものと思われる。これはアルタイ語系の後置詞と好対照をなし、非常に興味深い研究対象である。
さらに名詞に対する修飾は形容詞が担当するが、その位置は必ずしも前からとは限らず、名詞のうしろからも修飾できる。ここから、形容詞の働きを専門とした接続詞、つまり関係詞が登場する。関係詞は、通常の形容詞に頼らず、文そのものを形容詞に変えてしまう記号である。アルタイ語系では、連体形が大活躍するところだ。
これらの特徴は、すでに述べた中央ヨーロッパの、ゲルマン系もラテン系にも共通してみられ、少々乱暴だが、ロシア語系やアラビア語系にも見られるのだ。中でも主役はローマ帝国の言語であった、ラテン系であろう。フィンランドやハンガリーでは比較的後世になって、中央アジアのステップあたりから新しく移り住んできた民族がいたので、ヨーロッパ系と異なる言語になってしまったのだろう。
余談だが、国際語として生まれたエスペラントも、この意味ではアルタイではなく、明らかにヨーロッパ系に属し、しかもラテン系の語彙を多く使用しているから、ヨーロッパの統合言語とはいえても、世界の言語の統合ではないといえる。
英語しか外国語を習ったことのない人は、世界の言語はみな、現在、過去、未来によって区分されていると思いこむ人も多かろう。ところが実際はそうではないのだ。未来なんか、文脈でわかるという言語もあれば、現在と未来の区別がつかない言語もある。
時制というものはかなり哲学的であって、ひたすら現在の雑事に没頭する人間たちにとって、それ以外の時制は「ヒマ」な時に考えるべきものなのだ。今晩8時の待ち合わせになぜわざわざ未来形を使う必要があろうか?過去のことなど、「3年前の9月20日午前10時」といえばそれで済むこと。
ところが日常生活にとって欠かせない要素が一つあったのだ。例えば「なくす」という動詞を日本語で見てみよう。
- ああ、鍵をなくしちゃったよ!
- よく物をなくすねえ、ボケたんじゃないの?
- 最近の彼女はかつての魅力をなくしているね。
いずれの例もすべていわゆる「現在形」である。1番の文は過去形ではない。なぜならば、今ポケットを探って鍵がないことを発見したからだ。鍵がポケットから落ちた瞬間は過去だろうが、持ち主はその時間を特定できないはずだ。2番の文は今までのなくした実績の総括だが、もちろんこれも過去形ではない。なくすのはこの人の性質、性分、習慣、なのだ。特定のなくした行為をさして言っているわけではない。3番の文は、今ちょうど進行中のことで、これが最も現在をよく表している。ただし、今はなくす過程であって、彼女がすっかりその魅力を失ったわけではない。
このように、実際のコミュニケーションで区別が必要なのは、単純な時制による区切りではなく、行為が「すっかり済んでしまった」か、それとも行為が「いつも繰り返される」とか「行為が今まさに進行中」かを判別することなのだ。これができないと、鍵はなくしたあと見つかったのか、見つかっていないのかわからないし、仕事も済んだのか、済んでないのかがはっきりしない。
したがって1番の表現を「完了」、2,3番の表現を「未完了(不完了」」と名付けることになった。世界の多くの言語でこの区分が見いだされるのも、実用上の必要からなのだ。
英語には、ご存じの通り現在完了形や過去完了形がある。ロシア語には、完了動詞と不完了動詞と、別々の単語がそろっている。中国語では、語尾や動詞のあとに「了(le)」をつける。アラビア語では動詞活用が、完了形と未完了型にわかれている。
驚くべき共通点の一つである。人類の日常生活で、この区別がないと支障をきたすために、人種や地域や文化にかかわらず生まれたのだ。ただそれを研究する学者がそれぞれの専門分野から外を見ないために、それぞれの言語で違った名前がついてしまった。今度はそれぞれを詳細に研究して共通の用語を使う方向へ進まねばならない。
動詞を区分する上で完了形と未完了形の区別が重要であることはすでに述べた。しかし英語学習書を見ると、それよりも大切な区分は、昔から他動詞と自動詞の二つであるようだ。今でこそ基本5文型の考え方が普及し、この区別はやや後退した感があるが、それでも基礎的な事項として厳然と存在している。
そもそも他動詞とは、うしろに目的語、つまり名詞相当語句が付いたものをいうが、この位置にあるものを目的格、他の言語では対格と呼んで、いわゆる主語(主格)と区別している。
ところが、文法の世界で簡単に定義しても、生きている動詞の世界ではどうしても目的語とは納得しがたい現象が数多く見つかるものだ。日本語で次の例を見てみよう。
- 私は思いっきりジャンプした。
- 私はこの曲が気に入っている。
- この曲は私を夢中にさせる。
- 彼はロシア語を学んでいる。
- 彼はロシア語をしゃべる。
1番目の文では「ジャンプする」という自動詞が主語との組み合わせで一つの行為を記述しており、「いつ」「どこで」「どんなふうに」「なぜ」というような、取り外し自由な要素(副詞的要素)がついてもつかなくても一つの意味として完結できる。注:ここでは「思いっきり」というのが「どんなふうに how 」に属する副詞的要素である!!
2番目の文も誰も異存がないだろう。日本語であろうと、英語であろうと「曲」が「気に入る」という他動詞の目的語になっており、曲という語がないと、気に入るという動詞の意味が完結しない。すべての他動詞がこのようであれば何も問題ない。
ところが3番目になると少し事情が違ってくる。2番目の文との最も大きな違いは、主語が私ではなく、曲になっていることだろう。そのため「私」は目的語にされてしまう。つまり主語と目的語との逆転が起こっているのである。この原因は動詞そのものにあるといえる。「S が O に夢中になる」と「 S が O を夢中にさせる」とはまったく別の種類の動詞なのである。
走ったり、しゃべったり、怒ったり、人間行為や感情は人間の主体性によって起こるという考えから、主語が人間になるのは当然といえる。実際に、行為を表す動詞のほとんどはこのタイプだ。
ところが、「悲しむ」「驚く」「けがをする」「興味を持つ」という場合、まずそれらを引き起こす「原因」が存在して初めて、それらが人間どもにそれぞれの「結果」を引き起こすのであるから、方向性が逆になってしまうのである。
特に「けがをする」がいい例だろう。自分から進んでけがをしたがる者はいない。「滑ったナイフでけがをした」を厳密に記述するなら「滑ったナイフが私にけがさせた」のである。
この「原因から結果へ」の流れを汲む動詞の存在は、英語、フランス語、スペイン語、ロシア語などにはっきり見いだされる。これらの言語では、はじめから他動詞の概念がはっきりしているが、さらに厳密に記述するためにこのタイプの他動詞が必要とされたのだといえよう。
4,5番の文は、英語を学んでいる人なら、迷わず「ロシア語」を目的語とする他動詞を思い浮かべるだろう。ところがロシア語を学んでいる人にとってはそうはいかない。4番では通常の「ロシア語」という名詞を使うが、5番では、「ロシア的に」というような副詞を使うのである。
これはなぜだろうか。ロシア語だけに通用する特殊な問題だと一笑に付さないでもらいたい。ここには重大な問題が含まれているからだ。副詞を使うということは自動詞になってしまうが、「しゃべる」以外に、「読む・書く・(聞いて)理解する」の場合もそうなる。それ以外の動詞の場合は名詞である目的語の「ロシア語」をつける。
副詞を要求するのは、その動詞との関係が希薄だからだろう。言語の4機能に関する動詞では、必ず何らかの言語で話すのに決まっているから。必要なのは「どんな言語手段で(話すか)」なのだ。
これに対し、「学ぶ」の場合は、その対象が物理でも、文学でも、法律でもその分野が広範囲に及ぶ。常識の範囲内で学ぶことに適したものなら何でもよいわけだ。その分だけ他動詞との関係が密接になっていなければならない。。
この説明は強引かもしれないが、実際問題としてこのような現象が存在する以上、目的語と他動詞の関係は、副詞と動詞との関係に近いのではないかということが推測されるのである。すでに述べたように、副詞とは取り外し自由なものであるから、他動詞に必ずつかなければならない目的語とは、はっきり区別されるべきものである。
だが、その境界線上に存在する語も数多くあるということも忘れてはいけないだろう。特に中国語を学ぶ場合は、他動詞と目的語の関係(そう定義できればの話だが)きわめて流動的だから大いに悩まされるだろう。
文法学者たちは、さまざまな文例を観察して動詞のあとの目的語の有無により、他動詞と自動詞の区別をしてきたことはすでに述べたが、言語が人間生活の中で自然に根付いてゆくとき、どのような過程を経て今日のような形になったのだろうか。
言語が人間がとりおこなう日常生活の中から生じてきたとすれば、当然最初に登場した動詞は、自分や仲間の「行動」を記述するものであったろう。
まず自らの「自律的」行動の記述の例を見ると、「歩く」「走る」「跳ぶ」「止まる」「笑う」「泣く」のように、主語である人間と主体が引き起こした行動を示すだけであるから、全て自動詞となる。
つまり自らの肉体が引き起こした行動には、目的語はいらないのである。「遊ぶ」も自動詞となる。遊ぶときには道具を何らかの道具がかかわり、それがおもちゃであれ、木ぎれであれ、それらを使いつつ、人間は遊びを自ら体験する。
だから「野球を遊ぶ」と言わないのは、この本来の意味を失い、実は野球を「する」という意味がすでに固まっているからである。play baseball は確かに「遊び」の起源は含まれているが、ここでの動詞の役割はもはや特定のスポーツをこなすという意味で使われている。
これに対し、人間が外界のあるものに対し働きかけをして、または感じ取っている場合はそれを示すために目的語、つまり他動詞が必要となる。「ダンスを楽しむ」「悲しみを感じる」「品物を受け取る」などはみなこの範疇に属する。
結論から言えば、その動詞の持つ性質が目的語を必要とするか否かに行き着くわけだが、動詞に対する定義が違ってくれば、目的語の有無も異なってくるわけだ。
そのいい例が「その問題を討論する・その問題について討論する」「 discuss the problem 」だろう。これは日本語と英語とでは、同じような意味の動詞が違ったように定義された好例である。
日本語における前者の「討論する」は、英語の場合と同じように、討論の主題になっているものが目的語として位置するが、討論の主題があって始めて全体の行為が成り立つという考えから他動詞が使われていると言えよう。
もう一つの「・・・について討論する」では、すでに「討論を行う」という他動詞と目的語の組み合わせがあって、それだけで意味が自己完結している。だから、「・・・について」を追加しておかないと主題を付け加えることができないのだ。
このことから、他動詞とはそれだけでは意味を完結できない不完全な動詞ということが言える。英語の辞書で動詞をひくと、その多くが意味の変化はなくとも、他動詞と自動詞の両方があると記述されているが、これは文脈によってすでに何が来るかわかっている場合は自動詞を使ってよいことを意味する。
だからいちいち drink alcohol beverage といわずとも、気の知れた仲間たちの間なら、 drink で済んでしまうわけで、そのメンバーは誰1人としてジュースを飲もうなどと想像する者はいないのである。
この概念なしには、人類の言語はまったくまとまりのつかないものになるだろう。格という用語を古めかしい言語の遺物ととらえる向きもないではないが、ラテン語やサンスクリット語の息をのむような複雑な活用にもそれなりの存在理由があったのだ。
格とは名詞の文中における位置を示す記号である。「トラだ!」と叫ぶだけだったら格はいらない(いる言語もあるが・・・呼格と名付けている)。だが名詞が複数使用されだすと、名詞を繋ぐ語との関係をはっきりさせる必要が出てくる。主な格を日本語で見てみよう。
- gakuseiga 学生が気楽です。
- gakuseiha 学生は気楽です。
- gakuseimo 学生も気楽です。
- zouwa hanaga ゾウは鼻が長い。
- gakuseiwo 何人かのたむろしている学生を見た。
- gakuseini その学生にメモを渡した。
- gakuseino それはあの学生の本です。
- gakuseitoshite その行為は学生として恥ずべきことだ。
格の表現方法はいろいろある。日本語ではいわゆる「助詞」を使う。名詞のうしろにつくので「後置詞」という人もいる。ただし、離れているのではなく、前の名詞と「膠着」してしまっている(アルタイ語族の特徴)。これをローマ字で書くと、とても覚えにくいような印象を持つ。実際、ロシア語の複雑な活用法を覚えさせられている人にはよくわかるだろう。
1,2,3番は有名な「が・は・も」で、主格を表す。1番の「が」は、「学生でいることが気楽です」ともとれる。2番の「は」は、1番の意味の他に「その学生は気楽です」ともとれる。文脈にもよるが、表現の工夫次第で「その・・・」という限定的意味をこの「は」に加えることもできる。これは英語なら定冠詞 the を必要とするような場面である。日本語では、このように助詞の使い方次第で、冠詞の機能も表すことが可能なのだ(うまくやれば!)3番は「他の職業も気楽だが」という前提を含むとも考えられる。
このようにニュアンスの違いはあるけれども、基本的にこの3つの助詞は「気楽」の主語になっていることは間違いないだろう。4番のように紛らわしい文もあるが。だがこれも「長い」のは何か、と検証すれば、「鼻が」が主格になっているのは明らかだ。「ゾウは」は単に話の主題を提供しているのに過ぎない。
5番では動詞「見た」のは何かを示している。これを目的格(対格)という。他動詞・自動詞の項で述べたように、この定義は流動的で難しいが、とりあえず一番無難な例を挙げておいた。
6番では動詞「渡した」の目的格(直接目的語)に該当するのは「メモ」だが、それ以外にそれによって利益を受けた人物が存在するため、これを示す必要がある。これが「に・へ」などで表される与格(間接目的語)である。与格が必要な場合は、特別な動詞「送る、渡す、与える」などに限られる。
7番では、学生は本の所有者であることを示す。所有格(属格・生格)などと呼ばれる。二つの名詞を結びつけるので最もわかりやすい。
8番では、数多くあるつなぎの助詞の中から、「・・・として」を選んだ。地位・位置を表すものと考えられるが、特に名前は付けない。
自分の母国語であれば、格の約束は生まれてから無数の練習を経てきているので、われわれは無意識のうちに話している。だが外国語を学ぶときは、いちいち文中の位置を意識しなければならないので、これが語学の進歩の上で最大の障害になっているといえよう。
格の表現は、ラテン語、サンスクリット語、ロシア語のように、「語尾変化」によって区別するものが最も有名である。ただ、それがさらに人称や時制とも関わりを持たせてあるから、人間の記憶力の限界を超えるような複雑な体系ができてしまう。だが人類が言語を身につけ、それを運用させるときには、これが最も確実な方法であったようで、古代語は文章語において特に、その点で共通している。DNA の中には「語尾変化」を担当する遺伝子があるという説まで存在するのだ!
だが一般の人々が話す場合の煩雑さが、単純化に拍車をかけ、語尾変化はどんどん少なくなっていった。そしてついに、英語のように所有格や代名詞を除き、「位置」だけで格を示すようなものまで現れたのである。
中国語も系統はまったく別だが、英語と似ている。ただどちらが優れているかは一概に言えない。動詞の語尾変化が無くなると、主語を省略することが困難になる。しっかりした語順のルールができあがっていないと、文が曖昧になる危険性がある。
さらに、与格や8番で示したようなさまざまな状態をより軽快に示すために、前置詞が多用されるようになった。語尾が取れて前に来たようなものだから、前置詞の利点は、そのあとで示される名詞の意味よりもその(副詞)句の機能が先にわかるということにある。
仮に、「として+・・・」とはじまれば、学生なのか、社会人なのか、親なのか、まだわからないにしても、これから「地位・位置」の話が始まるのだな、という想像がつく。
現代の、特にインド・ヨーロッパ系の大多数の言語は、主格・目的格・所有格にはまだ語尾変化が残っているものの、それ以外の格については前置詞を利用する傾向が大きい。
そして我が日本語、そして朝鮮語、トルコ語、モンゴル語などは、いわゆる後置詞によって格を表している。この方面の言語世界には前置詞の発生はあり得ない。言語が別の方向に進化してしまった。だが後置詞が、前にある名詞と離れているわけではないから、誤解を恐れずにいえば、一種の語尾変化とも考えられるのである。
このような混乱は、それぞれの言語の専門学者が自分の都合で次々と用語を考え出したからで、早くこれらの共通点を結ぶ用語が作り出されてほしいものである。
英語を学んでからフランス語、ドイツ語、スペイン語、はたまたアラビア語やロシア語、どれを学んでも男性、女性名詞の区別を聞かされる。中にはさらに中性名詞まで加わっているものがある。一体なぜ名詞にわざわざこのような面倒な区別をつけなければならないのだろう?その多くは男性、女性名詞の間で「語尾」の形を特徴づけている。
その理由は多くの人々が考えたが、今ひとつ決定的な結論は出ていないようだ。外国人にとっては煩わしいばかり。確かに英語でも20世紀前半までは「台風」「飛行機」「国名」などに関してはその代名詞を she として使っていた。ただ最近ではすっかりそれもすっかり見かけなくなった。
トンネルが女性名詞で、列車が男性名詞、ボルトは男性名詞で、ナットは女性名詞、山も女性名詞などと聞けば、この区別を採用している国民は色キチガイであろうと思ってしまう。だが形状的なものから判断できるのはごく一部で、大部分はなぜそう決まったのか首を傾げざるを得ないものだ。
ただ、この区別によって受ける利点ははっきりしている。男女の区別をつける言語では、形容詞がそれらを修飾するときに同じ区別を示すための記号がつく。たとえば「花」が女性名詞だとすると、「赤い花」と言った場合、「赤い」という形容詞もいわゆる女性形となる。だから誰でもこの二つが一体であることが一目瞭然であり、多くは語尾が同じになるので、韻を踏むにも都合がよい。
英語の場合、ある形容詞が近くの名詞に係っているのかいないのか、文脈以外では判断がつきにくいことがある(もちろんそれは書き手のうまさによるのだが)。だが男性女性の区別が完備していればそのような不便はかなり解消できるのではないか。ヨーロッパ系の言語は関連ある単語同士の「一致」を大変重視する。
ある修飾関係を文脈だけで判断させることには無理がある。書き手のうまい下手もあれば、読み手の能力の不足も考えられるからだ。明瞭な言語とは、文脈だけでなく、他の方法でも間違いなく伝えられるものであるべきだ。一般庶民の間で勝手に発達していった言語であれば、文脈やジェスチャー、相手との相性だけでコミュニケーションが成立するかもしれない。だが、法律、政治、行政、科学の分野でも使われるとすれば、伝達の正確さのさらに一層の保証がほしいところだ。男性、女性の区別はそのような点で役に立っているのではないか。
だが、近年になって英語がこの区別を捨て去ってしまった事実も考え合わせてみよう。イギリスでは男女平等の考え方がもっとも早くから普及していた。これに対し、南欧、ロシア、アラビア、といえばいずれも女性の社会的地位が相対的に低い国々である。と同時に女性への文化的、生理的?関心も高い国々でもある。当然人間はもちろんのこと、物事も「二分」するとなれば何を基準にするか?これは男性、女性の区別以外に考えつかない。子供と大人でも、若者と老人でも、貧乏人と金持ちでも、境界線がはっきりしない。
何でも二つに区分して分析を試みることの好きなギリシャ、ローマ、キリスト、イスラム文明に属する人々にしてみれば、この区分方法が最も日常生活にぴったりだったに違いない。これとは逆にイギリスでは、男女の区別に対する関心が著しく低かったのだともいえる。misogynies (女嫌い)という専門的な単語があるくらいだ。
ラテン語、古代ギリシャ語、サンスクリット語、正統アラビア語(フスハー)。これらの言語に挑戦した人々は多いだろうが、挫折してしまった人々はその8割だろうか、それとも9割だろうか。
古代語とよばれるものは、どれも難しい。不必要と思われる些末な文法規則が絶えずつきまとい、これに気を取られていると一体この文が何を言いたいのかを忘れてしまう。ヨーロッパで高等教育を受けた人々の記録を読むと必ずと言っていいほどラテン語の語尾変化の暗記に苦労したかが述べられている。
これらの言語の共通性は、これらが「書き言葉」だったことと官僚の用いる「記録言語」であったということだ。ラテン語とフスハーはそれぞれ宗教の聖典の言語として、宗教団体内の共通語として今日に至るまで伝えられてきた。
古代ギリシャ語とサンスクリット語に関しては今日に残る記録を読んでわかるように、書記たちが石版や木版にせっせと書きためたものが大部分である。書き言葉として使われると、後世の人々が誤解を生じることのないように、厳密さが必要以上に強調される。
また、どの古代国家でも「韻文」が重んじられ、一定のリズムに沿った文づくりが進んだ。おそらく書記たちは毎晩のように会議を開きいかにして言語の壮大な体系ができるかを検討しあったにちがいない。彼らの職業柄からして、また石碑に刻むと言ったような名誉ある作業があったこともあって、念には念を入れた規則のシステムを作り上げたのだ。
また、これらは読まれるために書かれているが、読むという作業は慣れてくると、単語を一つ一つ追っていくのではなく、一度に視野に入るすべてを同時に把握する芸当も可能になる。こうなるとそれぞれの単語は全体の中における位置を示す厳密な記号が要求されるのである。これは巷の商人たちの取引や、女たちのうわさ話に用いる言語とはもちろん同じはずがなかった。現実の口によるコミュニケーションは、スピーディーであり何よりもその時代の一般の人々のほとんどは文盲だった。記憶の負担になるような余計な規則ははじめから存在せず単純さが重んじられたのだ。
音声言語は言うはしから空中に消えていく。だから前に口から出た単語と次に出てくる単語とははっきりした文法関係を持ってつながっていなければならない。つまり「語順」が重視される。語尾の複雑な活用はスムーズなコミュニケーションのじゃまになる。実際多くの言語で、文字としては残っていても発音されない語尾の部分が数多く見受けられるのだ。発音のしやすさも大切な要素だ。日本語でもかつて「書きて」と言っていたのを「書いて」とし、「読みて」としていたのを「読んで」と変化する「音便」現象に見られるように、文法規則よりまずはなめらかさが優先されるのだ。
それでも王侯貴族の話す言語が一般の人々に影響を及ばさないはずはない。書記たちの持つ文化的権威が人々の言語も勝手な方向へ発展する方向をおさえていた。ある王国が閉鎖的でほかの国々との交易があまり盛んでないとか、遠く離れている場合そこにある言語は独自の発展を遂げ、独特の規則を発展させた。それは現在でも保たれていて昔の形式が今でも使われている。
一方トルコのように、周りを言語タイプの違う国々(アラビア、ペルシャ、サンスクリット、ヘブライ)に囲まれながらも盛んに外交、戦争、交易を繰り返した地域では、それぞれの言語の要素を取り入れて単純化した。実際トルコ語と(口語)アラビア語の文法規則は単純で例外が非常に少ない。これは外国人にとってありがたいことだった。
このように、古代語の難しさは、書記たちが自分たちの言語を独り占めし、閉鎖的な空間での言語構築が進んだからに違いない。一方外の世界では次々と「俗語」が発展した。ラテン語からはスペイン語、フランス語、イタリア語が、フスハーからはアンミーヤが、サンスクリット語からはヒンディー語やウルドゥ語が生まれていったのだ。
***
人類の言語は一般に、昔にさかのぼればさかのぼるほど、複雑で難しい構造になっている。これは単なる書き言葉による影響だけではなさそうだ。というのも古代文明が出現する以前には、人類全体が文盲だったわけであり、そこでは音韻だけが支配する世界であったのだ。
ラテン語、サンスクリット語のような代表的な古代語のみならず、アメリカインディアンの言語、アフリカ奥地の言語なども複雑きわまるものが多い。これらの共通点はそれらの言語が形成されるまで、激しい人間の移動や出会いがなかったことがある。つまり閉鎖的な空間でその場所独特の言語体系が極めて長い間に培養されてきたのだ。
そこでは集団の長老たちがしきたりを作り上げ、おきてを人々に広め、厳かな儀式を繰り返してきた。人々に威圧感を与えるには、その道具立てだけではなく、使用言語も特別なものでなければならない。服従する庶民たちは文句を言うこともできず、周りの民族との交流もままならないから、世代を経てもそれらの体系に変化はあまり見られなかった。
かくして言語は、現代よりも古代が、都市よりも田舎のほうが、交易の場よりも孤立した地帯のほうが、保守的な性質を帯びるようになる。このことは柳田国男も述べていることである。
したがって、現代において英語がもっとも単純化された言語の一つであることは、イギリスが中世の停滞の後に産業革命を起こし、世界の果てにまで進出していったことと大いに関連があるに違いない。中世英語はまたたくまに現代英語への変化を遂げたのであった。
2009年6月追加
日本人は自分たちのしゃべる言葉に大して普段あまり注意を払わない。最近日本語関係の本が多く出版され、ようやく母国語への「自覚」が高まってきたようだ。フランス語のように昔からきちんとした体制を作り、世界中に通用する教授体制を作っているのに対しまだまだだ。
もし日本語の構造について明確な理解があれば、英語などの外国学習に対する効果も上がるはずなのだ。たとえば今日の中学校や高等学校での英語の授業では、単なる「訳読」を進めるのに過ぎず、日本語と英語の文法や構文の比較はもちろんのこと、考え方や文の流れに対する最も基礎的なことすら触れられていることがない。
これでは6年間学校で英語を学んでもその努力の大半は無駄になるどころか、英語の嫌いな人間を量産していることになる。日本語の語順と英語などのインド・ヨーロッパ語族との違いを少しでも認識すれば、外国語の勉強はどれだけ楽になることだろう。
学校では「英語」「国語」の時間だけでなく「言語間比較」の時間をもうけたら生徒たちの外国語に対する偏見もずいぶん改められるのではないか。ただしそのような科目を担当できる人材が払底していることも事実ではあるが。
多くの日本人が自分たちの言葉を特殊なものと思いこみ、日本語を巧みに操る外国人を見て驚嘆の目で見ることが多いが、実は日本語は少なくとも話し言葉に関してはかなりパターン化しており、かなり扱いやすい言語の一つなのだ。多くのヨーロッパ言語での動詞や名詞の語尾変化の煩雑さに悩んだ人にとっては、日本語のそのような意味での難しさは皆無と言っていい。
日本語では動詞表現が最後に来る。「私はデザインがよく作りも立派なバッグを渋谷の専門店で・・・」と来て最後にどうなったのかもどかしい。「買った」と終わればほっとする。名詞の修飾も必ず前だ。「公園でなわとびをしながら大声を上げている子どもを見守っている・・・」ときたところで最後に「母親」とくれば修飾が完了する。
だがこれらも別に日本語の専売特許ではない。トルコ語も朝鮮語もその他その系統にある言語はみなそうだ。むしろさんざん文字で苦労させられたアラビア語などを勉強していて英語と同じ働きをする関係代名詞を発見したりしてその共通性に驚かされる。
こうやってみると日本語は世界の言語の中では一つのグループに属する言語に過ぎない。長い間海によって隔てられていて語彙における独自性は際だっているものの、文法構造に置いてよく似ている言語はいくらでもあるのだ。
言ってみれば、太古の昔に、人間集団がある時点で決別してそれぞれまったく別の地域に住む分岐点の時点で同じ言語をしゃべっていたわけだからそれを現在に至るまで引きずっているのは当然のことだ。トルコ人と朝鮮人と日本人はさかのぼればどこかで合流するのだ。
さまざまな細かい変化はその後の時代の中で起こったに過ぎない。たとえば音韻変化だが、学者によればこれはかなり規則性があり、同じ音韻であれば広く語彙の中で変化が起こるという。音声は識字率が高まるまでは人々のコミュニケーションのほとんどを占めていたわけだから、ちょっとした変化は急速に広まり、中央で起きた変化などは同心円を描くように地方へと伝わってゆく。
日本人は母音をあまり増やさなかった。というよりはもとはたくさんあったらしいがいつの間にか5つに収束してしまった。これはイタリア語やスペイン語などあまり例がない。しかも子音の方もずいぶん単純化されてしまった。h の音も f の音も一緒になって「ハヒフヘホ」になってしまった。
このため現代日本語には同音異義語が多すぎる。これはいわゆる「駄洒落」の乱造を招き、意味のない笑いを引き起こすだけになっている。それどころか平板なアクセントのおかげでそれぞれの単語の意味がつかみにくくなっており、効率的なコミュニケーションにも支障を来すようになっている。
対策としては、中国語における声調のように、何らかの区別をつけるための標識を同音異義語同士の間にもうけることだ。それが難しいのならば、音声の全く異なる別の単語に言い換えを促進することだ。
もちろんこのためにはアカデミー・不乱せーずのような強力な推進機関がなければ不可能だが、それにしても日本語の現状だけでも学校できちんと教えてくれないものだろうか。作文、読書指導も結構。だがもっと言語学的な基礎事項をしっかりと生徒に身につけさせるべきなのだ。
世界の言語がどうしてこんなに多様な形に分かれてしまったのか?何といってもこれまでのお互いにほとんど行き来のない孤立した暮らしがそれぞれの独自の発達を助けたのだろう。逆にシルクロードのように人々の行き来の盛んな地域ではお互いに言語が似通っている。
ただ、言語の相違や類似を語るとき、語彙の点から見るか、文法の点から見るかでまったく異なってくる。語彙の点からの比較はわりあいかんたんだ。現代のわれわれでも日々外来語の攻勢を受けており、いつの間にか数え切れない外国の言葉が似たような発音と共に日本語の中にしみこんでしまった。
ところが、文法構造の変化はちょっとやそっとでは変化しない。なぜならそれは人々の思考の道具になっているからだ。これをいじくりまわすには人々の論理の捉え方や感性の内容まで手をつけなければならない。このため長い間接触のなかった言語間であってもその祖先が共通であるならば文法構造に驚くべき類似が見いだされるのだ。
日本語を母語とするものが英語の学習を「苦痛」と感じる人々が多いのは、その語彙の違いによるだけではない。発音が難しいということもあろう。だが何といっても根本的な問題は、「後ろから訳す」という言葉に象徴されるように、まるで正反対と言えるような文法構造の対照性である。それは次の3つがもっとも顕著である。
(1)英語では主語のあとすぐさま動詞が来るのに、日本語ではすべてを言い終わったあと、最後にやっと動詞が現れる。
(2)英語ではまず前置詞が現れ、その支配下にある名詞が現れる。ところが日本語ではまず名詞が現れそのあとに後置詞(別名助詞)が現れる。
(3)英語ではある名詞の説明を文を使ってするのにそのうしろに関係代名詞で始まる形式を使う。これに対して日本語ではその名詞の前に文を並べて連体形を使って修飾する。
このようにわざとやったのではないかと思われる逆の方式が存在するのはなぜであろうか?われわれの祖先が共通の単一言語を話していたと想定しよう。ある日、何らかの事件によって彼らは集団を分裂させ、ある者は東に、あるものは西に向かって行ったのであろう。
だが上記のような表現方法の違いが自然にあらわれたとはどうしても想像しがたい。誰か中央政府のやり方に反発する者がいて、秘密結社を作り、集団で主流になっていた言い方に対し、自分たちの集団を迫害や発覚から守るために、一種の暗号としてあるいは隠語として逆の言い方を発明したのかもしれない。
最終的にはその集団は主流派からわかれまったく別の地域に移住していったのものと思われる・・・と今さら想像をたくましくしても何にもならないが・・・いずれ誰かが史料をそろえてもっと気の利いた「創世記」を語ってくれるだろうから。
ここで取り上げたいのは、現代に使用される言語の大きな二つの流れを英語タイプと日本語タイプに分けてみる試みである。英語タイプに属するものは、今まで通り日本語を母語とするものにはつらい学習が待ち受けているだろうが、日本語タイプに属する言語については語彙や文字、発音の学習はさておいて言語そのものの学習は比較的楽ではないだろうか。
英語タイプとしては、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語、アラビア語を選んだ。この中で文字からしてまるで違う中国語が入っていることに困惑する人もいることだろうが、西洋語に近いというのは紛れものない、多数の学習者の感想なのである。
日本語タイプとしては、朝鮮語、トルコ語、ヒンディー語があげられる。この中でヒンディー語はヨーロッパ語族に近いというのが一般的な学説であろうが、それは動詞の語尾変化などに着目した場合である。動詞の位置と、後置詞の存在についてはこちらのグループに属する。
言語間の比較をする場合、違いを強調するのは当然だが、一方で類似点を徹底的に追及するのもおもしろい。たとえば日本とトルコという歴史も宗教もまったく違い、途中にまったくの異国をはさんで遙か彼方の距離にありながら、言語の共通性に気付くと、もしかしたら遠い昔の人類の移動のあとを発見できるのではないかという予感をもってしまうのだ。
2006年5月初稿
英語を世界の共通語にすることは、英語を母語として用いている人々と、そうでない人々との間に大きな不公平を生じる。現在は経済的、政治的優位が、人々に「自発的」に英語を学習するように動機づけているが、例えば国際会議などで使用言語が英語として決められてしまう状態は決して英語が母語でない参加者の利益にはならない。
一方で英語を母国語とする者たちは同時に国際語を繰っていることになり、権力の偏在にますます拍車がかかる。彼らは、したがって外国語学習に非常に消極的である。アメリカの場合を見てみると語学を専攻する学生の数や外国語学校の割合が他国に比べて驚くほど低い。この状態は彼らをますます傲慢にしていく。決して放置できない事態である。
人工語であるエスペラント語を使うことが本来はもっとも望ましいことだが、これは発明されて100年たった今もあまりに普及率が低い。自然言語のなめらかさや効率の良さを人工語に加えるにはまだ相当時間が必要なようだ。
となると世界の言語体制はどのような形で進むべきなのだろうか?グローバリゼーションは、世界の文化の統合と画一化を進めはするものの、絶滅の危機にさらされた弱小言語の衰退を早めるばかりである。言語が単一になってしまった人類社会は何と退屈なところになることだろう!
言語の多様性を減らしてゆくことは、生物の多様性を減らすことと同じく人類、ひいては惑星の財産を大いに減らす結果をもたらしてしまった。これは中央集権的な国家が自国の統一を確実なものにするために半ば強制的に「国家語」を定め、教育機関によってそれを国内の隅々まで普及させようとするからである。
このようにして、アメリカ合衆国、ブラジル、インド、中国、ロシアなどの他民族を含む大国はその中にいる少数民族の同化をいっそう進めようとしている。しかし大国主義は人類の未来にとっては危険きわまりないものだ。大国間の対立は直ちに大戦争の危険をはらみ、内部分裂を恐れる各政府はいっそう国民への締め付けをはかろうとする。
大国主義と、言語による覇権は手を携えて進む。世界はまっすぐにその方向に進んでいるように見える。だが、ヨーロッパ連合のように、ゆるい連帯のもとに、小さな国が生きて行く方法も示されているのだ。かつては世界に植民地を多数建設したイギリスやスペインでもその国内には中央政府に反対して自らの自治権を求め、それぞれの「生活言語」を主張する住民グループが多数存在する。
今のところは経済的にも政治的にも力を持つ、カタルーニャのような自治政府の存在が将来へのモデルとして有望である。人々のコミュニティーは、いくらでも細分化されるべきであり、これは旧ユーゴスラビアの地域でも目下進行中である。これらがいずれはすべてEUに加盟し、各政府の権利を尊重しつつ共存をはかることになろう。
EUでは「言語権」が保証されている。それは一定の大言語に偏ることなく、会議ではどの言語も平等の権利を持つということだ。ここではじめて言語による不平等を完全とは言えないが何とか解決してゆく道が開けたのである。将来的には通訳の増員、翻訳機械の改善が、少しずつこの方向を現実化ならしめてゆくことだろう。
それではここの人々はどのような生活を送るべきか?すでにシンガポールやスイスの人々に見られるように、バイリンガル、トライリンガルであることが求められる。もはや今までの日本人のように単一言語だけを使って死ぬまで暮らしてゆける時代ではない。頭の構造を変革する必要がある。
いちばん根本的な言語は、自分の家族や友人とのコミュニケーション言語、いわゆる生活言語であるが、もっとも大切なのは、自分が「思考」するのに用いる言語であるということだ。これはこの言語が自分のアイデンティティの源泉であることを意味する。
これは人間にとってもっとも大切な権利の一つである。アメリカ合衆国において言語を奪われたインディアンたちのような例は決してあってはならないのだ。育った地域の方言で話すときに、自分の感情や相手とのコミュニケーションがもっともよく行われる。生まれ育った場所の方言は自分の血液であるのだ。その言語世界は実にプライベートなものだ。
生活言語はごく小さな国ではそこの国家語と一致する。言語統一が進んだ(多様性の見地からすると必ずしも良いことではないが)国では、方言が消滅しかかっている場合もある。一方、インドネシアとかマレーシアのような場合には、方言以上の違いを含む「部族語」や「地域語」が無数に存在する。
このように言語が国内でそれぞれ異なって存在することを、為政者たちは毛嫌いする。国家統一の障害としか見ないからだ。だが自らのアイデンティティを破壊したくなければ、権力者たちとの対立は永遠に続くことを覚悟しなければならぬ。そして国際的にも言語独立の運動には力強い支援が必要である。
現在の世界では各個人は必ず何らかの国に属することになっているから、その国家が定めた言語、つまり「国家語」が自分の住む国内での共通語となる。インドにおけるヒンディー語、インドネシアにおけるインドネシア語、中国における北京語などは、その中に抱える無数の少数言語が存在する以上、国内でのコミュニケーションにとっては必要不可欠のものである。
ではいったん国外に出たらどうか?すでに述べたように、英語のみを国際共通語とすることは不平等を深刻化し、文化的偏りを招くことになる。世界の広域共通語は完璧な人工語が実現するまでは、少なくとも5個以上存在し、互いに牽制し合う状況であらねばならない。野放図な「自由競争」が今日の事態を招いたのであるから、EU諸国のやり方を参考にして当事者以外の言語を除く「媒介言語」をうまく組み合わせるしかない。
そのためには現在のアメリカ合衆国による政治的、軍事的、経済的な寡占状態が最大の障害である。一刻も早くこの国が衰退して他の言語圏と対等の立場になるまで落ち込むことが切に待ち望まれる。そのためには、中国、ロシア、インド、ブラジルなどの経済圏が大きく拡大して均衡のとれた状態になる必要がある。
広域言語とは、共通性の多い文化圏に流通する人類社会の最終的な共通語である。その候補としては現在、国連の言語として用いられている、英語、フランス語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、中国語の6カ国語が有望である。もちろん6カ国語によってそれまでの不平等が解消するわけではない。しかし一国主義、超大国主義の事態は避けられる。
英語、フランス語、スペイン語は旧植民地諸国の共通言語として、ロシア語は旧ソ連圏の共通言語として、アラビア語はイスラム圏の共通言語として、中国語は東アジア圏の共通語として定着しつつある。さらに南アジア圏でのヒンディー語や東アフリカ圏でのスワヒリ語も共通語になる可能性がある。
さらに日本に関して言えば、将来的には東アジアの周辺諸国との接触が最も重要なものになるのであるから、当然中国語が第1に重視されるべきである。残りの共通語に関して言えば、それぞれの仕事や興味に応じて加えてゆけばよいのである。
このように、世界市民は、「生活言語(方言)」「国家語」「広域言語」による2段階、または3段階での言語使用者になるべきなのだ。そして旅人は安易に共通語に頼ることなく、できるだけ地元の言語を勉強していけばたとえたどたどしくてもきっとそこの人々に歓迎されることだろう。
2006年5月初稿
日本語では、主語がよく省略される。そのために誰がそんなことをしたのか言ったのか判然としない場合がある。一方、スペイン語やトルコ語でも主語の省略はごく普通に行われる。
だが、これらはみな同じ現象と思ってはいけないようだ。というのも、スペイン語やトルコ語の場合、主語と結びつく動詞の形はしっかり決まっていて、動詞そのものを見ただけですぐにその主語が何であるか判定がつくからだ。
一般的に人称代名詞の1人称単数・複数、2人称単数・複数、3人称単数複数の計6種類が一つの動詞の「原形」から語尾を換えたりして派生している。だから、その派生形式が規則的であればたとえ主語がなくとも少しも困らないのである。
代名詞でない場合、つまり一般名詞や固有名詞の場合は、これらの言語では主語を省略することはない。だから、この点では日本語の場合とは基本的に違うのである。
日本語の場合、人称代名詞の変化によって動詞やその他の用言が規則的に変化するわけではない。「私は走る」だし「彼は走る」である。だから、いきなり「走る」と言われても「誰が?」とわからなくなってしまう。
このように日本語で主語をやたらに省略されたならば、不正確きわまりないのか?かつてはこれに対処する方法があったようだ。それは敬語である。尊敬語、謙譲語、丁寧語などの細かな区別がかつての日本語には存在していた。
この使い分けにより、(話の当事者の上下関係がわかっている限り)主語はそこからある程度推定することができたのである。だから権力機構や宮廷内での話は、主語が省略されてもさほど不便はなかった。
ところが現代日本語では敬語は急速にその明確な形を失いつつあり、上下関係は混乱し?、状況に置ける正確な使い分けも曖昧になり、もはや敬語の使い分けで主語を推し量ることはほとんど不可能に近くなった。
このため、現代日本語の文では「彼」「彼女」などの西洋語から借りてきたような代名詞をつけることがますます重要になってきている。この習慣はかつての日本語の伝統とはあまり相性がよくないのであるが、コミュニケーションにおける誤解を避けるためには、我慢して使っていくしかないだろう。
一方、日本語以外の言語における主語の省略というのは、通常曖昧さを伴わないものであるから、単に主語を別の言葉や記号に置き換えたに過ぎないと認識すべきだろう。ただ、多くの国民は、いちいち主語をつける煩わしさから逃れたいというのは世界的傾向であるようだ。
2007年4月初稿
日本で親しまれている外来語のうち、その起源が明らかになったものはそう多くない。何しろマンションや店舗の命名者は次々と口当たりのいい単語を見つけだしてくるものだから、使用者はその起源を追い求めるのをあきらめそのままになっているのが多い。さまざまな外国語を学んでいると、「これは?」というのにいくつか出くわすものだ。
生理用品で有名なアンネ、これはドイツでナチスに迫害されたユダヤ人少女の日記で有名になったと思われるが、 トルコ語の「母」もまたアンネなのである。このほうが関係が深くてよさそうだ。もちろん将来の調査が必要である。
ある会社の名前が「アサンテ」という。この響きのいい言葉はどこから来たのかと不思議に思っていたが、スワヒリ語の「ありがとう」に相当することが判明した。これは映画の題名だが、「ブワナ・トシの歌」。ブワナは スワヒリ語の「ミスター」に該当する。
マヒナスターズといえば戦後生まれの歌謡曲愛好家にとっては懐かしい名前だ。マヒナは ヒンディ語の「月」にあたる。つまり両方合わせて「月星」というわけで夢のあるコーラスグループにはぴったりの名前である。
どうやら諸外国語のうちでスペイン語は、日本語の語感にぴったりらしい。「ルミネ(光)」「カサ(家)」など母音の音が強く響く単語がよく採用される。英語の単語はもちろん必要上最も多く用いられてはいるが、その子音中心の発音構造のせいで日本語音になじまず、大きな変形を受けている。
その例としては machine が「ミシン」と「マシン」の二つになり、strike が労働運動では「ストライキ」となり、野球界では「ストライク」となるというのは、日本人が勝手に語尾の母音を変えてしまった好例である。
もっとひどいのは Hepburn であろう。ローマ字に改革を加えたヘボン氏も「ローマの休日」で有名なヘップバーンまたはヘプバーンも同じ綴り、つまり同じ発音だ。違った世界で受け入れられたから違った音になってしまったのか?
thank you の th の音はもともと日本語にないから、これが日本語に採用されたとき「 san + kyuu 」となり、もととは似てもにつかぬ音になってしまった。もっともこの現象は世界中で起こっており、インドなどでは「 タンキュー tank you 」というのも聞かれる。書類を fax で送るときこの単語を英語式に a+e の音、つまり「ア」と「エ」をつき混ぜたような音で発音する日本人はほとんどいないだろう。実際に発音しているのは fuck(s) (性交する)にむしろ近い音である。
もっと発音の違いについてきちんとした訓練を施す必要がある。「英語戦争」という本でも言っていたが、hot / hat / hut の発音の違いを正しく教える日本人の先生が中高校にどのくらいいるだろうか?この3つがすべて「ハット」では・・・。
日本語には同音異義語が多いからあまりこういう違いに敏感ではないらしい。たいていは文脈で理解できるだろうとたかをくくっている人々が多い。なにしろ「ダジャレ」がお笑いの大部分を占めるお国柄だから。
振り返ってみれば漢字の音は、もとは中国語の発音であった。それが今「音読み」などといわれているが、実際の中国語の音とはすっかり違ったものになってしまっている。このように外来語はそれぞれの国語に都合がいいように、すっかり変容されてしまうのである。
初稿2007年5月
再び諸言語を二つに区分する****語順優先言語と標識優先言語
よく言語を分類するとき、SVO型とか、SOV型というようなことが言われるが、それは何が次に出てくるかというだけで、たいした問題ではない。V を前のほうに置くか後のほうに置くかは一種の”好み”であって、もっと大事なそして歴史的な経緯を背景に持った着眼点が存在する。
<標識優先>とは主語、動詞、目的語、属詞(補語)など文の欠かすことのできない要素だけでなく、修飾のための語についても、それぞれの働きが何であるか一目でわかるしるしをつける形式をいう。この”しるし”は語の前のこともあれば、語のうしろのこともある。音声の場合にはつながって聞こえても、文字にした場合にはそのしるしは単語とくっついて記述されるものもあれば分離される場合もある。
語尾につくしるしが前にある語と”分離”して記述される場合にはこれを<後置詞>とよぶが、形の上では<前置詞>と対比される存在である。標識優先言語は比較的古い言語、都市化の波から離れた場所の言語、たとえばラテン語、そして現代ロシア語などに色濃くのこっている。そしてわが日本語も”助詞”と呼ばれる後置詞によってこちらのグループに属するといえる。語順優先の言語と違って、単語の置き場所がかなり自由である。
これに対し、<語順優先>とは、主語、動詞、目的語、属詞など、文の欠かすことのできない要素について、厳格な順番を決め、そのルールをはずれた文の作り方をすると文として意味をなさないような形式をいう。都市化や貿易などで異民族との交流が活発になって発達した言語に多く、外国人にとって学びやすい。現代英語がそのもっとも典型的な例である。
ただし、語順優先の原則は形容詞や副詞のような修飾のための語にまで及んでいるとは限らない。というのも修飾語は強調したり非修飾語との関係によっていろいろなおき方ができないと、文が硬直してしまうからである。英語では標識優先である前置詞が発達し、語順優先の骨組みのまわりをやわらかく包み込んでいる。
いうまでもなく両者にはそれぞれの長所、欠点がある。しかし一方の長所が他方の短所になるというような具合で、どちらが優秀か効率的か、について安易に軍配をあげるのはむずかしいようだ。しかも言語には単なる文法解釈ではおさまらない、文化的背景というものがひかえているわけで、それを話す一人一人の人間のアイデンティティを決定するほどの重みを持っていることを忘れてはならない。
初稿2008年2月にんげんの話すことばは、その意味や機能を変化させるたびに語の形態を変化させることを行ってきた。世界の言語(のすべてというわけにはいかないが)を見回すと、そのほとんどがある単語のまとまりの最後、または最初に来る部分を変化させている。もちろん調査すれば”中央部”を変化させる例もきっとあるであろうが、多数派は語尾変化のようである。なぜだろうか?
ある単語の最後の部分が何らかの記号になるとき、それを<接尾辞>という。また先頭の部分であれば<接頭辞>である。音声認識の観点からすれば、まずある単語である”意味”を確認してから、そのあとで特有の”機能”を知るほうが順番としては効率的であろう。
音声認識といったが、すべての言語は最初は文字のない状態から発生している。音声は時間の経過にしたがって発していかなければならず、視覚認識のように同時に行う芸当ができない。このため”順番”の厳守ということがもっとも大事なことになる。また、文字がその接辞とつながっていることを示すために、おそらく続けて、あるいは一息に読まれることであろう。
問題は文字の発明によって複雑化した。おそらくラテン語、ギリシャ語、サンスクリット語の文字の発明者たちは、支配者によって与えられたその膨大な時間の中で、うんうんうなりながらいかにして言語を正確に文字化すればよいのかに全エネルギーを注いだことだろう。これらの言語では接尾辞が優勢である。
使用分類に応じて接尾辞の形は次々と変形を生み出し、変化の種類は天文学的に増えていったに違いない。しかも書き言葉は、話し言葉と違い、時間的な制約がないから記号の厳密化、精密化がいくらでも可能である。読むことのできる人間も限定されている。このようにしてたとえば、中世以後のヨーロッパの学生たちを死ぬほど苦しめたラテン語文法は成立したのである。
振り返って、それほどの厳密さを追求しなかった一般の諸言語では、語尾の表記法には二つの流れが生じた。ひとつは母体となる単語の後に続けて書く方法であり、もうひとつは<分かち書き>である。日本語なら、<は>を表記するときの「わたしは」と「わたし は」の違いのようなものだ。前者は接尾辞、助詞などと呼ばれることが多く、後者は付属語、後置詞と呼ばれることが多い。
これらは一見、重大な文法上の違いにみえるが、音声にしてみればいずれも同質のものである。実は、分けて書くか書かないかではなく、むしろどんな品詞と結びついているかが重要である。接尾辞の部分を P とすれば、”動詞+P 、名詞+P 、主語+P 、目的語+P 、述語+P ”などの組み合わせが考えられる。中でも動詞の場合は普通分かち書きをしないから、不変部分を<語幹>といったりして後に続く部分と区別をすることが多い。
接頭辞についてはどうであろうか。世界的に有名なのはスワヒリ語であろう。この言語では動詞の前に”主辞、目的辞、時制辞”などの名前で、次々と分かち書きなしで追加される。慣れない者にとっては、同じ動詞でありながら最初の形が違うので戸惑ってしまう。
しかし音声認識にしてみれば、主辞というのは主語(人称代名詞)の代わりをしているだけだから、その特有の音を覚えてしまえば英語で I have , You have などといっているのと同じであり、時制辞に至っては、英語での助動詞や have動詞のことを考えればそう大きな違いがあるともいえないのである。英語の場合、助動詞は必ず動詞原形の前におかれるから、分かち書きさえしなければ、スワヒリ語とそっくりなわけである。
そして最も重要な方面は、<前置詞>であろう。後置詞とちがい、数多くのヨーロッパ言語、アラビア語、中国語で採用されているこの形式は、ほとんどすべてが後に続く名詞相当語句とは分かち書きであるが、これこそ接頭辞の王様である。ただしおもしろいことに、前置詞が使われる状況は主語、目的語のような基本構文関係ではなく、位置や時間などの副詞的表現に多いというのが全体の印象である。
前置詞を採用する言語が非常に多いところをみると、実は接頭辞と接尾辞との使用比率はあまり変わらないのではないかと思われる。全体を大雑把な印象で述べると、接頭辞方式は、ヨーロッパ言語において、助動詞、前置詞の名で発達し、、接尾辞方式では、トルコ語、朝鮮語、日本語など、いわゆるアルタイ語族とかつて呼ばれたグループでは動詞のみならず名詞においても多く採用されている。
このことから非常に大胆な仮説であるが、アフリカ人類発生の頃の言語ではほとんど接尾辞が優勢であったが、アフリカにとどまるか、ヨーロッパ方面へ移動した人類たちはこれに接頭辞方式を加えていった。一方ユーラシアをどんどん東に進み、アフリカから遠く離れた場所になればなるほど、古来の接尾辞優勢の傾向が変化せず現在に至るまで保存された、というのはどうだろうか?これは遠隔地に言語の古い形式が保存されやすいという考え方にヒントを得たものである。
2008年7月初稿
語順に注目するだが、各国語のさまざまな側面を見るうち、もっとも問題になるのは”語順”ではないかと思うようになった。これは改めて詳細を論じたいが、「雨が降るとき」と「 When it rains 」とを比較してみるとわかるように、日本語と英語のいわゆる”接続詞”の位置はまるで反対である。同様に「部屋の中に」と「 in the room 」とを比べてみよう。
動詞の順番に注目すれば「私は朝食を食べた」と「 I had breakfast. 」を見ればわかるように日本語では動詞が最後(ついでに否定後も最後)なのに対し、英語では動詞は主語の後が原則である。
形容詞、名詞、副詞、動詞のいわゆる”品詞”はどの言語でもほぼ共通になっている。ただ前置詞とそれに対応する後置詞、前におく接続詞とうしろに置く接続詞、そして関係詞とそれに対応する連体形が、各国語によって大きな相違があり、英語のような SVO タイプ以外に SOV タイプやその他の並べ方がいろいろと見つかる。
動詞の分類、形容詞の分類、名詞における男性、女性の区別などはそれらに比べると些細な問題でしかないように思われる。なるほどスワヒリ語の変わった名詞分類などは最初目を奪われるが、覚えなければいけない語彙が増えるというだけ、ロシア語の”格”によるさまざまな語尾を持った名詞形も記憶の問題である。スペイン語の動詞活用もそれを覚えきるのになんと多くの学生たちが苦労していることだろう。
だが、それらは根本的な言語の問題ではないと思われる。それは音声の場合でも同じである。地域によって空気の乾燥度や気温が異なるのだから、発生の仕方がそれぞれに独特の進化を遂げたのも当然のことといえば言える。
これに対してなぜアフリカ中央部のあるひとつの箇所から発生したはずの人類がこんなに違うことばの並べ方をそれぞれ決めてしまい、それらは時代の進行にもめげず変わらずにきているのか。たとえば日本語と朝鮮語とでは語彙はまるで異なるのに、並べ方がほぼ同じだということは語順というのは非常に保守的なものであると察することができる。その頑固に変化を拒むはずのはずのものがなぜ人類の最初の段階でこんなに異なる形にそれぞれ定着してしまったのだろうか?まさにこれこそが文法の最も根源的ななぞなのではないかと思う。
2009年4月初稿一つの言語における単語の数は多ければ多いほどいいのか?高度な文明だから数が多い、というわけでもなさそうである。日常生活を営むためには必須の語というのは当然存在するが、各言語集団の日常生活を探ってみると、分野ごとに非常なばらつきがあることがわかる。
フランス語では、「彼を知っている」、と「その事実を知っている」では、同じ”知る”を使いながら、使う動詞が違う。前者は”connaitre”であり、後者”savoir”である。なぜこのような違いを作っておくのか?それは区別すべき理由がある、つまり、区別するほどに関心が深いからである。
細分化された単語の例として、言語学の講義では必ずといっていいほど、エスキモーの例が引き合いに出される。というのも、彼らの雪という単語には世界中が驚くほどの多用な命名がされているからだ。降ったばかり、翌日の固くなった雪、連日の寒さでほとんど氷になった雪、春めいた天気のために溶け出した雪、もういまや消えようとしている雪、それぞれにちゃんと命名がされているのだ。
これを聞いて熱帯に住む人々は、まるで理解できないであろう。彼らの周囲に雪はないからだ。生活にまるで雪は関係がない。だが、エスキモーにとっては雪は生活のほとんどのあらゆる側面にかかわる重大な出来事である。そのため自然に雪についてもさまざまな名前が生まれてしまったのだ。ちょうど熱帯の人々にとってマンゴーの種類が重大な意味を持つように。
再びフランス語に話を戻すと、知るについてこのような区別をするところを見ると、彼らは事物と人間の区別にかなり関心があるようだ。これに対して日本人は同じ”知る”で済ませているのだから、もしかしたら事物と人間の区別に関心が薄いか、あるいは人間そのものに関心が薄いのかもしれない。これは社会学者や人類学者にとって重大な問題になるかもしれないのだ。
2009年8月初稿
The news surprised me. が言語分布を解く鍵かも・・・
英語では、大部分の動詞が、人を主語に、モノを目的語に持つ。 I speak English / Mary took the unbrella / They drank coffee などなど。だが、 surprise に代表される動詞は「わたしがニュースに驚く」ではなく、「ニュース(主語)がわたし(目的語)を驚かせる」という形をとる。このように”逆転”した構造の存在は注目に値する。
このように、外界の働きかけによって人が影響を受ける図式は、動詞表現の中では少数派に属し、たとえば日本語を母語とするような人々にとっては奇異な表現にうつる。だが、これはおそらくこのような表現を作り出した人々にとっては、自然観察の結果による論理的な帰結だったに違いない。しかもそれが滅びることなく、現代に至るまで受け継がれている。
この表現形式は、英語だけに見出されるのではなかった。フランス語、スペイン語といった近隣諸国だけでなく、かなり言語的には遠い縁と思われるロシア語にも、そしてアラビア語にも存在するのだ。これは単なる偶然だろうか?
これらの英語も含めた5つの言語をみると、いずれも SV を中心とした文の構成や、関係詞、接続詞、前置詞における使用法がよく似ている、いわゆる”西欧言語”的な共通点があるのだ。一方、トルコ語、日本語、朝鮮語にはかつて”アルタイ語族”と呼ばれていたような、類似点の多い言語であるが、surprise タイプのような使用法は見当たらない。
文法構造は、語彙や発音の変化と違って、時間の経過における変化が極めてゆっくりであるから、”西欧言語”の共通点の一つとしてこの surprise タイプを挙げ、共通の祖先を過去にたどることができそうだ。つまり、アフリカ東北部あたりに発生した人類の一部が、一つの移住先としてアラビア半島、そしてユーラシアの東部を選んだことが、現代における多様な言語の中で、一つの共通点を求めることができるのではないか。と同時に、surprise タイプを持たない言語集団と異なる地域での発展を遂げたことが想像できるのではないだろうか。
2010年7月初稿![]()
© 西田茂博 NISHIDA shigehiro