
ここより 2003年
@だからアメリカは嫌われる * 忠平美幸・訳 * 草思社 * The Eagle's Shadow; Why America Fascinates and Infuriates the World by Mark Hertsgaard * January 15, 2003
 ビート・たけしの本に「だから私は嫌われる」という本があったが、この本の原題は「鷲の影」、つまり「アメリカの影響下に」といい、サブタイトルは「なぜアメリカは世界を引きつけ、また怒らせるのか」となっている。
ビート・たけしの本に「だから私は嫌われる」という本があったが、この本の原題は「鷲の影」、つまり「アメリカの影響下に」といい、サブタイトルは「なぜアメリカは世界を引きつけ、また怒らせるのか」となっている。
前に読んだ、マイケル・ムーアの「アホでマヌケなアメリカ白人」と同系統の本であるが、ジャーナリストである著者はだいぶ抑え目に、そして客観的に書こうとしている。だが、実際はアメリカの傲慢さ、アメリカ人の無知さ加減に相当うんざりしていることが、行間ににじみ出ている。
目次
- 世界を知らないアメリカ
- 豊かさが犠牲にしたもの
- 本当に自由の国なのか
- アメリカ「帝国」がしてきたこと
- 堕落したメディア
- 行きすぎた「ドル」信仰
- 失われたアメリカン・ドリーム
- アメリカ民主主義の悲喜劇
- 心の植民地化
- 9:11をどう超えるか
特にこの本で、注目すべきことは、第5章にあるように、アメリカのメディアのどうしようもない実態である。我々はアメリカは、3権分立が見事に機能し、さらに加えて自由な報道機関が、「第4の権力」を行使して、理想的なバランスにある、と思い込んでこなかったか?
だが実際は政府と企業にすっかり飼い慣らされ、御用機関となり、国民にはくだらないカスのようなニュースが止めどなく流すが、肝心のことは伝えない、バランスよく反対意見を採り上げない、という偏った報道方針が目に付くようになってしまった。というよりはずっとそうだったのだ。
しかも、本来なら小さな独立機関であるべきの報道機関は、レーガン大統領以来の規制緩和政策によって、次々と合併を繰り返し、巨大な多国籍企業に変わり果ててしまったのである。無数の記者たちの言動は、そのトップの者たち、そして政府の権力をつながりを持っている者たちの意向が反映するのは当然のことである。
そういわれてみれば、ベトナム戦争の場合でも反戦運動がとてつもなく激しくなるまでは、ずっと政府の戦争政策を黙認していた。「黙認」ということは、全面的な賛成に近い。そしてあの悪夢のようなマッカーシー旋風と、赤狩り。
国全体がヒステリックになれば、あえてこれに反対意見を唱えるものは少なくなる。本来ならそのような場合に勇気を持って別の角度からの考えを堂々と主張するのが報道機関の務めのはずなのだが、それが実際に行われた場合が実に少ない。
今回の同時テロのあとでも同じことで、ブッシュ大統領のテロリストへの復讐と壊滅宣言だけが、大々的に取り上げられ、これに疑問を示す者たちは激しく非難された。結局、「愛国的」でなかったり、「非米国的」であるものは、この社会ではすぐに排斥されるのだ。ここでは「ある範囲内」での民主主義しか存在しない。
著者は、世界中を旅行して、アメリカに対する意見を聞いて回る。確かに映画や音楽、ファッションなどには強烈なあこがれが存在するが、ファスト・フードのような画一化の波は、それぞれの文化を破壊する元凶だと憂慮する声はあるし、グローバリズムの名の下に、アメリカが自分の利益確保に奔走していることは、多くの人々から指摘されている。
アメリカ人は世界中から知られ、注目されているが、自分たちは世界のことを少しも知らない。いい加減なメディア、英語以外の言語を軽視した教育、欠陥だらけで、必要なことを教えない歴史教育、こんな中で世界最強の軍事力だけは持っているのであれば、誰でも危惧の念を感じずにはいられないだろう。
@土は生命の源 * 岩田進午 * 創森社 * February 05, 2003
 土は地味な存在だ。だが、地球が生まれて気が遠くなるような時間の間に、営々と土は作られ植物はもちろん、動物もその命を支えてもらっている。
土は地味な存在だ。だが、地球が生まれて気が遠くなるような時間の間に、営々と土は作られ植物はもちろん、動物もその命を支えてもらっている。
土は、単に岩が砕けて粉になったものではない。単なる砂とも、粘土とも違う。なぜならその中にさまざまな有機物を含んでいるからだ。そしてその有機物を豊富に含んでいると、水持ちも水はけもよい、いわゆる団粒構造ができあがる。人の滅多に入らない森林のふかふかした土がそのいい例だ。
植物にとって理想の土とは、中に入っているさまざまな成分がバランスよく含まれていること、それらが相互作用を常におこない無数の生命現象を支えていること、そしてあらゆるものがミックスされた多様性を保っていることである。
ちょっと先の気象の予報が人間にとって手に余るのと同じように、土の中で起こっていることを予想することはもちろん、現状を分析することすら、とても無理である。そして太古の昔から土は環境が変わらない限り、動植物の遺体を取り入れて少しずつ肥沃になっていく。
誰も耕さなくとも、土中に張り巡らされた根が、モグラや鼠やミミズの掘ったトンネルが、空気を通し、中にうごめく虫や微生物を生かしている。いわば全く自動的にそれらは起こり、この地球を持続可能にしているのである。
だが人間の文明はこれをまったくめちゃくちゃにした。金儲け主義は、化学肥料、農薬、単一栽培と次々と土の環境を破壊し、取り返しのつかないことがわかっていながら、今日もその営みをやめようとしないのである。
@生物は体のかたちを自分で決める * 竹内久美子訳 * 新潮社・進化論の現在 * John Maynard Smith * February 9, 2003
 このわずか80ページの小冊子の著者は、半世紀にわたり進化論の流れを見つめてきた長老。最近のおもしろい発見としては個体発生の際にたとえば「眼」を作る指令(信号)は、動物であればどんな種類でもみんな共通であり、何億年もの間変わってこなかったらしいのだ。
このわずか80ページの小冊子の著者は、半世紀にわたり進化論の流れを見つめてきた長老。最近のおもしろい発見としては個体発生の際にたとえば「眼」を作る指令(信号)は、動物であればどんな種類でもみんな共通であり、何億年もの間変わってこなかったらしいのだ。
進化はわずかな突然変異がゆっくりと進むものであるから全体の変化はなくても、小部分(モジュラー)でのわずかな変化の積み重ねが長い年月には、大変化につながるのだという。だから指令は、急に変わってしまったりすると混乱をきたすので、動物界共通の言語としてずっと変わらずにきたのだ。
このため19世紀のある思想家の「すべての動物には共通の要素がある」という推論が現代の研究のお陰で期せずして正しいことになった。
さらに、生物の個体発生を考える上で、自然選択と、動的展開の二通りのアプローチがあるという。前者は、あらかじめ遺伝子の書き込まれている「指示書」(情報)の通りに細胞が機能分化をすすめていくとみなすもの。
後者では、いったんある反応が始まるとその勢いで、まるで気象現象のように次々と連鎖反応が起こり最後に目的の細胞が出来上がる(自己組織化)、とみなす。自己組織化はたとえば、二重ラセンが出来る際に、4つの物質がそれぞれお互いに求める物質を結びつけて、ひとりでに遺伝子が構成されてしまうような場合が考えられる。
おそらく最終的には両方の要素が融合するであろうが、当面の間それぞれの陣営で研究が進みそうである。
@女について * 石井正・立訳 * 角川文庫 * ショーペンハウエル * February 9, 2003
 このわずか80数ページの論文によって、この本は「女の敵」という烙印を押された。だが、誰がそんな名前をつけたのか知らないが、あまりにも軽薄なステレオタイプ化ではある。
このわずか80数ページの論文によって、この本は「女の敵」という烙印を押された。だが、誰がそんな名前をつけたのか知らないが、あまりにも軽薄なステレオタイプ化ではある。
この本では女性の一般的性格について赤裸に述べられているが、必ずしも従来の偏見に基づくものではない。男性と女性の違いは厳然と存在し、得意な分野もあれば不得意な分野もあるわけだから、それぞれについて明確に論点を明らかにすることは決して悪いことではない。
実際の内容は、観察力が普通にある人なら誰でも気づくことである。ただこの哲学者は、女権論者の攻撃をおそれて普通の人ではうまく口では言い表しにくいことを、得意の論理展開を使って、誰でもわかる形にしている。これを読むと日常生活の至る所で思い当たるところがあり、なるほどと溜飲が下がるだろう。むしろ様々な口にしたくない特徴を覆い隠すことによって、これまで男女の間に無数の悲喜劇が生じていたのだ。この小編は、まず結婚前で女性の本質について何も知らず、ただ女を抱きたいという欲望だけが先行している若い男性諸君に読んでもらいたい。
もしこれを読んで恐れをなすような男性であれば、もう女性に手を出さないのが賢明だと思うが、一方実体が分かった上で女性とつきあおうとする男性は、勇気と知恵を少しは手に入れたのだから、人生の様々な冒険に乗り出してくれればいいのだ。
繰り返すが、この小論は決して女性蔑視の本ではない。むしろ男女の摩擦を事前に防止してくれる様々な見識を提供してくれると言っていい。
どくとるマンボウ航海記 * 北杜夫 * 新潮社 * February 17, 2003
 航海記というタイトルは、何か胸がときめくものだ。まだ交通の不便だった時代に、はるばる海路を越えて見知らぬ国々へ向かうロマンと期待にあふれた気持ちで本を開く。船は地球の本当の距離を感じさせてくれる。
航海記というタイトルは、何か胸がときめくものだ。まだ交通の不便だった時代に、はるばる海路を越えて見知らぬ国々へ向かうロマンと期待にあふれた気持ちで本を開く。船は地球の本当の距離を感じさせてくれる。
それが、1959年で、若くして水産庁の漁業調査船の船医となれば、寄港する先々でどんな冒険が待っているのか胸が躍るのは当然だろう。日本を出てシンガポール、インド洋を越えて紅海、スエズ運河、ジブラルタル海峡を抜けてアフリカ西海岸を南下、再び北上して、ヨーロッパの北海岸の諸都市を巡って再び地中海に戻って日本に帰る。
一つには若さが未知のものと出会えるスリルがある。著者はもともと神経科医だが、しかも帰国後には神経を使いすぎたのか十二指腸潰瘍になる有様だが、ものを書く才能を存分に活かしてこの小編を書いた。また、この航海記を利用してゴキブリの目から見た作品、「高みの見物」もおもしろい。
1960年代に出版された当時、この本を読んで、船乗りになりたいとか、旅行家になりたいと思った若者が多数現れた。それもそのはず、敗戦の内向き志向を背負っていた日本人にとって、堀江健一のヨットでの太平洋横断のように、海外に目を向けるきっかけになったからだ。
しかも、今ではあたりまえになっているパック旅行やリゾート志向ではなく、本物の「旅」を含んでいる。スムーズにものごとが進まず、間違いだらけの旅行。見知らぬ街の雑踏の中に自分をうずめていく体験。言葉が通じないままに、訳の分からない食べ物を口にするスリル。そしてなんと言っても現代社会のように画一化が進んでいない、各国の多様な文化と人々に出会える体験。
残念ながら、21世紀は、旅の喜びが急速に消滅している。どの街に行ってもコンビニがあり、交通渋滞があり、アメリカ映画を上映する映画館があり、ファストフードの店が軒を並べるようになってきた。皮肉にも「便利」と「快適」が旅を殺している。急がないと、記念碑や銅像や建造物しか見るものがなくなってしまう。
フィクションなら「ドリトル先生航海記」があるが、「マンボウ」以外に、日本人の旅ではなんと言っても沢木耕太郎の「深夜特急」、小田実の「何でも見てやろう」、堀江健一の「太平洋ひとりぼっち」と本当の旅を感じさせてくれる作品は少ない。みんな若者の新鮮な目で満た世界だ。しかもどれもグローバル化がまだ進んでいない時代に書かれた。もう多様性は進む一方なので、このような作品ができることはもはやない。
@農業は人類の原罪である * 竹内久美子訳 * 新潮社・進化論の現在 * March 05, 2003 (再)2017/07/26 * Neanderthals, Bandits and Farmers -- How Agriculture Really Began by Colin Tudge
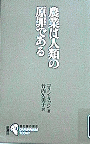 農業は、人類を支える上で今では欠かせないものになっているが、もとはと言えば、長い狩猟・採集生活から革命的な変換を経て、成立したのである。
農業は、人類を支える上で今では欠かせないものになっているが、もとはと言えば、長い狩猟・採集生活から革命的な変換を経て、成立したのである。
一般の人は農業と言えば、自然の中で営まれる、というイメージが強いが歴史の長い目で見ると、まったくその逆と言ってよく、絶えず自然環境を駆逐破壊することに力が注がれてきた。
それまで人類は、植物の栽培は狩猟採集の片手間に、つまり今で言えば庭いじりの程度しかやっていなかった。だが、今のペルシャ湾にあたる場所の豊かな森林が氷河期の終わりとともに海水の流入を受け、人々はイラン高原の方へ移動しなければならなかった。
幸い肥沃な土地と、今の小麦の祖先など、栽培植物にも恵まれ、ここで急激に食糧の生産高が増大したのだ。これを誰でも結構なことと思うだろう。ところがそうではない。これによって人口が急に増え、この人々を支えるために、一層の増産が要求されることになった。
農業は働けば働くほど、つまり管理を厳しくし、肥料をたくさん入れ、病虫害が起こらぬよう、ほかの植物に侵入されぬようにすれば、どんどん生産高が上がるが、その分だけ農民は過酷な労働を強いられることになった。しかも狩猟採集生活ではバランスのとれていた栄養が、穀物だけに片寄りがちになってしまった。
かくしてメソポタミアには都市が誕生したが、おかげで農民たちは労働強化の悪循環にしっかりと組み込まれ、そのうちに土地は疲弊して砂漠となり、食糧不足は他の国との戦争を開始させることになった。人類は、地球上の農耕可能な地に広がっていったが、そのあとには不毛の砂漠を残し、現在では石油から作った肥料と農薬がなければ、一時も生きながらえることはできない。
これこそ、聖書の「創世記」に書かれている顛末である。エデンの園は、今のペルシャ湾の海底にあった。アダムとイブは最初の本格的農耕民であり、それまでの狩猟・採集生活から訣別した。だが、そこから得られたものは都市の繁栄と引き替えに、人生の苦しみ、汗みどろの労働生活であった。これで農業が人類にとっての原罪となったのである。
 (2017年)農業が現在の人類の繁栄をもたらしたというなら、それは本当だ。しかし、人口が100億人に迫り、世界各地で動植物が次々と絶滅し、地球温暖化がますます深刻になり、紀元前に始まったメソポタミアでの“土いじり”がどんな結末を産もうとしているのか次第に明らかになってきている。
(2017年)農業が現在の人類の繁栄をもたらしたというなら、それは本当だ。しかし、人口が100億人に迫り、世界各地で動植物が次々と絶滅し、地球温暖化がますます深刻になり、紀元前に始まったメソポタミアでの“土いじり”がどんな結末を産もうとしているのか次第に明らかになってきている。
「自然に干渉しない農業」などは現実にありえないが、ニューギニア、東アフリカ、アマゾン川流域などにこれまで暮らしてきた原住民たちの“農業”を見れば、エネルギーと技術を極限まで使いまくる現代農業の「持続不能」の実態と、彼らがこれまで数千年、いや数万年続けてきた「持続可能」な農業の違いを、今こそしっかり見つめなおすときが来ているだろうし、今そうしなければ人類に22世紀はないだろう。
子供の科学流ー手づくり食品 * 増尾清 * 誠文堂新光社 * March 10, 2003
 もう70年ぐらいも「子供の科学」という雑誌を出している会社がある。鉄道模型、自然観察、科学実験と、今のようにゲームをはじめとして何でも高度に進歩してしまう前のエキサイティングな世界を少年たちに紹介してくれた雑誌だった。
もう70年ぐらいも「子供の科学」という雑誌を出している会社がある。鉄道模型、自然観察、科学実験と、今のようにゲームをはじめとして何でも高度に進歩してしまう前のエキサイティングな世界を少年たちに紹介してくれた雑誌だった。
子供がどんな訓練を経て成長するのがいいかについて一定のスタンスを持っている会社だから、その出版物は大変に魅力があふれている。切り抜く直前のボール紙を本にして売っている紙飛行機入門などもある。
この手づくりと銘打った食物の作り方の本も、今の大量生産大量消費で、出来合いのものしか知らず、昔の人が知恵を絞って作り上げた発明の結晶だということも想像だにできない子供や大人だらけになってしまった日本社会には、ぜひ読んでもらいたいものだ。
豆腐、味噌、たくあん、梅干し、手打ちうどんといった伝統的な日本的食品から、ヨーグルト、トマトピューレ、マーマレード、ビスケット、ババロアという洋風なものに至るまで、全部で34品目の作り方が興味深く、だが子供でも楽しみながら作れるように易しく書いてある。
解説部分には、大量に生産していくために、保存料、着色料、その他さまざまな名称の改良材を食品にぶち込まなければならない現実を、事あるごとに説明している。手づくりの良さは、本当に必要な素材だけで作れることだ。
もっとも、今の子供たちがこの良心的な本を喜んで買い、作り始めるとは思っていない。ごく一部の子供たちは別として大多数は、コンビニでおにぎりを買い続けるだろうし、なんと言ってもその母親たちが食べ物に手をかけることをとっくの昔に放棄しているからだ。
@だから私は嫌われる * ビートたけし * 新潮社 * March 11, 2003
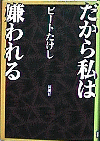 彼が映画製作に励むようになったのも、この本に山ほど書かれている自分の考えを何らかの形で表現したかったためなのかもしれない。
彼が映画製作に励むようになったのも、この本に山ほど書かれている自分の考えを何らかの形で表現したかったためなのかもしれない。
この本の内容は、雑誌の連載をまとめたもので、書かれたのはバブルの最盛期あたりだ。今読むと、当時の金に狂った日本の世相がよくわかるし、彼の予言も良く当たっている。
このあと、続編の本を何冊か出しているが、これもいずれは読んでみるつもりだ。歯に衣着せぬとはまさにこのことで、本当のことをいう人間は「暴論」を吐くというわけで、どんな時代でも嫌われたものだ。
自分の持つ価値がなんだかわからずに人について行くだけの薄っぺらな世相はいつになっても変わらない。だから、常にこんな種類の本が必要とされるのだ。
美味しんぼの秘密 * 佐藤世紀 * データハウス * March 11, 2003
 いつの世にも大ファンはいるもので、その人たちは自分の好きなものはとことんまで研究する。この著者も、大河漫画「美味しんぼ」を徹底的に読み込み、さまざまな研究成果を発表している。
いつの世にも大ファンはいるもので、その人たちは自分の好きなものはとことんまで研究する。この著者も、大河漫画「美味しんぼ」を徹底的に読み込み、さまざまな研究成果を発表している。
この本が書かれて時点では、このシリーズはまだ50巻で、これから100巻を越えていこうとしているので、さらに続編を書いてもらわねばならないが、ここまででもさまざまな分析がなされている。
登場人物のグループ分け、ストーリーパターン、最盛期と停滞期、人気のある話とそうでないもの、ヒロインや特色ある人物についての考察、と盛りだくさんだ。
こんなに長い間人々に親しまれ、ネタが尽きることもなく、食物についてのうんちくを中心とした話を続けられてきた、制作者と漫画家のコンビの秘密に迫る。
それぞれのストーリーに関しては、・・・巻・・・話と明示されているから、当該箇所をきちんと読み直してみるとますます興味深い。
@食品の研究 * 晶文社 * 北濃秋子・訳 * Can You Trust a tomato in January? by Vince Staten * March 29, 2003
 日本語タイトルから見ると、ごく普通の食品についての調査と思うかもしれない。だが、原題を訳すと、「1月のトマトなんて信用できるかい?」となる。これなら、食品「産業」の実態についての暴露本だとわかる。
日本語タイトルから見ると、ごく普通の食品についての調査と思うかもしれない。だが、原題を訳すと、「1月のトマトなんて信用できるかい?」となる。これなら、食品「産業」の実態についての暴露本だとわかる。
ところがこの著者のヴィンスさんは、まったく平凡な一アメリカ市民になりすまして?ごく普通のスーパーに奥さんのお供をして買い物をする設定となっている。どこから見てもごく当たり前の買い物をさりげなくやってゆくわけだ。
ところが、アメリカならどこにでもある巨大スーパーの通路(どこに行ってもほとんど同じ構成)を順番に歩きながら、スーパーに売られている食品の歴史、製造法、添加物について次々と懇切丁寧な説明を試みる。
それまでの小さなパパママ・ストアーを駆逐して、車で一週間に一度買い物出かける習慣は、そこに売られている食品に大変な変化を引き起こしたのだ。それが良い方向に変わったとは誰も思うまい。当然のことながら普通の工業の生産方法が人間の口に入るものにも適用されることになったのだ。
しかも化学物質の中には、インチキ食品を作り出すものも数多く含まれている。腐りかけているのに新鮮に見せるとか、本物が入っていないので、その代わりに香料と調味料でまったく同じ味を作って客を騙すという手口だ。
より安いもの仕入れるために、遠距離を運ばれてくる生鮮物。鮮度を保つための薬、品種改良、輸送にかけるコスト。ものぐさなアメリカ人はさらに、加工食品に頼るようになった。これなら冷凍、缶詰、瓶詰めのほかに保存料をまぶして長持ちさせるなど、最初に生産されたものとは似ても似つかぬ形に変形されて客のもとに届く。
1年に300個以上の卵を生むニワトリとか、黄色い着色をおこなって美味しそうに見せる鶏肉とか、消費者が「便利」な食生活を営む以上、代価を払わねばならないのだ。そしてほとんどの人々はそのライフスタイルを受け入れている。というよりもこの巨大な生産機構の中に組み込まれている。
1月のトマトが旬でなく、まともな作り方をしているはずがないのだが、それに敏感に反応する消費者はほんの一握りだ。たいていの人々はそれが当たり前になってなんにも疑問を抱かない。
著者は皮肉のつもりだろうか。すっかり一般消費者になりきっているから、反自然的な食品が作られている様も淡々と語り、その判断はすべて読者に任せているようだ。面白くこの本を読んでいるうちに実態を知ってコワーくなるのを密かに待っているのかも。
私の愛する憩いの地 * 兼高かおる * 新潮文庫 * 2003年04月21日
 兼高かおるは、1959年から31年間テレビの「世界の旅」に出演し、世界中を回った日本でも指折りの旅行家である。その彼女が振り返って様々な思い出の地の中から、ある程度海外旅行をした熟年以上の人々にお勧めのスポットを案内している。
兼高かおるは、1959年から31年間テレビの「世界の旅」に出演し、世界中を回った日本でも指折りの旅行家である。その彼女が振り返って様々な思い出の地の中から、ある程度海外旅行をした熟年以上の人々にお勧めのスポットを案内している。
紹介されているのは全部で29カ所と、温泉案内。いずれも想像を絶するような苦境を飲まず食わずの旅をするような場所ではなく、誰が行っても思い出に深く残るような「文明化」された場所である。ただしこの中には北極や有名な河川の水源巡りも含まれている。
兼高かおるは、昭和3年生まれだから、決して若い世代の仲間ではないが、その海外体験によって得た考え方や感じ方は、かなりリベラルである。が一方ではパイのぶつけ合いについて、食べ物をおもちゃにするのは大嫌いだと、はっきり私見を述べているのがさわやかだ。
彼女の文体にはとても特色がある。決して長い文を書かない。せいぜい半行から一行どまり。いわゆる副詞節や連体修飾がきわめて少ない。それでいて文が単純かというとそうではなく、次の文と続いて見事な内容を表現している。面白いユニークな書き方で、紀行文のお手本としたい。
30年も世界を回っていると、その変化が本当に身に迫ってくるのだろう。最初の10年は人々が建設に希望に燃えていた時期。次の10年は、人々が物質主義に浸って次第に疑心暗鬼になってきた時期。そして最後の10年は破壊の時期だという。
旅の最初の頃にあった人々の純情さや素朴さは次第に失われ、生活水準の向上と共に大切なものが次々と失われてきたということだ。日本で起こっていることが実は世界規模で進んでいるということだろう。もちろんそれに伴う環境破壊、自然破壊が常につきまとう。旅は急いだ方がいい。それが失われてしまわないうちに。
@シンデレラがいじめられる本当の理由 * 竹内久美子・訳 * 新潮社・進化論の現在 The Truth about Cinderella--A Darwinian View of Parental Love; Martin Daly and Margo Wlson * 2003年04月22日
 「農業は人類の原罪である」「生物は体の形を自分で決める」に続いて新潮社から出た進化論の本を取り上げる。この人目を引くタイトルは、一部のサルなどに見られる「子殺し」から端を発している。
「農業は人類の原罪である」「生物は体の形を自分で決める」に続いて新潮社から出た進化論の本を取り上げる。この人目を引くタイトルは、一部のサルなどに見られる「子殺し」から端を発している。
子供を連れた母親ザルが、死別離別によってほかの新しいオスザルと一緒になると、そのオスザルは「前夫」によって生まれた授乳中の子供たちを皆殺しにしてしまう。
この事実が観察されたとき、学者たちは解釈に困った。幾多の紆余曲折を経た後にようやくまとまった、現在の見方は人間の道徳観念を超越した、自然の掟を再認識させるような内容である。
最も大きなコペルニクス的転回といえば、「進化とは種全体の繁栄のためにある」という考え方が根本から覆されたことであろう。その種が滅びないように、どんどんその勢力を増すようにという力がその種全体に働いて個々の生き物は行動し、種が生き続けてゆく・・・そういう見方を否定しなければならないことが判ったのだ。
オスザルが「継子」を殺すのは、自分自身の遺伝子コピーを一刻も早くこの世に出すためだ。子供が授乳中だと、メスザルは妊娠しない。子供たちが離乳するまで自分による新しい子供を新しい夫は待っていなければならない。だが悠長に待っているわけにはいかないのだ。いつなんどき自分や妻が死んでしまうかもしれない。自分のコピーを残すのに一刻も猶予は許されない。
自然界に働く、コピーを残そうというこの強烈な力はすべてを動かす。そのためには幼い命を残しておくわけにはいかないのだ。だが、この摂理は人間にも作用しているようだ。シンデレラの物語と同じような民話が世界中に存在し、義父による継子殺しとまではいかないまでも、継子いじめは非常に高い割合で、世界のどこにでも普遍的に見いだされるという。
人間社会のうち立てた倫理の観点からはとうてい許されないことなのだろうが、社会の中の複雑な諸要因を考慮しても(そのためにこの本では大部分のページがさかれているが・・・)、社会的制裁があるために実際に子殺しまでゆくケースはまれだとしても、継子がいじめられる事実は避けて通ることができないのだ。
人間も含めて自己の遺伝子のコピーを後世に残そうと必死で競争する自然界。この競争の中から驚くべき多様性や、優れた資質が誕生してきたのだろうか。
アダム・スミスの言った「見えざる手」がそれぞれの個体に働きかけ、それぞれが潰し合いの利己的な競争に邁進しているように見えて、実は全体を見通すと、より多様化して安定したシステムができあがっていくのかもしれない。
カレーライスがやってきた * 大塚滋 * 朝日文庫 * 2003年04月29日
 サブタイトルは「日本食べ物事始」である。こんにち、飽食で知られる日本国であるが、食糧自給率の低下にもお構いなく世界中から食物を輸入してどん欲に各国料理を味わっている。
サブタイトルは「日本食べ物事始」である。こんにち、飽食で知られる日本国であるが、食糧自給率の低下にもお構いなく世界中から食物を輸入してどん欲に各国料理を味わっている。
そうなのだ。日本料理の独自性は言うまでもなく、明治維新と太平洋戦争終結の2回のきっかけを利用して、日本人は世界中の料理の中から、自分たちに合いそうなものを選び、しっかりと自分たちのものにしてしまった。
食べ物の好みは保守的だと言われる。それぞれの国の中での料理は大きな変化はあまりない。だが日本に限って、その取り入れ方は群を抜いている。その代表格がカレーライスというわけだ。
すでにインド人の作るカレー料理とは全く違った作品を生みだしてしまった。あんパンといい、肉まんといい、次々と魅力ある食材や料理を取り入れた上で、それを独自なものに変化させてしまった。
この本はそうやって日本の風土にすっかりなじみ、稚内に住む漁民が旧ソ連の抑留から帰ってきて、カレーライスが「ふるさとのアジだ」を言わしめるほどにすっかり日本化した食品について解説している。
その種類が実に多い。この本では31種類が取り上げられている。振り返ってみれば寿司も豆腐もかつては外国から入ってきたものだ。だが発祥の地ではそれほど発展せず、日本に来てそのセンスが磨かれた。
この本は、独自な料理のできあがる過程を詳しく調査し、その歴史的な流れを追う。読後に腹が減れば、何か印象に残った料理を食べたくなること請け合いだ。
ことばのエコロジー * 田中克彦 * ちくま学芸文庫 * 2003年05月12日
 世界の言語は3千とも1万とも言われているが、グローバル化の進行によって、その数が急激に減っているのは本当だ。それは、一民族が一国家を作る場合ならまだしも、一つの国家が複数の民族を抱え、その国内では、国家語を制定して、それ以外の言語を従属的地位に置いているからだ。
世界の言語は3千とも1万とも言われているが、グローバル化の進行によって、その数が急激に減っているのは本当だ。それは、一民族が一国家を作る場合ならまだしも、一つの国家が複数の民族を抱え、その国内では、国家語を制定して、それ以外の言語を従属的地位に置いているからだ。
それが方言の場合はさらに悲惨である。中央放送局が日夜流す「標準語」によって人々の日常生活から、どんどん昔懐かしい訛が消えていくのである。
弱小言語は、その地域で通用し、人々のコミュニケーションに役立ってはいても、若者が成長し大学にはいるとき、その言語では入学できないというのが、これらの言語の最大の弱点とされる。
人々は田舎から都会へと流入し、若者の進学率が高まれば高まるほど、これらの言語の影響力は衰えていく。この動きはもう止めようのないものだろう。
しかし、言語は人々にとって血液のようなものである。消えゆくからといって簡単に入れ替えるというわけにはいかない。その表現、文法には、土地や風土に根付いたそれぞれの実に個性的な違いがあるのだ。
本来言語は、自然界における動植物におけるそれのように、互いにニッチを確立して、共存すべきものなのだ。「エコロジー」のタイトルはそこから来ている。
かつてソビエト連邦が成立したとき、そこに加盟した各共和国は、それぞれの言語を、ロシア語と対等の地位にあるとされた。これは、人類の歴史の中でもきわめて珍しい現象である。普通は最も強大な民族によって言語が統制されるものであるからだ。
もちろん実際にはロシア語の天下になったが、それを明記した部分は、各国が自由に脱退できるとした部分と共に、ソ連崩壊までしっかりと残されていたのである。各共和国では、外部とのコミュニケーションとしてロシア語が広がったが、一方でその国内では、地元の言語が幅を利かしソ連崩壊後の現代に至っている。
中小言語が元気に今後も活躍するためには、どんな人間にとっても等距離の連絡用言語を開発し、すべての人類がバイリンガルとなればよい。残念ながら、エスペラントにしても英語にしても、ある特定の民族に有利である。あるいは万能翻訳機が出現するのを待つのがよいか。
細胞から生命が見える * 柳田充弘 * 岩波新書387・岩波書店 2003年05月22日
 生命の最小単位である細胞とはどんな働きをしているのか、どの程度まで判っているのか。人間も魚も、最初はたった一つの細胞から始まった。あとは際限なく分裂を繰り返してコピーを作ったのだ。
生命の最小単位である細胞とはどんな働きをしているのか、どの程度まで判っているのか。人間も魚も、最初はたった一つの細胞から始まった。あとは際限なく分裂を繰り返してコピーを作ったのだ。
細胞は、外界との境界としてシャボン玉のようものだ。内圧と外圧が微妙なバランスを取って一定の大きさを保っている。その調整にはカルシウムやカリウムの濃度を上げたり下げたりすることによる。
中心部にある核には染色体が収められており、その遺伝子情報は、人間から細菌に至るまで、かなりの部分が共通部品でできており、祖先が同じであったことをうかがわせる。
二重ラセンで有名なDNAは、巨大な高分子化合物であり、たった1個の人間細胞から引き出して延ばすと1メートルにも達するほどの長さのひもに膨大な情報がしまいこまれている。
DNAという設計図から、RNAに転写され、それが細胞の別の場所で、タンパク質が合成される。しかしその過程には、途方もない数の酵素やらタンパク質が関わっており、最終的な「製品」ができあがるまで、無数のステップを踏まなければならない。
その過程は細胞の他の機能でもそうだが、エラーが実に少ない。途中のステップにエラー発見装置やエラー訂正装置が何十にも関わっているからだ。
細胞の中は水だが、さまざまな物質が溶け込んでおり、内部間、内部から外部へ、外部から内部へと微少管のようなきちんとした「レール」が敷かれている。だから必要な物質は間違いなく目的地に達するようになっている。
細胞が分裂する際には、DNAがジッパーのような開き、そこに新たな文字が付いて、コピーが作られる。これも誤りがとても少ないのは、訂正装置が働いているからである。
一対のコピーが完成すると、細胞内の他の部分も二つずつできて、二手に分かれるように「ひも」で引っ張る。細胞分裂は一回に2つずつしかできないのが普通である。
細胞の一生は、分裂という点から見ると「不死」であるが、母細胞と娘細胞というように分けると、ガン細胞でない限りは母細胞には普通、寿命がある。また全体のためにじゃまな一部の細胞が「自殺」したり、数の調節は適宜行われる。
細胞の生活を単純に見れば、「刺激→受け入れ→反応」というようにかんたんに記述できるが、実はその間には数え切れないほどのスイッチが関わっており、短絡的な暴走を防ぎ、生物らしい行動を引き起こすためには、実に複雑なステップが備わっているのだ。
だから生物のスイッチは、途方もなく長い「将棋倒し」による最終目的達成であり、活動化させるスイッチももちろんあるが、今までしていたことを止めるためのスイッチも訂正や促進装置も用意されているのである。
スイッチの多くはタンパク質の「活性体」化、「不活性体」化に依存しており、それぞれの性質を引き起こすのに、それぞれに決まった物質が用意されている。
また、これほど膨大な種類のタンパク質やらアミノ酸やら酵素があるのに、ほとんどスムーズに相手に作用しているのは、それぞれ反応する相手との「適合性」が決まっているからである。
これはDNAのコピーを作るときに A|T,G|C というように結びつく相手が決まっていて、そのおかげで正確なコピーを作る原理と同じである。
こうやってみると、細胞内というのは、大気圏における気象と同じように、とてつもなく複雑な要素が動じ動き回っている世界であり、とうてい人智の理解を超えるように思えるが、一方では驚くべき統制で動いており、ある条件下では、決して予測不能な世界ではないらしい。
@クレオール語と日本語 * 田中克彦 * 岩波セミナーブックス77・岩波書店 2003年5月28日
 クレオール語とは、大言語のはざまに生まれた言語の混血児である。大きな国が、植民地化や占領によって、現地住民が生活の便宜のために作り出した新しい言語である。
クレオール語とは、大言語のはざまに生まれた言語の混血児である。大きな国が、植民地化や占領によって、現地住民が生活の便宜のために作り出した新しい言語である。
このような言語は19世紀の言語観によれば、「汚れた」「正当性の低い」「知的レベルの低い」「伝統のない」言語だとさげすまれてきた。だが、現在では一番最後の理由を除いては、おおかた撤回され、新しい研究の光が当てられつつあるのだ。
というのもクレオール語が、その原初的な形態である「ピジン」から発展していくさまは、人類がいかにして言語を獲得したか、いかにしてそれを「使える道具」へ変えていったかを知る重要なヒントになるものだからである。
たとえば、パプアニューギニアで発達した「トクピシン」では、現地の民族の諸言語と主に英語、さらにさかのぼってドイツ語の影響を受けて育った。そこには言語を簡素化して、使いよくするさまざまな工夫が生まれ、大言語にあった不規則な活用や困難な発音、そして無駄な文法構造が大胆に取り除かれた。一方で他動詞であることを示す語尾の存在など、実に興味深い。
これによってこの言語の質が低下したわけではない。それどころか、より文法規則が簡潔になることによって外部の人間の学習が容易になった。ザメンホフによるエスペラントも、この流れを人工的に作り上げたわけだが、トクピシンではこれを名もない大衆がいつの間にか作り上げていったのである。
そしてその最大の特徴は、総合的から分析的な方向への明確な流れである。つまりヨーロッパ言語に特徴的な屈折語としての特性を捨て去り、英語、中国語に見られるような孤立語的構造への流れ、そして「とりはずし」のきく文法的道具(前置詞、後置詞、助詞の類)ー膠着語タイプーのいっそうの発達である。
歴史の流れの中で、大言語がぶつかり合うたびに、クレオールが次々と生まれたのではないだろうか。それがいつの間にか人々に受け入れられ、高度な教育にも使用されるようになると、それは国民語としての地位を確立するようになるのだが、知識人たちによって文法規則や語法が確立され固定化するまでは人々の創意工夫が生かされるのだ。
世界の言語のうちどれが優秀でどれが劣等かを区別することはむずかしい。だが、クレオール言語のできる過程を研究することは、人類の共通な遺伝的特性である「言語操作」がどのような形で現れるかを知るのに、最適の手段となろう。
さらに日本語の生成過程を研究する上でも大きなヒントになる。日本語はアルタイ語族としての特性を多数持ちながら、それらとの近縁関係がはっきりとは示せないために、発祥不明の言語とされてきたが、これはもしかして太古の昔に東西南北から多種類の民族が気候のすばらしいこの日本列島で入り交じったために生まれたクレオール化のためかもしれない。
もしそうだとすると、ユーラシア大陸や、ポリネシアとはまた違ったスタイルの言語が生み出されたことになり、クレオール語としてみた日本語の性格がまた新たな特徴を明らかにすることになるのだ。