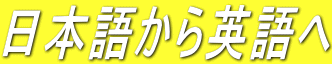第2章 基本構造
- すべての言語に共通する構造とは?
- <コラム>文法における品詞についての考え方
- 語順からみた言語
- <コラム>語順優先言語と標識優先言語
- 構造面からみた言語
- <コラム>他動詞と自動詞
- 文法カテゴリーからみた言語
日本語と英語の話に入る前に、世界の言語の大まかな姿を見てみましょう。気を見る前に盛り全体を見ておくと自分がどの位置にいるかよくわかり、進む方向もなんとなく見えてきます。
日本語と英語は構造がこんなに違う言語ながら、お互いに翻訳が可能だということは共通の要素を持っているからです。仮に宇宙人の言語が翻訳不可能だとすればそれはまったくそのシステムが人類語とは異なっているからであり、少なくとも地球上のホモ・サピエンス同士はお互いに通訳者や翻訳者を通じてコミュニケーション可能です。世界中のどんな言語を研究しても最低限、このような働きだけは確認できると思われるものをとりあげてみました。これらの知識は英語だけでなく、将来ほかの言語を学ぶ際に大いに助けになることでしょう。
![]() _
_
文法における品詞は、英文法でよく<8品詞>といわれるように、8つに区分されることが多いですが、同じ8つでも中身の2つぐらいが異なる場合があります。どこから目をつければいいかといえば、人類が言語を進化させたときの順番を想像しながら決めていくのがわかりやすいでしょう。
まず(1)”文の骨格”を作る部分に注目するべきでしょう。さらに骨格に肉付けする部分、つまりもっと内容を(2)”詳しく”する部分が加わります。さらに語彙数や文が増えてくるとこれらを結合しなければなりませんので、(3)”連結”のためのことばが必要になります。ほぼこれで文は完成ですが、文の中心である動詞はさらに細かい情報を追加する必要があり、名詞にしても長いものを何度も繰り返して使うのは大変ですから、骨格部分を(4)”補う”ものが必要です。以上、4つの観点から見ていきましょう。
(1)チンパンジーたちには名詞はあっても、動詞を使いこなすことができるか?これは今後の研究を待たなければなりませんが、動詞があるとここからいきなり言語が大発展を遂げることは間違いありません。人間言語の中心はなんといっても<動詞>です。<名詞>は歴史的に見れば、ものをさすだけのものとして動詞より以前にあったでしょうが、動詞の出現によって新たなる役割を獲得しました。つまり、主語、目的語、そして補語です。そしてその結果、文というものが誕生しました。(注1)
(2)名詞についてはこれをもっと詳しく示すために、<形容詞>が生まれ、名詞以外については<副詞>が生まれました。名詞とそれ以外に分けたのは、名詞が古くからある品詞であり、名詞専門にいろいろ説明を加えることは以前から定着していただろうが、副詞の用法については、比較的あとの時代、つまり動詞の誕生以後に生まれた新しいタイプと思われるからです。(注2)
(3)単語や文をつなぐ場合、同質のもの同士をつなぐときと、異質のものをつなぐときと2通りあります。また、2つをつなぐときはどちらが前でどちらがうしろかを決めておかなければなりません。また、つなぐための記号は文字にした場合、ある単語の(ア)接頭辞(イ)前に置く(ウ)接尾辞(エ)後に置く、の4通りが考えられます。このうち音声の場合には、(ア)(イ)のあいだと、(ウ)(エ)のあいだには、それぞれたいした違いはありません。これらを品詞として独立させた例としては西欧語における、名詞を主につなぐための<前置詞>であり、これは(イ)タイプに属します。もうひとつは文を主につなぐ<接続詞>です。こちらも大部分は(イ)タイプに属します。(注3)
(4)発展を重ねる動詞はさらに、時制や願望、現実・非現実などをあらわす必要があり、その記号は文字にした場合、ある動詞の(ア)接頭辞(イ)前に置く(ウ)接尾辞(エ)後に置く、の4通りが考えられます。こちらも音声の場合には、(ア)(イ)のあいだと、(ウ)(エ)のあいだには、それぞれたいした違いはありません。このうち、(イ)タイプを西欧語では一般に<助動詞>といっていますが、中には2つの動詞をただ連結しただけで、前の部分を助動詞のように扱っている場合もあります。一方、名詞はその語彙数がどんどん増え、1単語の文字数も多くなる傾向があり、日常会話においても支障をきたすほど煩雑になってきたことに伴って、もっと短く言う方法が工夫されていました。こうして生まれてきた<代名詞>は、単に名詞の代わりをするだけでなく、主語、目的語、補語の役割を果したり、ほかの名詞と区別するためにきちんとした体系が作られる必要ができてきました。(注4)
注1;現代のわたしたちも外国人を相手にしたとき、「本」とか「鉛筆」といった名詞をわからせることはできます。しかし、「ほしい」とか「あげたい」という気持ちを伝えるには、身振りや顔つきを総動員しなければできません。動詞の発明はその手間を省くものです。
注2;いくつかの言語では形容詞とそれが修飾する名詞は一致します。たとえば、名詞が女性名詞単数ならば形容詞も女性形単数形になるというように。ところが副詞については、そのような一致の法則はほとんど見かけません。一般に言語は都市化や文明の広がりとともに、複雑なルールが次第に簡略化される傾向がありますから、副詞のほうが時代的に後に発生した可能性が高いと推定できるのです。
注3;英語の場合でも(イ)のタイプが主流を占め、同様に「前置詞」、「接続詞」の名前で使われています。日本語の場合には(ウ)または(エ)のタイプが主流で、「助詞」の名前で使われています。他の言語では(エ)のタイプを「後置詞」という場合もあります。
注4;英語の助動詞は特によく発達したことで有名ですが、過去形には ed をつけるなど、(ウ)タイプも残っています。日本語では動詞とすっかり膠着(こうちゃく)しており、(ウ)タイプですがこちらも助動詞と呼ばれています。
言葉の基本はまず<音声>です。文字はあとから生まれました。音声は声として発せられると同時に次々と空中に消えていきます。ですからメロディの場合と同じく、聞き手の頭の中に時間的に連続したものがつなぎ合わされてできたイメージを作らなくてはなりません。そのためには発せられるものがデタラメに並んでいては困るわけです。ここに<語順>の重要性が浮かび上がってきます。
それぞれの文法体系の中では、これは名詞、これは動詞、これは形容詞、というように言葉の機能を示すのに何を使っているかをはっきり示さなければなりません。しかし、さまざまな言語を見ると、語順が厳しく決まっているものもあればそうでないものもあります。
たとえばラテン語を学んだ人はそれぞれの単語の<語形変化>の複雑さに閉口しますが(自分の記憶力に絶望して挫折する人も後を絶ちませんが・・・)、そのシステムのおかげで文をバラバラにしても、単語それぞれがどのような機能を持っているかが一目でわかるため、別に語順にこだわらなくとも全体の構造は聞き手に容易に理解されます。
ところが英語、その他国際貿易の中心地で生まれたさまざまな言語の混合体から生まれた、新しいタイプの言語(ピジン語・クレオール語)はたいてい単語そのものの語形変化は少なくて記憶の不得意な人にも気軽に使ってもらえるようなシステムになっています。しかしそれではそれぞれの単語の文法機能を示すには不十分となりますから語形変化の代わりに語順に重点をおくようになりました。つまり名詞のあとは動詞、動詞のあとはまた名詞、というように使い手が勝手に順番を変えられないように制限したのです。
ですから人類は自分の使う言語について、語尾変化を複雑にするか語順を複雑にするかのどちらかの選択を迫られたのです。ラテン語、ギリシャ語、ロシア語などは前者の方向に、英語や中国語は後者の方向を選びましたが、日本語は名詞のあとの助詞の使用(これを一種の語尾変化とみなすことができる)によって前者のコースのほうに傾いています。これまた英語と日本語を隔てる大きな要因の一つになっているのです。
よく言語を分類するとき、SVO型とか、SOV型というようなことが言われますが、それは何が次に出てくるかというだけで、たいした問題ではないのです。V を前のほうに置くか後のほうに置くかは一種の”好み”であって、もっと大事なそして歴史的な経緯を背景に持った着眼点が存在します。
<標識優先>とは主語、動詞、目的語、属詞(補語)など文の欠かすことのできない要素だけでなく、修飾のための語についても、それぞれの働きが何であるか一目でわかるしるしをつける形式をいいます。この”しるし”は語の前のこともあれば、語のうしろのこともあります。音声の場合にはつながって聞こえても、文字にした場合にはそのしるしは単語とくっついて記述されるものもあれば分離される場合もあります。
語尾につくしるしが前にある語と”分離”して記述される場合にはこれを<後置詞>とよびますが、形の上では<前置詞>と対比される存在です。標識優先言語は比較的古い言語、都市化の波から離れた場所の言語、たとえばラテン語、そして現代ロシア語などに色濃くのこっています。そしてわが日本語も”助詞”と呼ばれる後置詞によってこちらのグループに属するといえます。語順優先の言語と違って、単語の置き場所がかなり自由です。
これに対し、<語順優先>とは、主語、動詞、目的語、属詞など、文の欠かすことのできない要素について、厳格な順番を決め、そのルールをはずれた文の作り方をすると文として意味をなさないような形式をいいます。都市化や貿易などで異民族との交流が活発になって発達した言語に多く、外国人にとって学びやすい。現代英語がそのもっとも典型的な例です。
ただし、語順優先の原則は形容詞や副詞のような修飾のための語にまで及んでいるとは限りません。というのも修飾語は強調するほか、非修飾語との関係によっていろいろなおき方ができないと、文が硬直してしまうからです。英語では標識優先である前置詞が発達し、語順優先の骨組みのまわりをやわらかく包み込んでいます。
いうまでもなく両者にはそれぞれの長所、欠点があります。しかし一方の長所が他方の短所になるというような具合で、どちらが優秀か効率的か、について安易に軍配をあげるのはむずかしいようです。しかも言語には単なる文法解釈ではおさまらない、文化的背景というものがひかえているわけで、それを話す一人一人の人間のアイデンティティを決定するほどの重みを持っていることを忘れてはなりません。
次に具体的な構造上の特徴についても述べておかなければなりません。まず文をそれが構成する単語にバラバラにしてみます。単語の性質を分類すると、文法機能を持ったいくつか(たいていは8種前後)の<品詞>がみえてきます。これらはそれぞれの持つ機能や文中の位置によって見いだされた共通点をもとに作った”モデル”です。これらを組み合わせて言語が構成されるわけですが、その基本単位については次の7つの項目でその働きを確認して下さい。
(1)語・句・節
例文1;名詞を出発点にして (語)リンゴ→(句)リンゴを→(節)リンゴを食べた。
例文2;形容詞を出発点にして (語)赤い→(句)赤いリンゴ→(節)太郎から赤いリンゴをもらいました。
例文3;副詞を出発点にして (語)柔らかく→(句)柔らかく煮て→(節)母は豆を柔らかく煮てくれました。
言語構造はその複雑さのレベルに応じて3つに分類することができます。 一つまたは複数の音素を組み合わせた一つの固まり、つまり<語>が存在します。その中でもっとも基本的なものは実際の品物との対応関係を示すことからはじまった名詞です。名詞以外にもさまざまな機能を持った語が発生し、そのいくつかが結びついて新しい意味や機能を発揮するようになったのが<句>です。そして実際の行動や動きとの対応を示した動詞があり、句のさらに上の段階としてこの重要な単語を中心にしてできあがったさらに大きなかたまりが文または<節>です。
(2)名詞のはたらき
例文1;太郎(主語)はリンゴ(目的語)を買った。
例文2;太郎(主語)はサラリーマン(補語)です。
言語の基本は名詞だと思う人が多いようです。そもそも実際の品物を見てこれを口で出したある音で示したというのは、ヘレン・ケラーの伝記に生き生きと描写されているように、とてつもなく革命的なことだったに違いありません。その後抽象化が進み、「愛」とか「雰囲気」などという名詞まで作られるようになりましたが、相手の言語がわからなくても名詞だけを叫べば何とか通じる場合もあるところを見ると、言語の底辺をなすものなのです。
名詞の最も重要な働きは<主語>と<目的語>の2つです。主語は動詞の動作主や原因を示すためにあり、目的語は主語以外に動詞がどうしても付け加えておかなければならない”名詞による情報”を示すためにあります。つまり、多くの言語では動詞が中心になっていて、名詞は主語や目的語のかたちで動詞にコントロールされているといえます。
さらに3つ目としてこれらの主語か目的語を説明するときに必要とされる<補語(属詞)>としての役割もあります。これは性質を表す場合は形容詞が大部分を占めますが、職業名などは少ないながらも名詞も一役買っているのです。例2では「太郎=サラリーマン」の関係を結ぶために補語を用いています。
(3)動詞活用とそれを中心にした文型
例文1;太郎は歩く。 (名詞1個)
例文2;太郎は杖を使う。(名詞2個)
例3;その男は女からハンドバッグを奪った。(名詞3個)
名詞と違って、動詞は文全体を引っ張ってゆく“機関車”です。<人称・動作の完了・未完了、時制、現実・非現実・思考内容>など、いずれも動詞を何らかの形に変形、または他の文字や語を追加させることによって表すことがおこなわれています。そして動詞そのものがコミュニケーションの中心的役割を果たすためには、さらに名詞の助けを借りなければなりません。
その名詞のつき具合がいつも違っていたのでは混乱を来します。そのため動詞を中心とした特別な組み合わせが決まってきました。これが<文型>です。例1のように主語と動詞だけでもすむ場合もあれば、例3のように名詞を3つも追加して、さらにその間に結合のための語(日本語では助詞)をあらたに追加しなければならない場合もあります。
文型は語順が厳しく決まっている場合もあります。一般の人々が使いやすいようにパターン化されたものができあがっていったのです。他動詞・自動詞といった区別もこの分類に含まれます。英語では<基本5文型>が広く用いられています。
人類は言語を使い、動詞を中心に発達させてきたとき、困った問題に直面しました。それはある動詞はそのままで言い切れるが、ある動詞はそれだけではどうしても情報不足で何らかの名詞をつけ足さなければならないことがわかったからです。
たとえば人々が地表を移動するとき、「歩く」「走る」「泳ぐ」は誰がそうするか(主語)が明らかであれば問題なく使えるわけです。ところが人々が自分の手で何かをするときに「つかむ」「切る」「握る」「運ぶ」だけでは不足する。誰がそうするかを明示するのに加えて、「枝を・つかむ」「肉を・切る」「棒を・握る」「石を・運ぶ」と言わないわけにはいかなくなったのです。つまり名詞による情報がひとつ余計に必要になったわけです。
このようにして主語さえあればそのまま使える<自動詞>と、必ず主語のほかに名詞をつけ足さなければならない<他動詞>の2種類を使い分けなければならないことを悟ったのです。ですから、この2種類はたいていの言語に存在し、日本語と英語の場合も同じです。
(4)形容詞の働き
例文1;重いかご(形容詞+名詞)→←かごは重い
例文2;花でいっぱいのかご(形容詞句+名詞)→←かごは花で一杯だ。
例文3;私が花をいっぱい詰めたかご(形容詞節+名詞)→←私は花をいっぱいかごに詰めた。
名詞が単独では十分に内容を伝えることができない場合があります。「かご」をもっと細分化して表現したい。それで名詞を修飾して他と区別をつけるもの、つまり<形容詞>が必要になりました。形容詞は名詞のために存在します。
例1と例2は、構造を変えることができます。「赤い花」<限定用法>では「赤い」が「花」を直接修飾しているのですが、節である「花は赤い」<叙述用法>では「花」という主語に対して「赤い」は補語となり間接的に説明しています。多くの人々が日常会話でこの二つのタイプの違いをあまり意識しません。ですが、いずれにしても名詞と形容詞との強い結びつきがあります。
限定用法の形容詞の場合には、その修飾する部分に注目して「語・句・節」のレベル分けの原則が使えます。それによって<形容詞・形容詞句・形容詞節>の使い分けが生まれました。日本語ではこの3つの違いはあまり目立ちませんが、英語をはじめとする西欧語では形容詞節をはじめるときに文の先頭に<関係詞>をつけるのです。そして修飾される名詞は先頭に来ることから<先行詞>(日本語での「底(てい)」にあたる)と呼ばれています。
関係詞の使い方は、日本語のように<連体形>を使うものとまるでかけ離れているように見えますが、意外と共通点があるものです。それは”ある文中の名詞部分を取り出してそれに対して残りの部分で修飾する”という発想です。おそらく起源をたどれば人類の歴史のどこかで、名詞を文で修飾するという方法が大きく分岐したのだと思われますが、形態が変わっても基本的アイディアは本質的な違いに至っていないことが判明したのでした。
(5)副詞の働き
例文1;急いで食べた。(副詞+食べた)
例文2;新聞を読みながら食べた。(副詞句+食べた)
例文3;風呂に入っていたとき、彼女がやってきた。(副詞節+彼女がやってきた)
名詞以外の語に対しても修飾は必要です。形容詞との「分業」から生じたのが<副詞>です。名詞の場合と違い、副詞の役割は広範囲にわたります。単に動詞にかかるだけではありません。「場所」「時間」「理由」「原因」「目的」「様態」「付帯状況」など特殊な関係を必要とする修飾部分はたくさん存在します。
しかし<形容詞+名詞>との固い結びつきとは違い、修飾される側にとっての重要度によって置かれる位置はさまざまですし、文型などと違って取り外しがきき、普通は語形変化をしないのが特徴です。副詞の場合にも「語・句・節」のレベル分けの原則が通用する場合があります。それによって<副詞・副詞句・副詞節>の使い分けが生まれました。
例1の場合ですと「急いで」は「ゆっくりと」とか「猛烈に」とか「だらだらと」などのように食べ方についてのさまざまな様子を表現していますので<様態>をあらわすと考えられます。このタイプでは英語でも日本語でもたいてい単語1語ですみます。多くはもとが形容詞から派生したものであり、特に日本語では<形容詞の連用形>と呼ばれているものもありますし、英語では「 slow → slowly 」のように語尾変化だけで副詞に早代わりするものも少なくありません。
これに対し、例2のように「私は食べた」と「私は新聞を読んだ」という同一の主語に基づく文が同時または連続しておこなわれた場合、一方をもう一方に”従属”させることができます。日本語では「・・・ながら」とか「・・・して」などを使い、英語では<分詞構文>や<不定詞構文>というタイプの表現を用いることが多く、これらは主語と動詞をきちんと伴った文ではないので、副詞と副詞節の中間的存在ともいえる<副詞句>だといわれています。
例3では「(私が)風呂に入っていた」と「彼女がやってきた」とは主語が違いますし、前者は継続中の動作、後者は瞬間的動作だという点でも異なります。このように多くの点で異なる文であっても一方に従属させるときには<副詞節>が利用されます。
これは主語と動詞の基本構成は守られた上で、英語では文の先頭に<接続詞>を、日本語では文の最後に<接続助詞>をつけることによって作られます。接続詞には時、条件、譲歩などさまざまな働きのものが用意されていて必要に応じて入れ替えることもできます。ここまでくると副詞節は主節から非常に独立性が高くなっており、特に日本語では慣習的な使い方を誤ると、前後のつながりが不自然になり奇異な文章ができてしまうことも少なくありません。
(6)結合のための語
語と語、句と句、節と節などただやみくもにくっつけただけでは混乱をきたしますから、それぞれの部分に特定の機能で結合していることを示す語(接続詞、疑問詞、介詞、前置詞、後置詞、助詞など)が発生しました。実生活の具体的な品物との結びつきから出発した名詞などと違い、これらは純粋に文法的な必要性から生まれた点で非常に画期的です。この時以来、人類は言語を本当の意味で抽象的な道具として使いこなすことができるようになったのです。
まずは2つの単語を平等な立場で結びつけることから始まります。「そして and 」、「しかし but」 、「あるいは or 」などはその代表的なものです。しかしそれでは足りず、一方の語<修飾語>がもう一方の語<被修飾語>につながっていることを示すために多くの場合、修飾語のほうに目印をつけるようになりました。「部屋+で in the room 」や「東京+へ to Tokyo 」などの「で」や「へ」がそれにあたります。
例文1;野球は中止だ。(単文)
例文2;野球は中止で、入場券は払い戻される。(重文)
例文3;雨が降り始めたので、野球は中止だ。(一方が理由;複文)
文についてはさまざまな形式が試みられました。このうち節については動詞が一つの場合、<単文>といいますが、特に前出の「そして and 」、「しかし but」 、「あるいは or 」を使った平等な関係で2つ以上の節と節が結びつくことによって<重文>とよんだり、主従関係ができたときには<複文(=従属節+主節)>とよんだりします。これらの呼び名は本来英語で使われていたものですが、日本語の場合にも利用されるようになりました。その結果、接続詞(接続助詞)、疑問詞が重文や複文同士を結合させる役割を持っているとされます。
(7)ダイクシス(直示)
例文1;ねえ、彼女にあれをしてくれるように言って。
例文2;そこにあるそれとって。
例文3;あんな服買ってきちゃって。
名詞相当語句の一つに<代名詞>があります。これらは「(6)結合のための語」と同様、文法的にたいへん抽象度の高い語群です。というのは名詞を完全に使いこなすことができてはじめてその代理をつとめる語を使い始めたからです。
代名詞は聞き手や読み手がすぐ理解できる<場面>でないと使うことができません。上の例文も、話者の家族の一員や友人であればすべてを了解することができますが、部外者にとってはまったく意味がとれません。
このように発話の場にいてはじめて理解できる語群を<ダイクシス(直示)>と言います。代名詞のみならず副詞にもあります。「そのように」「あのように」は方法を表し、「そこ」「あそこ」「ここ」は場所を表す働きをしていますし、形容詞の代わりをする「こんな」「あんな」も重要です。
また「君」「あなた」のような使い分けによってていねいさを表すこともできます。そのほか「あのころ」「当時」のような時間、「あちら」「向こう」などの場所、日本語の場合だと「おられますよ」のような<敬語表現>や「してもらったんだ」のような<やりもらい>、「また来るからね」のような<行く・来る>なども<場面>の理解なしには伝わりません。
「英会話」「スペイン語会話」「中国語会話」など、外国語のうち「・・・会話」の学習を目指す人は、会話のおこなわれる場面が第一に重要性を持っているので、特にダイクシスを徹底的に学んでおく必要があることがわかります。また、ダイクシスを巧みに使えば自分の語彙不足や文法力の不備をごまかせるかも・・・
********************************
以上7つの項目について構造上の基本点をあげてみました。これらの構造上の要素をまとめると「言語とは動詞の持つパターンを中心に基本文を作り、名詞(相当語句)は主語・、目的語・補語を担当し、形容詞(相当語句)は名詞と関係を持ち、副詞(相当語句)は名詞以外と関係を持ち、これに結合のための語群とダイクシスを加えて文の拡大に備えている」ということになります。
世界のどの言語を勉強する場合でもこれらの要素が入っていると思っていいでしょう。(ただし世界の数千ともいわれるすべての言語を調べ上げたわけではないのであくまで仮説の段階ですが・・・)だとするとここが肝心な点ですが、動詞→動詞、形容詞→形容詞というような場合、異なる言語間でもかなり確実な「対応関係」があるということになります。
世界の言語がいくら多様で奇妙な言い方があっても、どれも人間が話すものである以上、構造のみならずもっと抽象的ないくつかの観点(文法カテゴリー)に沿って整理すると、共通点がいろいろ見えてくるものなのです。一般に文法カテゴリーとは「テンス・アスペクト・モダリティ・ていねいさ・ヴォイス・肯定否定」の6種類のことをいっています。それぞれの言語がどんな性質をもち特徴は何かを考えるとき、この6つの観点から見てゆくのも一つの方法です。各言語を比較するには非常に役立つ基準です。
(1)テンス・アスペクト
一般の人は言語を勉強するときには必ず現在や過去についてしっかり述べる必要があると思っているようです。確かに英語を中学校ではじめて習うときもまずは、じっさいの話者がいる現在、さらにそこを基準にして過去、未来についての時間をきちんと表現しなければならないと教えられます。これらは<テンス(時制)>といいます。さらにことわざや真理については普通、現在形で示されますが、<超越時制>などというものを特別に設けている言語もあります。
意外だと思われるかもしれませんが、言語には現在形・過去形・未来形などの時制が必ずしもなくとも、何とかやっていけるのです。というのは「明日」とか「昨日の午後2時」のような言葉が付属していれば、聞き手は時制を明示した動詞がなくともその時間を推定することができるからです。世界の言語には特定の時制がないものも少なくありません。中国語などはその典型的な例です。
コミュニケーションにとって時間の設定よりも実はもっと大切なものがあります。時間の流れは川の流れのように途切れなく連続しています。上流か中流か下流かについてははっきりさせておくのがテンスの役割です。これに対して実際の物事の生起には”始まり”と”途中経過”と”終わり”があり、今述べていることがそのどの部分にあるのかも正確に伝える必要があります。
動詞「食べる」ひとつをとっても、一連の流れというものがあり、「食べようとする」「食べ始める」「食べかけている」「食べている」「食べてしまった」「食べ終わる」のようなさまざまな<アスペクト aspect (位相)>を想定することができます。日常生活における言語の運用はその点の明示に最も重点をおいています。特に「終わった」のか「終わってない」のかの区別が一番気になるところです。
あなたが昨日午後6時に「食べてしまった」、今ちょうど「食べてしまう」、明日の正午に「食べてしまう」のはいずれも<完了>に属します。テンスの細かい相違はほかの単語の助けを借りればできることですが、少なくともその動作・変化が終わっていないのか、終わってしまったのかだけはきちんと伝えておく必要から前者は<未完了>、後者は<完了>という区別はどの言語でもするようになりました。このことは人類の生活における重要なコミュニケーションの要素であることが判明しました。
例文1;散歩中です。He is walking now. (未完了)
例文2;10キロを歩きました。He has walked 10 km. (完了)
例文3;昨日10キロを歩きました。He walked 10 km yesterday. (過去のできごと)
よくある思い違いは<過去>と<完了>をごっちゃにしてしまうことです。英語での過去とは5分前、3時間前、100年前のできごと全般を指すのであって、それが位相の面から完了したかしなかったかについてはなにも言ってはないのです。一方、完了とはそれが行われる時間が、過去・現在・未来のどれであっても、位相の中の最後の段階を示すだけなのです。一方、英語の<進行形>というのは継続中の動作を表すことにより、ことさら未完了であることを強調しています。
英語のように普通の時制の区別の他に、<現在完了><過去完了><未来完了>などとそれぞれの時制に細かく分けるものもあれば、アラビア語のように<完了形>と<未完了形>の二つのタイプの動詞変化を用意するだけのものもあるし、中国語のように完了形のしるしとして動詞のあとや文末に「了 le 」をつけるだけのものもありますし、ロシア語のようにひとつの意味を持つ動詞について完了動詞、未完了動詞がはじめから決まっているものもありますが、形式は違えども言語生活ではどうしてもこの区別は必需品なのです。
英語では時制の区別が非常に細かく、「公認」のもので12種類もあります。日本語は、明確な現在形、過去形、未来形といったものはありません。現在形と未来形は混ざってしまっているようでもあります。一方、「読む→読んだ」のように動詞の<タ形>というものがあり、これを一般に過去形とよんでいますが、実際のタ形は完了を含むもっと広範囲の状況を担当します(後述)。したがって世界の言語の中で見るとむしろアラビア語などに近く、このタ形は<未完了>に対応する<完了>のはたらきに近いのではないかと思われます。
(2)モダリティ(ムード)・待遇表現
例文1;明日は雨です。It is going to be rain tomorrow. →明日は雨かもしれません。It may rain tomorrow.
例文2;彼は病気です。He is ill. →彼は病気のようです。He seems to be ill.
「かもしれない」「だろうよ」「だぞ」「らしいね」などという言葉を聞けばその会話の場の雰囲気(ムード)を想像することができます。話し手が怒っているのか、喜んでいるのか、悲しんでいるのか、ふざけているのかについても言語は伝えるためのさまざまな工夫をしてきました。文の構造はしっかり研究されていても、意外にこの面は複雑で体系的にまとめるのがむずかしい。しかも話し手個人によってさまざまな状況のもとで使い分ける癖も違っています。
言語によって示される実質的な「内容(コト)」に対して、話し手の主観的判断(推量、可能性、確信など)や、「対人」関係から生まれる聞き手への態度(依頼、命令、懇願など)を表すための表現方法(助動詞、語尾変化、文末表現など)が必ず存在します。もしこれがなかったら言語はすべて法律の条文みたいになって味も素っ気もなくなるでしょうが、このおかげで人間感情の微妙な部分も表現できる場合があります。もちろんこれは顔つきやジェスチャー、声の調子などによっても補うことができる部分でもあります。
モダリティの表し方は言語によってじつにさまざまです。それは背景となる文化が大きく関わってくるからです。主張を当然と思うか、控えめを美徳とするかによってまるで違った点に強調がおかれることでしょう。そして会話では語調や声の強さ、高さが重要な役割を果たしています。
使用される品詞も異なっています。英語の場合ですと can, may, will, would に代表されるような<助動詞>がその主役を占めていますが、日本語の場合には語尾のことば<終助詞>がその役割の多くを担っています。これは<文末表現>といわれ、肝心の主張や肯定否定、感情の微妙な動きが最後の一言で決まるわけです。
例文3;出て行きなさい。 Get out. →出て行け→出ていけってんだ。
例文4;太郎は医者でやがる。←太郎は医者さ。←太郎は医者だ。→太郎は医者です。→太郎は医者でございます。
日本語には「デス体」「デアル体」を基本に、その上に「丁寧語」「謙譲語」「尊敬語」があります。さらに社会的地位や地域、集団によりさまざまな文末表現が存在しています。このように話者が聞き手や文中の人物に対しての敬意の多少が変わる度合いを<待遇表現(ていねいさ)>と言ったりします。日本人の多くはこの文末表現を聞いただけでその人の社会的立場をほぼ理解できるのです。
世界の言語にはこのタイプの違いが厳重に守られているものもあれば、ほとんどそういう違いにとんちゃくしない言語もあります。西欧語では日本語のような細かい違いはないものの、たとえばフランス語での「tu テュ(君)」が親しい間柄で使われ、「 vous ヴ(貴方;あなた)」があまりよく知らない間柄で使うといったような区別は存在します。英語では男子に対する敬称 sir が有名です。
一方、敬意が減少すると今度は<ぞんざいさ>、<さげすみ>の表現が出てきます。これらの使い分けは相手次第、または場面次第だといえます。こうなりますと待遇表現の守備範囲はおおいに広がり、相手への悪口雑言も含めてもいいのかもしれません。
(3)肯定否定・ヴォイス
肯定否定
英文法に代表される西欧語の考え方によると、文をその性質の観点から分類すれば4つになります。<平叙文><疑問文><命令文><感嘆文>となりますが、それぞれが肯定形と否定形を持っています。つまりどんなタイプの文でもこの区別は必要なわけです。
例文1;私はその仕事を全部した。 I did all the assignment. (肯定)
例文2;私はその仕事を全部はしなかった。I didn't do all the assignment. (部分否定)
例文3;私はその仕事をまったくしなかった。I didn't do the assignment at all. (全部否定)
また、文の内容を完全に否定する<全部否定>か、一部だけ否定してのこりは肯定のままにおく<部分否定>の二つの区分があります。現実は、肯定か否定かできれいに割り切ることがむずかしく、自然にこのような表現が生まれたのでしょう。これらについてはどの言語でもその区別は注意が必要です。
例にあるように日本語での「部分否定」は「・・・は・・・ない」「・・・というわけではない」「・・・とはかぎらない」などがあり、中に「ハ」が含まれることが特徴になっています。これに対し、英語では主に not に対し、all, every のような形容詞、always, necessarily, completely のような副詞を組み合わせて作ることになっています。
例文4;富士山ほど高い山は日本にはない・どんな山も富士山ほど高くない。 No other mountain in Japan is as high as Mt.Fuji.
例文5;東京ほどレストランの多いところはほかにない。Nowhere are there so many restaurants as in Tokyo.
英語では not, no, never, none, nowhere などのような n タイプの否定語以外にもたくさんの否定語が作られており、品詞もさまざまなので、文全体、動詞、名詞、その他に対して個別に否定にすることができます。ですから主語をいきなり否定することもあるわけです。主語の前に No / Few / Little などがくればもう否定文であるとすぐわかります。
例文6;彼女はその仕事をしなかった。(事態の否定・・・別のことをした?)) She didn't do the assignment.
例文7;彼女がその仕事をしたのではない。(判断の否定・・・別の人がした?別のことをした?)It wasn't that she did the assignment.
ところが日本語では述語に否定を集中する形式です。つまりどこが否定されているにしても必ずその文の最後の部分に「・・・ナイ」が来ることになっています。ですから文が最後に達するまでその文が肯定なのか否定なのかはわかりにくくなっています。そのためどの部分を否定にしているのか、<焦点>をきちんと定めなければなりません。
例文8;明日は雨が降らないと思う。(??明日は雨が降るとは思わない。) I don't think it will rain tomorrow.
一方、複文になると二つの文のうちどちらが否定されるかが問題になってきます。特に日英の間で目立つのは think の否定の場合です。think は hope, wish, find などと違い、否定なら早めに(つまり that以下ではなく主節に)否定を打ち出す傾向にあります。日本語の場合はどちらが自然でしょう?
例文9;なぜ行くの?Why do you go there? (肯定疑問文)
例文10;なぜ行かないの? Why don't you go there? (否定疑問文)
例文11;誰が知っているか Who knows? →誰も知らない Nobody knows.
例文12;誰が知らないというのか Who doesn't know? →誰でも知っている Everybody knows.
疑問文の場合も、肯定否定の区別は重要です。肯定疑問文は一般に否定の答えを”期待”し、否定疑問文は一般に肯定の答えを”期待”しているものです。
雨の日です。出るのがおっくう。夫;「今日は買い物に行くの?」妻;「いいえ、やめたわ」ここで夫は妻に買い物に行かないほうがいいのでないかという気持ちを持ちながら質問しています。勉強部屋で。母親;「今日は勉強しないの?」子供;「もちろん、するよ!」では、母親が子供に今日も勉強をやるようにという”無言の圧力”をかけたいと思っています。子供のほうはそれを敏感に感知して返事をしています。
日常生活におけるこの傾向を極限にまで強めたのがいわゆる<反語>です。自分の正反対の気持ちを疑問文の中に表しています。その典型的な例が、例9、例10にみられるわざと疑問文にしてその真意を相手に悟らせる<修辞疑問>です。このように肯定否定は、単なる事実の伝達のためだけではなくもっと幅広いコミュニケーションの道具として大いに役立っていることがわかります。これは英語、日本語のかかわらずどんな言語にもある、ということは人類共通の伝達方法なのかもしれません。
ヴォイス
主語である人やものが外部にたいして働きかける文を一般に<能動文>とよんでいます。私たちが日常生活で普通考えつく表現形式はたいてい能動文です。ところが人やものが外部から働きかけられる場合もあるわけで、そのような場合には<受動文>が必要になります。
受動文はいきなり作るよりも、すでに対応する能動文があるならばそれを利用して変形するのがもっとも簡単です。ですから世界の大多数の言語は、動詞の<受身形>というのを作っておいてそれを利用して表現しています。
例文1;太郎は花子を殴る。Taro hits Hanako. →花子は太郎に殴られる。 Hanako is hit by Taro.
英語をはじめとする西欧語の場合には他動詞の目的語(場合によっては前置詞の目的語)を主語にしたあと、動詞の受動パターンを続けるのが通例です。ですからこのタイプの受動文は能動文から一定の手続きをへて作り出すことが可能です。主語が入れ替わることにより、話の”重心”が変化します。
![]() _
_
HOME > 言語編 > 英語 > 日本語から英語へ > 02
© 西田茂博 NISHIDA shigehiro